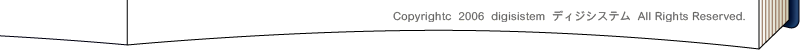はじめに・第1章・第2章・第3章・第4章・第5章・第6章・第7章・第8章・第9章・第10章・最後に
Ⅹ しっかりと取り組む
(1)中途半端では変われない やる気の問題は、中途半端では変わらない。意識の問題だからだ。意識を変えるのは人の決断である。また、親の側で先に心が折れている場合、子どもの側もその姿を見て、その程度のことだと認識してしまう。最初から「微塵の迷いもない形で物事に重要な課題であるのが当たり前」という感覚で取り組んでいく姿勢が重要だ。
(そんなことができるはずがない!)と読者が保護者の立場の人であれば、感じている人もいるかもしれない。もし仮にそうであれば、自分ができないことを子供に強いることになる。うまくいく家庭ではどちらかといえば、保護者の側で大きな迷いがないことも多い。したがって、最初はうまくできずとも、少しずつでも慣れていくことが大切だ。親が業者や企業に丸投げしてうまくいくこともあるが、両親が力になればもっとうまくいきやすくなる。子供にとって親ほど大きな影響力を持つ存在はこの世に存在しないためである。
もともと『やる気を引き上げる』ということは、教育業の中でも最難関の難事業だ。これが(相当お手軽にできることなんだ)という認識がある場合、最初から見積もりがズレていてうまくいかないということも多い。受験勉強も同じで、一日に1時間しか勉強していなかったけれども、東大を受けてみるというのはまず、ほぼ確実にうまくいかない。(なめてました。すみません。)というふうに思うのは、センター試験で30点くらいの点数が帰ってきた時である。
時間も労力も費用も惜しんでなんとかしたいという気持ちはよく分かるが、がんばることができない人の頭の中の刷り込み(数十年で刷り込まれた意識や思い込み)を取るだけでも相当な困難が伴う。「お前なんか無理に決まっているだろう」と塾や学校で教師、友人から言われる人も多いのが現実である。
(2)親がよい協力者になっている家庭の強さ 親が良い意味での協力者になっている家庭は強い。親子の力で難しい局面を乗り切っていく。
(3)まずは状況分析を
最後に、状況を分析するシートを用意したので、取り組んでみてほしい。
「モチベーション管理分析シート」(右クリック⇒保存でダウンロードが可能。) (4)具体的な問題を解決していく
モチベーション管理シートに記入すれば、どこに問題があるのかが具体的に見えてくるはずだ。ここでの注意点は、適当な一般論で対処しないことである。 よく子供のやる気の問題などについては、「褒めればいい」、「上手くほめろ」などの指導がなされることがあるが、このようなことをやっても、強いやる気は起きにくい。その場だけの弱いやる気は起きるが、だんだんと効果も無くなってくる。むしろ、「アンダーマイニング効果」と言われる作用により、逆に大きくやる気が減退してしまうこともある。外的な報酬がなくなった途端に一気にやる気がなくなることもあれば、自分が操作されていると感じれば、逆にやる気がなくなるということも研究されている。(操作されてたまるか)と思うわけだ。 私の場合、褒めることはあるが、本音しか言わない。褒めることをテクニック化するのは一種の心理操作だ。だからやらない。良いと思えば褒めるし、ダメなところはハッキリとダメだと伝える。逆に褒めてもらっているなどと思うのは褒められる側の一種のおごりで、それだけ強く気を使ってもらっていると考えているということだ。こういう考えの方がむしろまずい。既に大きく気を使ってもらっているというように考え始めている時点で甘えや依存心が芽生えているからである。 (5)「かわいい子には旅をさせよ」
10-5-1 厳しさの価値 10-5-2 親が子供の意識を作っている 10-5-3 今変わらなければ、問題は起こり続ける まずは「モチベーション管理分析シート」に記入し、真剣に問題に向き合うことが重要だ。
フラットな状態でいいものはいい、悪いものは悪い、と言い、気を使うこともしなければ、逆に意地の悪い物の見方もしないことは、大切だ。(何かしてもらっている)と感じるよりは、(何もしてもらっていない。)と感じているくらいの方がいい。事実そのように接する。
都合のいい時だけ保護下にある人格で、都合が悪くなると、大人としての人格を持つという二重の人格利用を思春期の子供や相手に許さない態度を普通に取れば、相手の意識も変わってくる。一人前の大人の人格として接する準備を少しずつ進めるということである。もしかすると、今この文章を読んでいるあなたは(厳しい)と感じるかもしれない。しかし、その程度の厳しさが持てなければ、自立型教育などは、夢のまた夢であるということは、伝えておきたい。厳しいことをマイナスに捉えるのではなく、厳しいことこそが相手のためであるという考え方が大切だ。
往々にして、自分の将来に関心が無く、勉強をする意欲が湧かない学生は、子供の人格のまま成長していることが少なくない。もちろん若い世代ゆえ、子供の人格があるのはむしろ普通だが、問題はその人格をアルバイトをしても、大学に推薦や妥協で入学しても、就職しても引きずるということである。ニートになる、フリーターになるなどの行為は、家族全体で作っていることもある。
放置して解決する類の問題と、放置では解決しない問題がある。やる気の問題は多くのケースで放置したままでは、解決せず、時間がたてばたつほど問題は深刻化していく。時間が先へと進めば進むほど解決しにくくなる。