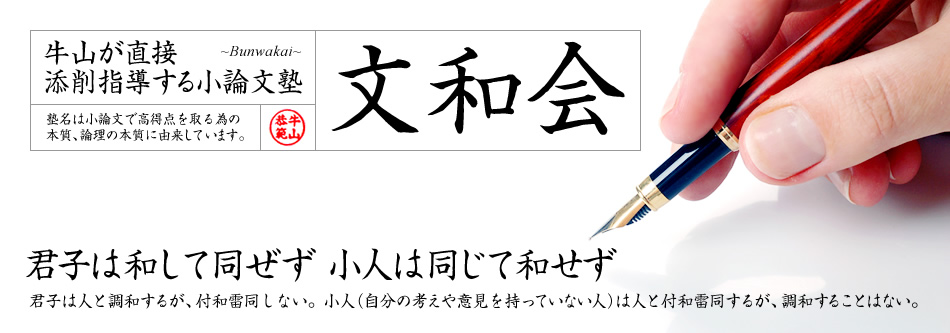~全国模試小論文1位の報告を3年連続でもらっている牛山の過去問題解説ページです。~

東京大学文学部 推薦入試 小論文 過去問題 平成28年度
問題1
問題1 解答例
見聞や体験を文章で表現することは、文化人類学者が常に突き当たる問題である。観察し、文章に表現するという行為は私の主観によって対象を切り取ることだ。だが対象の方も私と同じ資格で彼らなりの主観に基づく世界を構成しているのだ。心や価値観にかかわる、つまり意識の構築物となれば、日本語の概念と「彼ら」の概念との不一致、対象と表現されたものの不一致は、ますますひどくなる。このような乖離は狭めることはできるだろう。分かっているように、錯覚しているからこそかえって危険だという見方も成り立つだろう。標準化された日本語で理解し合う同じ日本人でも、地方により、職業により、生活圏により、ひいては個人によって少しずつ持っている文化は異なる。彼らの言葉と概念と感性の世界に、可能な限り入り込み、感情移入する努力をすること、それでいて表現する主体としての私の主観を保ち続けること、その私を相対化できる冷めた目をいつも持っていることの三つを、私は自分に目標として課している。だが、その三点の緊張関係を保とうと努めていながら、いつも気がつくことだが、異なる文化の中での体験で、自分の心にもっともしみこんだ瞬間は、記録されていない。主観だけになってしまったものに表現の上で客観性を与えること、それは、前に述べた私とは著しく異なる「私」の外にある対象を、主観によって切り取って表現する難しさの反対の極にある表現の難しさであろう。
以上が著者の議論である。著者は、相手目線、自分目線、客観的目線の3点を重視した上で、研究生活で印象深いものは記録されていないと述べている。記録されていない内容について述べる際には、主観的な自己正当化とも言える表現になること著者は恐れている。それでは、異文化を記録表現することの難しさとはどのような点にあるのだろうか。
私は主観と客観を切り分けて、自分の中で考えることが、異文化を記録表現することの難しさであると考える。主観と客観を切り分けるとは、自分の思考内容、考察内容について、何がどこまで自分の主観であり、何がどこまで、客観化できるのかを考えることである。
上記のような「主観と客観を切り分ける作業」は簡単なようで難しい。著者が述べるように、印象深いことは、記録されていないことが多いためである。仮に研究ノートのようなものを用意して、フィールドワークの内容を言語化しようと勤めていた場合、その自分の考察対象を文字により客観化することができる。このケースでは、自分が何をどこまで認識できており、仮につたなく、仮に主観が入り込み、自分が100%の客観的思考ができていなくても、それなりに自分の主観を排除しようとする自分に気づくことができていることが少なくない。ところが、著者が述べるように、「主観だけになってしまったもの」と呼べる自分の考察内容については、はたしてどこからどこまでが自分の主観で、本来の客観的な対象の認識はどのようにあるべきかについて、はなはだ不明確である。表現行為とは、考察内容のクリアな概念化に他ならない。そのため、もし研究プロセスにおいて、自分が考察する内容が、主観的な世界の認識であるのか、客観的な世界の認識であるのかについて、不明瞭になった場合、必然的に自分の表現は、研究的な立場から見て、妥当性を欠く可能性がある。
以上の理由から、私は、異文化を記録表現することの難しさは、主観と客観を切り分けて自分の中で認識し、考察することであると考える。
問題1 解説
問題2
右の文章に関して、あなたの考えを1000文字程度で述べなさい。
問題2 解答例
プルーストと、ポール・ヴァレリーの考えはどちらが妥当なのだろうか。私はプルーストの立場を取る。
芸術の価値について、私は3点あるのではないかと考える。第一の価値は審美性である。第二の価値は、表現性である。第三の価値は、情熱性である。審美性とは、美しさのことであり、表現性とは、芸術家が表現することを望んだ世界のことである。情熱性とは、その表現行為そのものに対する芸術家の想いである。
芸術を論じる時に、私たちが気をつけなければならないことは、芸術の特権化かもしれない。芸術をどの目線や立場で論じるのかについて、仮に芸術家本人が特権化を望んだとしても、そのような特権化が仮に存在すれば、芸術論を広く一般化した上で、何らかの考えを導くことはできなくなってしまう。
芸術作品がその由緒や、置かれる環境や、しつらえを必要とするかどうかは、その芸術品の個別的な問題である。奈良の大仏のように、その場所になければ、意味が理解できないものもある。
仮に芸術を特権化せず、しつらえが個別具体的な問題であり、芸術に少なくとも3つの価値が認められるのであれば、プルーストが述べるように、芸術品はどこにあってもよいということになる。
前述した3つの前提(特権化、しつらえの個別性、芸術の3つの価値)は、私が仮説を導く際の3つの論拠となっている。
以上の理由より、私は、プルーストの立場を取る。
問題2 解説
今回の問題は、やりにくかった人が多かったかもしれません。
内容が非常に抽象的な分、思考がついていかない人もいたかもしれませんね。かつての京都大学の経済論文を思い出させる試験でした。
大学受験生(学部生)の問題としては難しい部類に入ると思います。
それでいて、研究活動における言語表現について言及しているという点では、入試問題としても良問と言えます。
ところで、なかなかやりにくそうな要約問題が出ています。
この文章をいかにして要約するかですが、「牛山式要約の原則」について作図していますので、こちらの図のとおりに全体の文章の構造を把握してください。
●●●牛山式の要約の図●●●●
ずいぶん簡単になりましたね。

それでも、底抜けには、簡単になりませんよ。
さすが東大の問題です。

で・・・どのように考えるかですが、以下のpointに注目しましょう。
1)要は何が問題なのか
2)結局何が言いたいのか
今回の問題では、この2点に注目すると構図が見えてきます。
まず、要は何が問題なのかですが、それは、課題文に書かれています。
つまり、意識の構築物・・・・・対象と表現されたものの不一致はますますひどくなるわけである。
ということは、要は、対象と表現されたものの不一致が問題なのだということですね。
なんで?
研究だからです。
研究活動は、人に情報を提供するためにも行っていますから、対象と表現されたものに不一致があるとまずいですよね。
で・・・
その解決策も書かれているはずです。
そうやって視線を走らせると・・・・
最終段落に、
つまり、主観だけになってしまったものに表現の上で客観性を与える・・・
とありますね。要はこれが解決策であり、著者が述べたいことです。
ここが、表現の難しさなのだろう
と著者は述べているわけですね。
はい。
ここまでで、読解完了です。要約も完了ですね。
要約については、ねほりはほりこのページでは行いませんが、要は、私が教えている「理解速読」という手法を用いると、簡単に要約ができますよ。
ところで、ここから考察問題です。
1000文字程度で論述することが求められていますね。
長い~
と思う人もいるかもしれませんが、私が大学院博士課程を受験した時は、2時間で6000文字の論述でしたよ。
ざっと3倍以上書く必要があるというわけです。それに比べたら文字数は負担が少ないですね。
ところで、この問題をどのように考えましょうか。
まさか、フォーマットに流し込むなんて、レベルの低いことを考えていないでしょうね!
東大受験生がそんなことをしたらダメですよ。
きちんと考えましょう。
問題は、
異文化を記録、表現することの難しさについてあなたの考えを自由に述べなさい
というものです。
どう考えるべきですか?
少し自分で考えてみましょう。(1分は考えてみてね。)
いかがでしょうか。
一般的な問題では、今回のケースのように、著者の主張がある場合、その主張に対して、賛成か反対かを述べます。
しかし、今回の問題の場合、1000文字論述が求められているので、それよりもずっと深い考察をしてほしいのでしょう。
このように、ある程度出題意図を見抜いていくことが大切です。
著者は、主観化されてしまった自分の思考に客観性を与えながら表現していくことが難しいと述べているのですよね。
なんで??
そこが大事です。
なぜ主観化されてしまった自分の思考を客観的に説明することが難しいのでしょうか。
解答例にちょっと答えを書いてしまっていますね。
もちろん、解答例の内容以外の内容でもOKです。
あくまでも、解答例は参考にしてもらうべき事例の一つにすぎません。
本論では、あなたは自分の仮説を論証する必要があります。
今回の解答例のように、論理を説明することで、論証とすることもできます。

イメージとしては、掘りさげですね。
考察内容を詳しく掘りさげることで、論証するイメージです。
論理関係を説明すれば、論証を試みることができますよ。
さて、いかがだったでしょうか。
学部受験生にとってみれば、難しい問題だったかもしれませんが、このように、きちんと評価される書き方、評価される考え方で問題を解くことで、はじめて高得点をねらうことができます。
少しずつ勉強を進めていきましょう。
過去問題解説者 牛山恭範


 ・スキルアップコンサルタント
・スキルアップコンサルタント
・専門家集団Allaboutスキルアップの担当ガイド
・ヤフー(Yahoo)知恵袋 専門家回答者
慶應大学に確実かつ短期間で合格させる慶應義塾大学合格請負人。慶應義塾大学合格の要である、小論文と英語の成績を専門家として引き上げる為、理系を除く全学部への合格支援実績がある。(学部レベルだけに留まらず、慶應大学法科大学院へ合格に導く実績もある。)短期間で人を成長させる為の知見を活かし、教え子の小論文の成績を続々と全国10以内(TOP0,1%以内も存在する)に引き上げる事に成功。12月時点で2つの模試でE判定の生徒を2ヵ月後の本試験で慶應大合格に導く実績もある。技術習得の専門家として活動する為、英語力の引き上げを得意としており、予備校を1日も利用させずにお金をかけず、短期間で英語の偏差値を70以上にして、帰国子女以上の点数を取らせるなどの実績が多い。慶應大学合格支援実績多数。自分自身も技術習得の理論を応用した独自の学習法で、数万項目の記憶を頭に作り、慶應大学SFCにダブル合格する。(その手法の一部は自動記憶勉強法として出版)同大学在学中に起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長について師事を受ける。ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。慶應合格のためのお得情報提供(出る、出た、出そう)ではなく、学力増加の原理と仕組みから根本的に対策を行う活動で奮闘中。現在、東京工業大学大学院博士後期課程在学。
執筆書籍
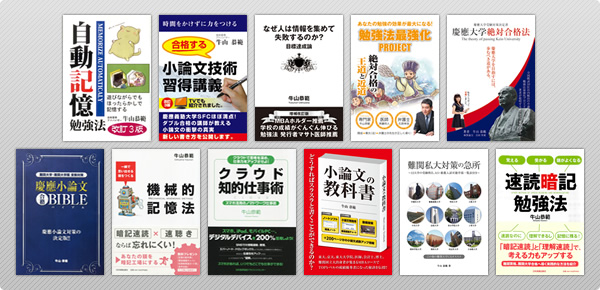
マスコミ掲載事例一部
『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』プレジデントFamilyClub様(メディア掲載)
クライアントの実績の一部
外部講師活動
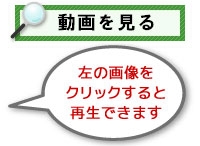 |
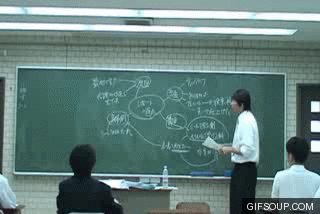 |
全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。
メディア掲載: プレジデントFamilyClub様
『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』
第2回 ⇒「慶應大学合格に必要な要素と中核」
第3回 ⇒「慶應大学合格に有効な受験対策(前編)」
第4回 ⇒「慶應大学合格に有効な受験対策(後編)」~「受け身の学習」から「攻めの学習」に変化させる~