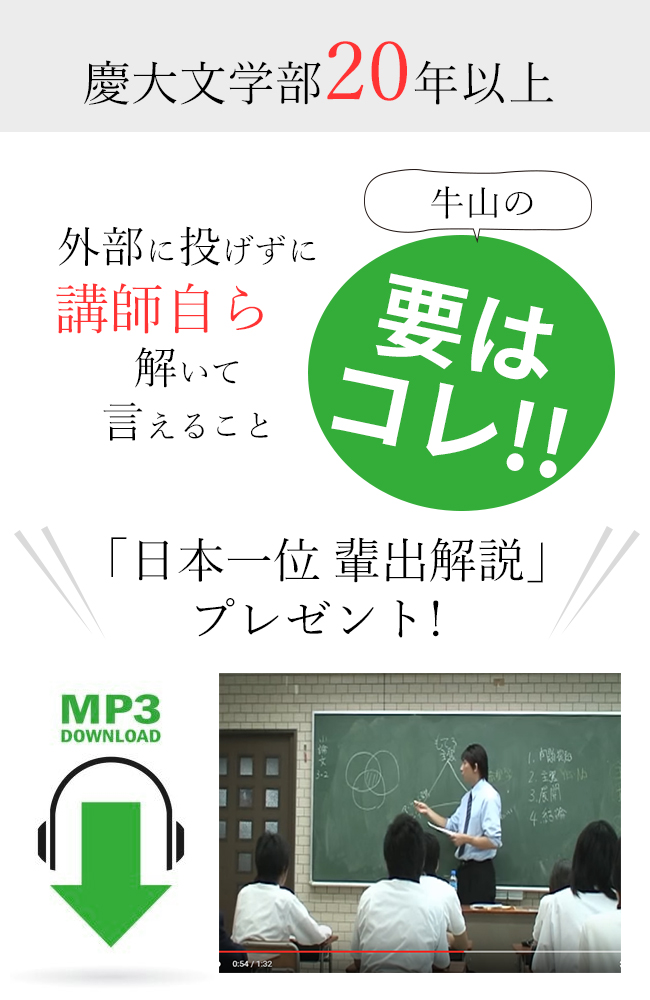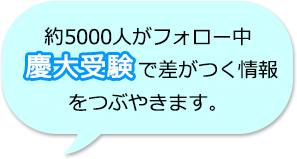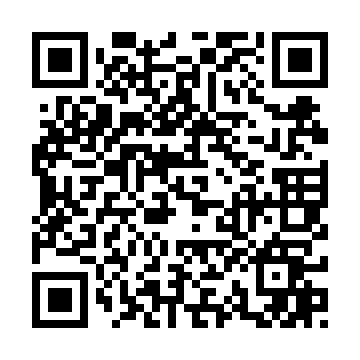このページでは、メルマガで流した慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。
慶應クラスでは、構造ノートや構造議論チャートを使ってもっと詳しく細かく各学部の過去問解説を動画で行っています。
2016年度 慶應大学文学部 小論文過去問題の解説
こんにちは。牛山です。
今回の問題は次のようなものです。
設問1
この文章を要約しなさい。
それでは、さっそくですが、課題文の要約例をご紹介します。
設問1 解答例
飼い主が犬などにつける愛称はその人物の属する階級と文化を表している。また、構造人類学の観点から見れば、犬の命名は人間の名のパラレルな隠喩である。このように、我々は見えない様々な法則に従って命名行為を実践している。人間の思考と行動は帰属する社会の構造によって暗黙のうちに規定されている。つげ義春の漫画作品では、ある飼い主に飼われていた五郎と名付けられた犬が、ある日突然姿を消し、別の飼い主にハチと命名され、のんきに飼われていたという話が出てくる。犬は自分の名前には無関心である。つまり、命名行為とは観念の虚構である。動物の立場からしてみれば、すべては人間の一人芝居ではないかと私には思われるのだ。
極限まで論理をそぎ落とすと、
①人間は自由意思に基づいて名前をつけることはできない。(構造主義)
②犬は自分の名前が何であるかを気にしていない。
③従って命名行為は観念の虚構である。
となります。
要約のやり方ですが、基本的な解き方は、重要な部分を抜き出してまとめるだけです。
具体的にはどうすればいいのでしょうか。要は次のようにやります。 ※図は、近いうちに出版される新刊の内容です。
要は、AからDまでの流れで文章を設計していきます。原則としてほとんどの文章は、A~Dのような形で構成されています。 いろいろ述べられていても、途中でまとめのような解釈が入ります。それがつまり、A、B、Cのようなパーツになります。このA~Cは、要は、結論の前提です。
今回の問題の場合、要約なのですから、筆者の最終結論に至る前提を並べて、Dの最終結論に文章をつなげていけばいいのか、、、、、と言いますと、
一筋縄ではいかない問題になっています。
上記の図の「論旨を整理する場合」を見てください。
要約の場合と、論旨を整理する場合で、どこが違うでしょうか。
要は、「テーマ」か「論点」かの違いです。
◆論旨を整理する場合は、テーマについて、話をまとめていきます。
◆要約する場合は、論点を中心に文章をまとめていきます。
【ポイント:複眼的に文章を見よう!】
従って以下のように複眼的に問題文を眺めることが大切です。
A:論旨を整理するものの見方
論旨を整理しつつ要約するように、課題文を加工し、その際に自分は何が本稿の中心命題(筆者が最も言いたいこと。)なのかを見抜くように、頭を働かせることが重要です。
そのためには、全体の論理関係を観察することが重要です。
~慶應大学の過去問題を理解しても本番読解力は高まらない!? 慶應大学に合格する読解力強化法とは
設問2
この文章を踏まえて、人間にとって「名づける」とはどのようなことかについて述べよ。
【ポイント:賛否両面検討により、問題の本質を見極めよ!】
それでは解答例を見てみましょう。
設問2 賛成側解答例
命名行為とは、観念の虚構だろうか。私は著者の意見に賛成の立場を取る。名前をつけることに意味づけを行う親がいても、名前を付けられる側は、親を選んで生まれてくることができるわけではない。従って必然的に命名行為とは、命名行為者の主観や個人的な価値観を被命名者に強制力を持って与えるものである。この名前の提供行為は、被命名者が自由な選択権を持たないという意味で、観念的であり、実態が存在しないと解釈できる。
結論を導く前提に注目しましょう。
この名前の提供行為は、被命名者が自由な選択権を持たないという意味で、観念的であり、実態が存在しないと解釈できる。
という別の理由をもってきて解答を構成しています。
それでは、反対側の解答例を見てみましょう。
設問2 反対側解答例
命名行為は観念の虚構だろうか。私は著者と反対の立場を取る。。認知症患者に対し、「755さん」 などと接しても同じかもしれない。しかし、人は名前で人を呼ぶ。「牛山艶子さん」と呼びかけることは、自分の名前を認知できなくなった人に対する尊厳を意味し、呼びかける人間の心の尊厳にも関わる。被命名者が何を認知するかの問題ではなく、呼びかける側の心の問題であるという意味で、命名行為は観念の虚構どころか、観念の完全なる実態である。
今回の反対側の解答例では、下線部(蛍光ペン)が、結論に至る重要な前提になっています。つまり、名前をつけるという行為は、名前を付けられる側だけの問題ではないということです。名前を利用するすべての人が人として尊厳を保つために、名前を呼びます。もちろん、自分の名前を認知できない人に対して、認知症患者ケアの医療現場で、「オイ、755番、飯はまだだからな。」などと言っても、何も分かっていないのですから、よいという意見も存在するかもしれません。
しかし、あなたはそんなことをしたいですか?
ちなみに、どうでもいいことですが、755番とは、有名なホリエモンこと、堀江隆文さんのかつての囚人番号です。
刑務所では、人格を排するために、囚人を番号で呼ぶのでしょう。非社会的な存在として、罪を償わなければならないことを自覚させるために、法の力で(もっと言えば、法の暴力で)強制力をもって囚人を従わせます。
名前が無い世界とは、このように人格を排し、人としての尊厳を一定程度奪う世界ではないでしょうか。
当然このような論考を反対側の立論の際に披露してもよいでしょう。
設問2では、人間にとって科学的な知識とはどのようなものなのかについて、自分の考えを述べる問題ですね。
【余談】
多くの一般的な祖父母がそうであるように、孫である私には大変優しく接してくれました。そして、山の上にある祖父母の自宅から帰るために、車に乗り込むと、男気一直線のような祖父は外に出てくることはありませんでしたが、祖母は、私たちの車が見えなくなるまでずっとにこにこしながら手を振ってくれていました。正月の寒い日に、山の頂上は特に冷え込み、ずっと雪が残ります。それでもその雪の中で名残惜しそうに、祖母は手を振ってくれていました。
とても優しかった祖母の思い出は、あなたもそうであるように、私たちの心の中で色あせることなく、ずっと生きています。
ですから仮に今回の問題の解説のように、ケアの現場で、誰かが私の祖母を番号で呼ぶようなことがあれば、私はきっと本気で怒るでしょう。仮に認知症が進み、子や孫が誰かが分からなくなったとしても、私たちの側では、はっきりとそれを認識しています。
【余談2】
ですから、意味は分かっていません。(苦笑)しかし、言葉から、どのような意味を持たせようとしたのかを考え、その考えに沿うように生きようと考えています。この意味では、私の名前について私が呼応しているという点で、観念の虚構ではなくなっていますね。
【余談3】
「あのね、ぴょんきちと、デイジーどっちがいい?」と質問すると、
ということでしたので、デイジーになりました。
そして、どうでもいいことですが、月亭ホウセイ(旧山崎ホウセイ)さんが飼っていたうさぎさんは、「にんじん」という名前だそうです。(汗
賛否両面検討で力を強化しよう!
以下の内容はおまけです。
物事を賛否両面から見ることで、論理に強くなりましょう。
死刑制度の存置に関する是非についての問題
以下の内容は拙著「小論文の教科書」の内容です。
----------ここから----------
問題
日本では毎年全国で数万件のいじめがあることが報告されており、毎年約200人の若者がいじめを原因として、自殺で命を絶っている。いじめを無くすには、いじめた側を強制退学させるか、強制転校させることが大切だという意見がある。この点についてあなたの考えを自由に論じなさい。
【解答例:賛成側】
反対側の解答例も見てみましょう。
【解答例:反対側】
あえて同じような下りの文章で解答例を作成しました。なるべく同じ個所を増やし、違いを明確にすることで、論点を中心として論争がどのように進むのかについてのイメージが膨らんだかと思います。自分が小論文を書く時には、このように、【何を争点とすべきか?】【争点についての解釈の違いで結論が変わり得る】ということを、強くイメージして下さい。
なかなか思いつかない人は、「小論文の教科書」も読んでみましょう。
過去問題解説者 牛山恭範
人を成長させる事が専門。決して頭がいいわけでもなく、勉強が得意ではなかったが独自の学習法を使うことで小論文試験が難関で知られる慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部にダブル合格する。
2009年、技術習得の理論・原理(成長の原理)を「目標達成論」(エール出版社)で発表。その他高速学習(どんな人でも大量の記憶を形成させる)を可能にする、プロフェッショナルとして、年間約3千のメールサポート・電話サポート・直接指導をクライアントと行い、累積数1万を超えるサポート実績がある。慶應義塾大学総合政策学部在学中にパソコンの家庭教師などを経て店舗経営で起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。技術の習得に関する周辺と、それを可能にする頭脳に関して研究を重ね現在に至る。(大学院では、思考力の研究を行い、研究は成功した。)現在は研究の成果を活かし、需要の多い分野で教育カリキュラムを構築し、技術を提供。
より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長より、BBT大学大学院にて問題解決思考の思考について師事を受ける。
ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者(写真) となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。
マッキンゼーの問題解決思考を上記大学院の学長である大前研一氏から直に師事を受け、各種技術習得、及び,問題解決型の 学習コンサルティングに活かした活動を行っている。
執筆書籍
・「小論文技術習得講義」(改訂版あり。)
・「自動記憶勉強法」(改訂版あり。)
・「なぜ人は情報を集めて失敗するのか?目標達成論」(改訂版あり。)
・「勉強法最強化PROJECT」(弁護士・医師との共著)
・「慶應大学絶対合格法」
・「慶應小論文合格BIBLE」(改訂版あり。)
・「機械的記憶法」
・「クラウド知的仕事術」
・「小論文の教科書」
・「速読暗記勉強法」
・「難関私大対策の急所」
・「AO入試対策とプレゼンテーション合格法」
マスコミ掲載事例一部
・読売新聞(全国版)学ぼうのコーナーにて8回掲載(週間企画)
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 会社紹介 平成23年10月7日
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 平成23年11月4日放送
・産経関西 20年前とは変わった受験事情 平成23年12月9日
クライアントの実績の一部
・教え子がダブルE判定から慶應大学に合格。
・教え子の成績がTOP0.1%に引き上がる。
・全国3位に急成長→慶應大学A判定に。
・北海道大学法科大学院次席合格。
・女子高生が2時間で速読を習得→名門津田塾大学に合格。
・医師の国家試験、公認会計士試験、薬剤師試験、弁理士試験など、難関国家試験にクライアントが合格。
・国立私立、資格試験、国家試験問わず、希望の試験に合格。
・全国模試で英語で二度日本一。
・慶應大学4学部(法・経・総・環)合格。
・大阪大学大学院主席合格。
・上記の他に、名門大学院、最難関大学院、京大、東京大学大学院などに合格実績がある。
外部講師活動
VIDEO
全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。
牛山執筆の慶應小論文対策本と書籍の動画解説
分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。 詳しくはこちら
「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース 詳しくはこちら
どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。) 詳しくはこちら
「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授! 詳しくはこちら
慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら
慶應対策丸わかりガイドのご案内
内容のほんの一部を挙げると・・・
・慶應大学に合格できる小論文の書き方とは?
無料メルマガのご案内
慶應大学総合政策学部の過去問題を20年以上講師自ら解いて言えることについて、音声解説した音源をメルマガ会員に無料プレゼントします。慶應模試2年連続全国1位(偏差値87.9)を輩出した牛山が解説します。
メルマガ会員のみの特典となりますので、ご希望の方は以下のメルマガ登録フォームにメールアドレスを記入下さい。
~メールマガジンについて~ プライバシーポリシー ・メルマガ解除
メルマガ以外でも、ツイッターやラインで情報提供しています!⇓⇓
ライン↓↓(スマホで閲覧)
ライン↓↓(PCで閲覧)
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。
慶應クラスの資料請求・お問い合わせ


 ・スキルアップコンサルタント
・スキルアップコンサルタント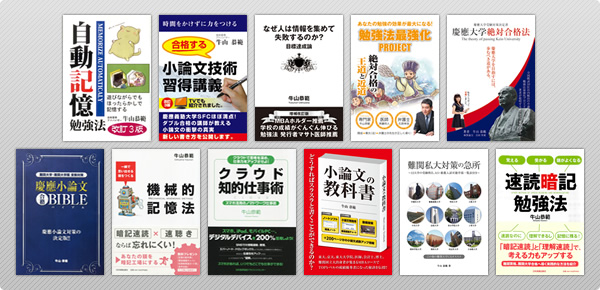
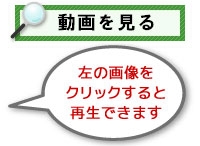
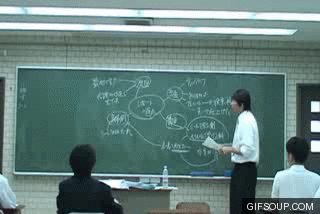


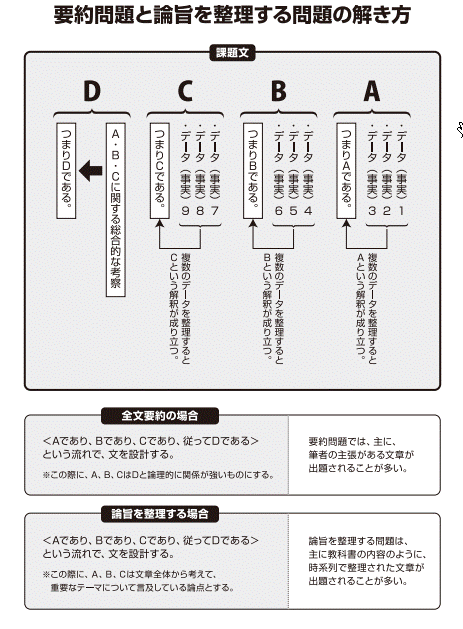

 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」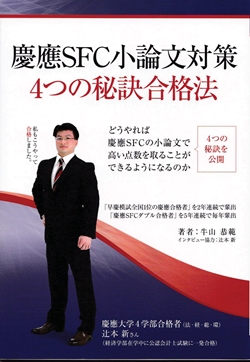 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」