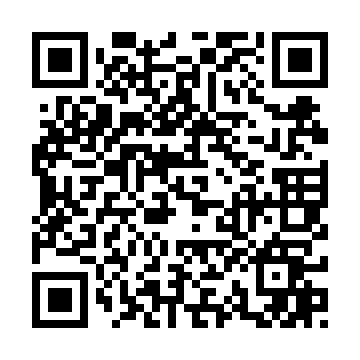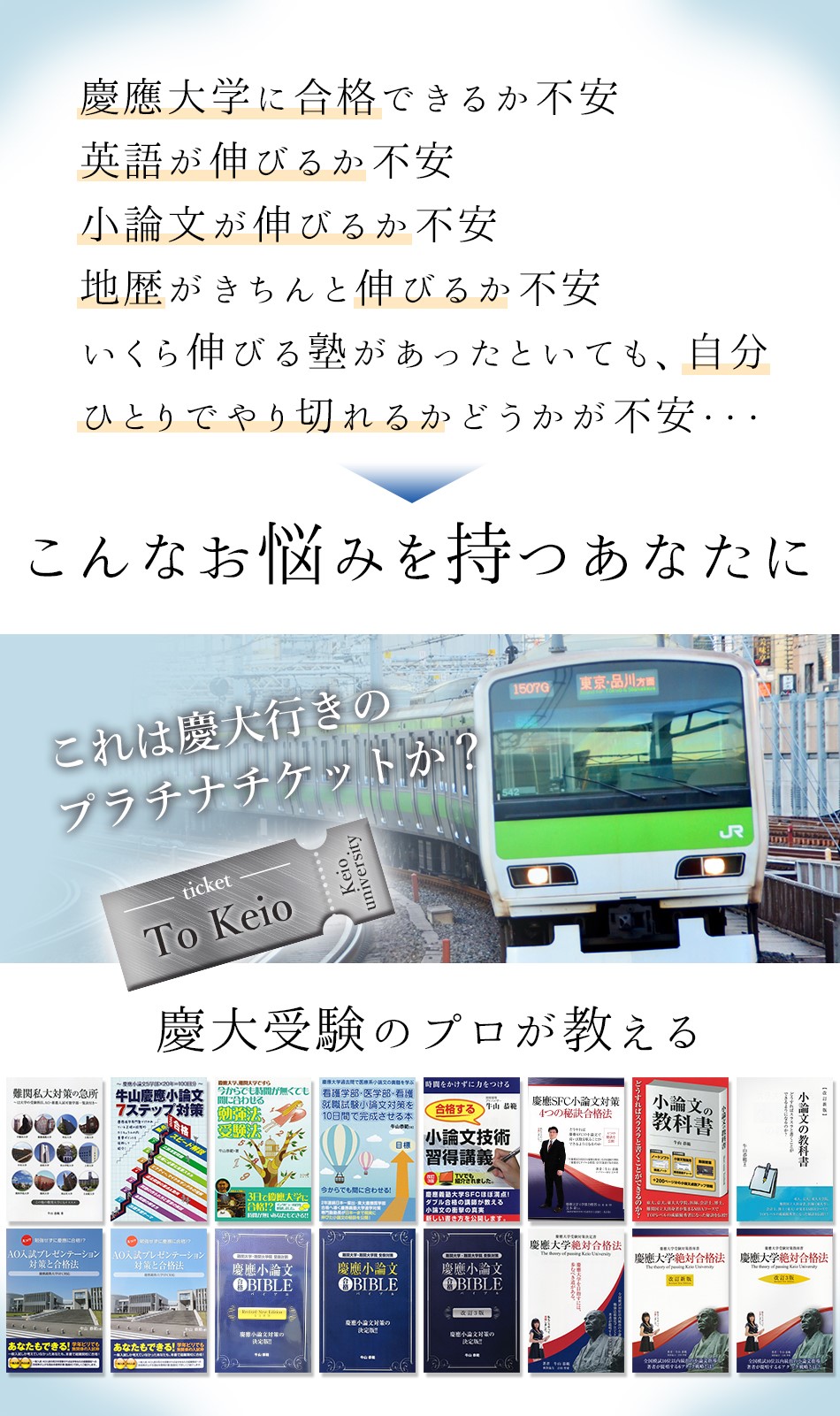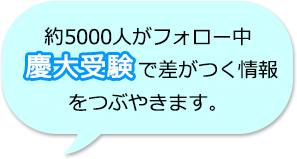
このページでは、メルマガで流した慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。 慶應クラスでは、構造ノートや構造議論チャートを使ってもっと詳しく細かく各学部の過去問解説を動画で行っています。
2014年度 慶應大学環境情報学部 小論文問題解説
こんにちは!
牛山です。
ちらほら慶應大学の合格報告が届き始めています。
ところで、慶應大学の環境情報学部の合格発表はもう少し先ですが、まずは受験お疲れ様でした。
受験生だった方は、ゆっくり休んで下さい。
【1】2014年 環境情報学部 小論文についての予想
今回の、慶應大学 環境情報学部の問題はまた面白い問題でしたね。
すぐにメルマガを送りたかったのですが、「慶應大学絶対合格法」の改訂版の校正作業について、納期が迫っていたため、急ピッチで作業をせざるをえませんでした。
みなさんの受験前は、これらの作業よりも、皆さんの合格を最優先にメルマガを書いていたのですが、環境情報学部は最終日にありましたので、今日メルマガを書いています。
さて、今回の問題はできたでしょうか。
問題の1と問題の2では、取り除きたい文章を取り除くんですね。これはユニークな問題だと思います。
実を言いますと、今回の環境情報学部の問題については、出題テーマ予想ではなく、思考回路の予想についての授業をやっていました。
その私の予想では、今年は何かを選ばせて、その選んだ理由を書かされるのではないかな?と思っていましたので、塾ではその練習をしていました。
そうすると・・・・
選ぶ理由ではなく、選ばない理由でしたね。
うーん、惜しいです。かすった感じですね。
ただし、これは物事の評価基準を考察させる問題でもありますので、その意味では練習になったかなと思います。
大学の問題によれば、何を選ぶかは点数に関係ないとのこと、その後の意味づけで、点数を与えられたり、与えられなかったりするようですね。
【2】問題3の大論述について
今回のメインはここですね。
皆さんはしっかりと書けたでしょうか。
ここの書き方にいわゆる正解はありません。正解の文章や正解の考え方が無いのと同じように、正解はありませんので、どれだけ採点側の価値観で良いと思ってもらえるかに点数はかかっています。
私なら何を書くでしょうかね。【地球と人間】というテーマで、刊行物があるのでしたら、私ならば、地球環境の本源的な部分を書くかもしれませんね。
皆さんは、地球環境がなぜ破壊されていると考えるでしょうか。
ちょっと考えてみましょう。
正解はありませんよね。いろいろな答えがあってしかるべきだと思います。
より本源的な部分を言えば、私は、人間の持っているエゴや欲望だと思います。
自分自身を正しいと思い込んだり、自分が正しく人が悪だと思ったり、自分なりの都合のよい解釈を行ったりと・・・
言い換えれば、慢心(驕り)あるいは、科学信仰、あるいは科学万能論提唱者、あるいは、エゴと言ってもいいかもしれません。
科学というのは、恐ろしいもので、我々の生活を豊かにすることもあれば、時に人の目を曇らせることもありますね。
また同時に慢心を起こさせることもあります。もちろん、科学それ自体が有害であるとは言いません。しかし一方で、この地球環境が崩壊するのもまた科学の力です。科学の力なしに、この地球が破壊されることなどありません。
私たちがどんなにはだしで大地を蹴っても地球はびくともしませんが、大規模な大気汚染や水害、核エネルギーの廃棄物などによって、地球環境は破壊されていきます。
したがって、科学を生み出した人間が変わらなければ、この地球環境は変わらないのではないかなと、私はそんな風に思うこともあります。
より本源的には、何が科学的なのかという問いはあまり簡単ではありません。
例えば、原子や粒子に名前をつけることはできますが、それらが本質的に何であるかとか、なぜあるのかということは我々は何も分かっていません。しかし、そこにある観察可能な出来事について、説明可能な範囲で、説明を試みる時、科学が現象を征服したような気分になっているのは人間の方で、実質的には何かが分かったわけでもなく、観察可能な対象を観察可能な範囲で考察可能な範囲で、考察しているだけ・・・
こんなことを述べた哲学者もいます。私の考えではありません。
しかし、的を得ているかもしれませんね。
これらの哲学者の言説と、過去の数千年の人間の営みを重ね合わせてみてみると、、上記のような考察に、私の場合は至りました。
まさしく、「環境と人間」かなと。
【3】統計的手法
科学の根幹を支える一つの指標は統計学です。
ゆえに、統計学は最強の学問である・・・という本も大変売れていますね。
私も大学院で研究指導を受けたのは、統計学の教授でした。
あくまでも、どこまでも科学的な手法で、研究を行いたいと願ったためです。研究は成功しました。
ところで・・・
おそらく私は今回の環境情報学部の問題で、「研究系」がくるだろうなぁと思っていたので、実証的な研究のやり方と考え方について、塾で授業を行っていました。
何が科学的で、何が科学的ではないのか?
どのようにデータを数値化して、どのようにそれらの数値を用いるのか。また、どのように論理的に意味づけを与え、どのようなデータは研究時に意味づけを与えることが危険なのか。
これらについて、統計解析の話も少し交えながら、科学についてのお話をしています。
上記の意味で、授業を受けていた人は、研究や実証性について具体的な感覚があったのではないかと思います。今年の問題では、2つの文章で、科学についての話がありましたね。
こういう問題は科学的手法とは何か。どのように考察し、何を調べ、調べた後に、何をどうやれば、科学的に結論を得られるのかを知っておくと考えやすくなることがあります。
世界の論文は、このような科学的なアプローチを大切に、作成されています。
このような点を詳しく解説した授業は例えば次のようなものです。
【該当授業】
・研究アプローチの基本理解 → 詳しくはこちら
・慶應クラス 思考回路予想問題
設問3について
今回のようなタイプの問題では、単に理詰めで論理的に文章を組んで答案を作成するだけではなく、どのような印象を相手に与えるのかを考えた文章設計が大事になってきます。
・感情設計理論 → 詳しくはこちら
「小論文技術習得講義」を読んでもらえれば、このあたりについてはイメージが膨らむと思います。来年受験する高校生はぜひ読んでみてください。
【4】設問4について
設問4は、プレゼンテーション(プレゼン)のスキルが大切です。どのように、自分の考えを一つのコンセプトにまとめることができるかについての力を見られています。
・紹介文で述べた内容が分かる内容
・魅力的に感じる内容
・説得力が感じられる内容(場合によってはここも必要)を考えてみましょう。
プレゼンテーションって何??と感じた人は、プレゼンテーションについていろいろと調べてみましょう。今回の問題は、あなたのプレゼンテーションの力を総合的に見られていると言っても過言ではありません。
総合政策学部も今年はプレゼンのスキルがいくらか必要な問題になっていましたが、環境情報学部も同様ですね。
社会で活躍する力の一つを大学側が見極めようとしています。
【5】編集後記 ボランティアについて
今回の課題文には、ボランティアについては、できる範囲で行動することが大切なのではないでしょうかという内容の文章がありましたね。
この文章を読んだ時に、大学院のディスカッションを思い出しました。ある人が、地球環境のために、ペットボトルかなにかについて気を付けているということを言った時に、それに対して、発言した人がいます。
たしか、「ボランティアをするのなら、何もかも犠牲にして徹底的にやるというなら、分かるけれども、マザーテレサほどのことは誰もやらないんだよね。」という趣旨の意見だったかと思います。
そこで繰り広げられる議論を興味深く見ていたのですが、皆さんはこの議論についてどう思われるでしょうか。
意見の是非ではなく、そこで起こっていることが興味深いので今回のメルマガで取り上げてみました。
1.徹底的にやるなら評価できるがそうではないなら評価できない。
2.ボランティアは背伸びをせずにやることが大事。
1と2は、ボランティアという行為を肯定しないという点において共通しています。
だからこそ、思い出したのだと思います。
つまりですね、何が言いたいかと言えば、結局ボランティアは、チョットやっても、激しくやっても、
いずれにしても批判されるということです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1と2がボランティア一般についての言説と決定的に異なるのは、テーマです。
1と2はボランティア論ではなく、生き方論です。
つまり、1と2の共通点とは、ボランティアの話ではなく、生き方の話であるという点。
ボランティアの是非を問うているのではなく、生き方を問うているんですね。
ところがこの生き方というのは、何が正しいのかというのは大変難しいところ。
ボランティアを一生懸命にやらない人を人でなし扱いするのもおかしな話ですし、
その逆に
ボランティアを一生懸命にやっている人の生き方がおかしいと言うのは、やや勘ぐりすぎです。言い方を変えれば邪推です。
ただ、問題の本質は邪推かどうかということですらないとも言えます。ボランティアをたくさんやっている人を批判するのは邪推。
ボランティアをちょっとしかやっていない人を批判するのは、何でしょうか。
自分とソリがあわないという感覚です。
~有吉さんの言葉~
邪推と言えば、芸能人で、邪推をすることで、笑いをとっている有吉さん。
この有吉さんは、「本当のこと言っても、薄っぺらすぎて誰も信じないでしょ?」と言います。
言っていることが本当かどうかが問題なのではなく、言っていることが本当っぽいかどうかばかりが気にされてしまう。
そういう風潮がちょっと危険だなと、今回の問題を解きながら感じてしまいました。
ただ、このお話にはオチがあります。人は感情的になった時に極端に思考力が下がる生き物なんです。
単なる生き方論や価値観の話をしているのではなく、ソリがあうかどうかで物事を考える癖が染み付いてしまうと、あなたは小論文試験で合格しにくくなるでしょうというお話だったんですね。
受験生の方は参考にしてみてください。
【6】解答例
【問題1】
A:河川の再生
B:環境レジーム策定と合意形成
C:科学理論と信じ込む人間
D:生物の食と住
E:SF的政治論
F:ボランティアで本当に大切なこと
G:日本国の人工的海岸
H:オゾンホールと実証的研究
I:地球の鉄則
【問題2-1】
C、E、F
【問題2-2】
私がC、E、Fを選ばなかった理由は、地球と環境というテーマとの関連性の薄さが原因である。関連性の薄いテーマを選べば、読者は一貫性の無さを感じる。また、関連性が低いことを並べた場合、本としてまとまりの無さを感じる類の精神的価値観や規範を持った人間はいるものだ。慶應SFCで発刊する出版物であれば、大学からの加工物となるため、実用書のような編集はあまり望ましくはない。従って、テーマに一貫性を持たせる編集方針が妥当だと考えた。
【問題3】
この【地球と人間】を刊行するにあたり、私がみなさんに感じてほしいことは、先入観を排除して、原点に立ち返る必要性です。人は簡単に判断を誤ります。人は、自分が考える範囲でしか物事を考えることができない性質があるため、自分の考えこそが正しく、自分が絶対だと思いがちです。しかし、このような考えは、多くの人が持ちやすい考えであるために、時に危険です。自分の価値観を正しいと思い、自分の考えが正しいと思った時に何が危険でしょうか。世界に存在するあらゆる物事の多様性を自分都合で解釈する危険性があるということです。
地球の環境を論じる際も同じです。我々の地球環境が脅かされている根源的な理由は、このように自分の価値観や行動を正しく、適切なものであると考える人の行動様式に起因するのかもしれません。地球の歴史は数十億年です。この気が遠くなるような歴史の中で、人類の歴史はわずか数千年です。この数千年の間に地球環境は激変しました。人間の営みや、諸学問に原因があるのではなく、人間そのものに私は原因があると思えてなりません。
自らの力を誇示し、強いこだわりを持ち、自らの価値観を優先し、驕り高ぶったとき、人間は(人類は)己の欲求を満足させることについて、歯止めがかからなくなります。この【地球と人間】というシリーズでは、細目事項として、以下の3点を皆様にお伝えしていきます。1)環境の変化2)科学的な研究の重要性3)地球環境の重要性の3点です。
自分こそが正しいという認識を世界各国の有識者が持った時、今まで人類が環境に対して行ってきた数々の失敗が繰り返されるのではないでしょうか。したがってこのシリーズでは、事実と科学、そして、科学万能主義という悪しき思想を持たないために、情報提供を持続的に行っていくことを目的とします。
人類が環境に対して行ってきた過ちとは何でしょうか。今一度、(わかったつもり)を排して、これを考えてみたいと思います。人間の行為に原因があったのか、より一層本源的には人間そのものにあったのか。【地球と人間】というテーマの「人間」について、私は問題意識を持ち、読者の皆様の考察に役立つ情報提供を行っていきます。
【問題4】
環境崩壊の真因