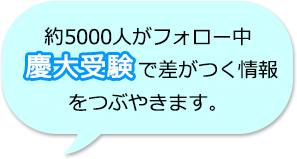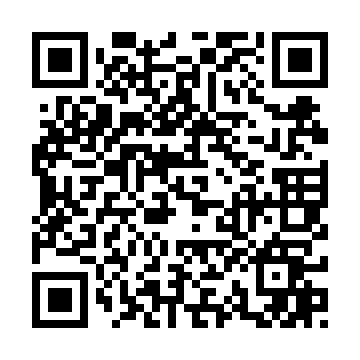このページでは、メルマガで流した慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。
慶應クラスでは、構造ノートや構造議論チャートを使ってもっと詳しく細かく各学部の過去問解説を動画で行っています。
2018年度慶應大学法学部 小論文過去問題解説
こんにちは。
2018年度の慶應大学法学部小論文過去問題解説を行います。
今年はリスク学についての課題文が出題されましたね。
課題文の要約的な内容は以下のとおりです。
スマホで、きれいな画面で見たい方はこちらをご覧ください。http://structure-notebook.com/public.php?id=11706
今年の問題は、中途半端に文章が抜粋されているので、全体像をつかみにくい文章が出題されています。
あくまでも、リスク学の話なんだと分かれば、少し課題文の内容をつかみやすくなるでしょう。
出典に注目しましょう。「リスク社会と信頼」となっていますね。
設問
次の文章は、現代社会のリスクに我々がどのように対処すべきかを記したものである。著者の議論を400字程度でまとめた上で、それに対するあなたの考えを、具体例にふれつつ論じなさい。
解説
今回の問題は、「要約せよ」ではなく、「まとめなさい」というものですね。
原則は次のように覚えておくと良いでしょう。
【原則】 ・教科書型・・・・まとめる(事実をまとめる)
つまり、歴史の教科書のように、時系列に事件が並んでいるようなものは、「まとめる」対象です。一方で、評論文のように、多くの主張が展開されているものを圧縮する時は「要約」です。
そうしますと、今回は、まとめなさいという要求ですから、事実が並んでいるのかな・・・と思うかもしれませんが、主張ばかり並んでいるのですね。なぜでしょうか。本文にあまり論理的にまとまりがないからと言えるでしょう。
今回の課題文の内容は以下のような構図になっています。
1) 3つのリスクへの対処法の提言 2) 3つ目の提言内容に関する詳細な説明
3) 結論
これはつまり・・・論理を厳しく見る練習をしている人なら一発でわかると思いますが、前半が、結論の前提になっていません。つまり、要約しようにもできない文章と言えます。従って要約はともかく、まとめなさいということになったのでしょう。
従って、今回は上記の1)~3)をまとめていくことが大切です。
【解答の指針】 理由を言語化することが大切です 。
ここについては、「理由を書くことができない人は、書かなくてもよい・・・なぜならば、このような構文を使えば、すぐに評価されるから」といった指導も近年見かけますが、非常に危険です。
当塾では、慶應法学部小論文、模試全国1位(偏差値87,9)が出ていますが、きちんと理由を言語化してこのような成績になっています。また、このような成果は、基本を大切にしているからと言えるでしょう。
あまり難しく考える必要はありません。なぜ現代社会におけるリスクは問題なのかを考えれば、よいでしょう。このように考える理由の一つは、法学部が政治や法律を学ぶ学部だからです。考察した理由と、それらのデータを論理的につなげば、主張を展開できます。
それでは、解答例を見てみましょう。
解答例
第一にリスクを取ってでも、事業を行おうとする決定者とそれにより損害を被る被影響者との間でのコミュニケーションのあり方を詳細に検討すべきである。第二に、専門知への不信や不安という問題への対処も視野に入れておかねばならない。第三に新しいリスクとのつきあい方について信頼を軸に考えていく際には、信頼についてのより詳細かつ緻密な理論を展開する必要がある。
過去問題解説者 牛山恭範
人を成長させる事が専門。決して頭がいいわけでもなく、勉強が得意ではなかったが独自の学習法を使うことで小論文試験が難関で知られる慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部にダブル合格する。
2009年、技術習得の理論・原理(成長の原理)を「目標達成論」(エール出版社)で発表。その他高速学習(どんな人でも大量の記憶を形成させる)を可能にする、プロフェッショナルとして、年間約3千のメールサポート・電話サポート・直接指導をクライアントと行い、累積数1万を超えるサポート実績がある。慶應義塾大学総合政策学部在学中にパソコンの家庭教師などを経て店舗経営で起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。技術の習得に関する周辺と、それを可能にする頭脳に関して研究を重ね現在に至る。(大学院では、思考力の研究を行い、研究は成功した。)現在は研究の成果を活かし、需要の多い分野で教育カリキュラムを構築し、技術を提供。
より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長より、BBT大学大学院にて問題解決思考の思考について師事を受ける。
ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者(写真) となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。
マッキンゼーの問題解決思考を上記大学院の学長である大前研一氏から直に師事を受け、各種技術習得、及び,問題解決型の 学習コンサルティングに活かした活動を行っている。
執筆書籍
・「小論文技術習得講義」(改訂版あり。)
・「自動記憶勉強法」(改訂版あり。)
・「なぜ人は情報を集めて失敗するのか?目標達成論」(改訂版あり。)
・「勉強法最強化PROJECT」(弁護士・医師との共著)
・「慶應大学絶対合格法」
・「慶應小論文合格BIBLE」(改訂版あり。)
・「機械的記憶法」
・「クラウド知的仕事術」
・「小論文の教科書」
・「速読暗記勉強法」
・「難関私大対策の急所」
・「AO入試対策とプレゼンテーション合格法」
マスコミ掲載事例一部
・読売新聞(全国版)学ぼうのコーナーにて8回掲載(週間企画)
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 会社紹介 平成23年10月7日
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 平成23年11月4日放送
・産経関西 20年前とは変わった受験事情 平成23年12月9日
クライアントの実績の一部
・教え子がダブルE判定から慶應大学に合格。
・教え子の成績がTOP0.1%に引き上がる。
・全国3位に急成長→慶應大学A判定に。
・北海道大学法科大学院次席合格。
・女子高生が2時間で速読を習得→名門津田塾大学に合格。
・医師の国家試験、公認会計士試験、薬剤師試験、弁理士試験など、難関国家試験にクライアントが合格。
・国立私立、資格試験、国家試験問わず、希望の試験に合格。
・全国模試で英語で二度日本一。
・慶應大学4学部(法・経・総・環)合格。
・大阪大学大学院主席合格。
・上記の他に、名門大学院、最難関大学院、京大、東京大学大学院などに合格実績がある。
外部講師活動
VIDEO
全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。
牛山執筆の慶應小論文対策本と書籍の動画解説
分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。 詳しくはこちら
「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース 詳しくはこちら
どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。) 詳しくはこちら
「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授! 詳しくはこちら
慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら
慶應対策丸わかりガイドのご案内
内容のほんの一部を挙げると・・・
・慶應大学に合格できる小論文の書き方とは?
無料メルマガのご案内
慶應大学総合政策学部の過去問題を20年以上講師自ら解いて言えることについて、音声解説した音源をメルマガ会員に無料プレゼントします。慶應模試2年連続全国1位(偏差値87.9)を輩出した牛山が解説します。
メルマガ会員のみの特典となりますので、ご希望の方は以下のメルマガ登録フォームにメールアドレスを記入下さい。
~メールマガジンについて~ プライバシーポリシー ・メルマガ解除
メルマガ以外でも、ツイッターやラインで情報提供しています!⇓⇓
ライン↓↓(スマホで閲覧)
ライン↓↓(PCで閲覧)
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。
慶應クラスの資料請求・お問い合わせ


 ・スキルアップコンサルタント
・スキルアップコンサルタント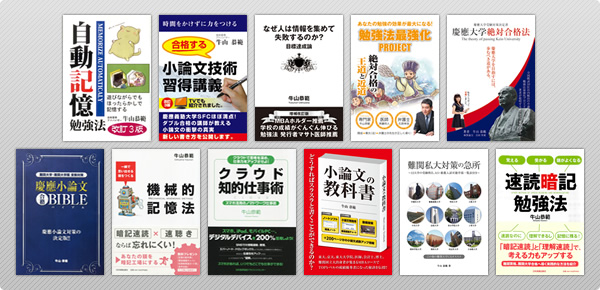
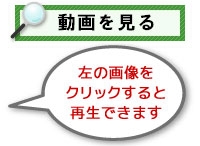
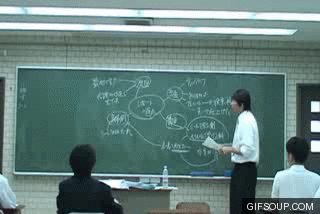


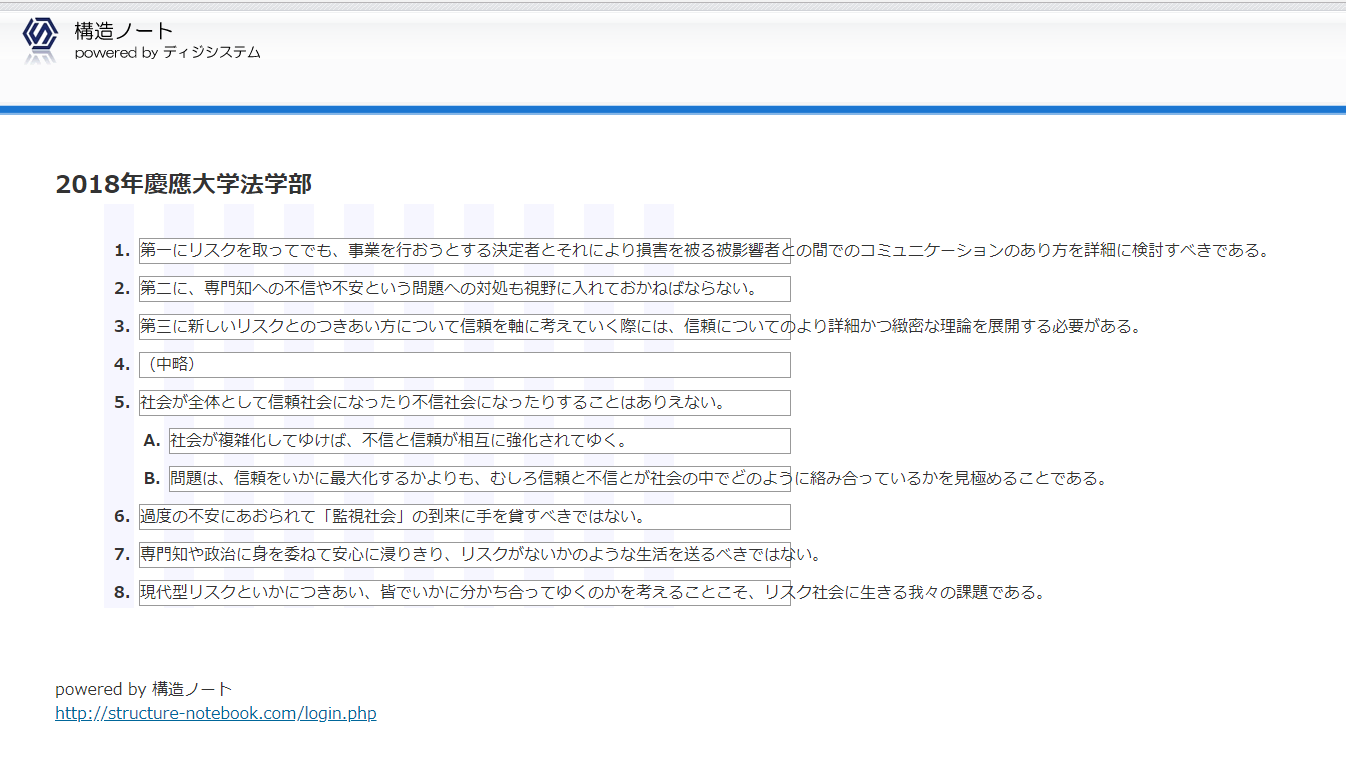

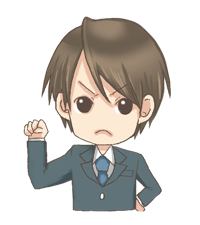
 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」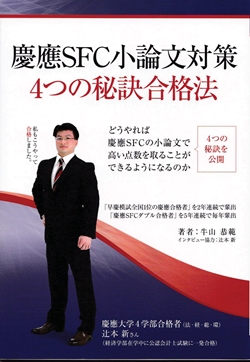 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」