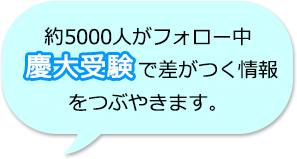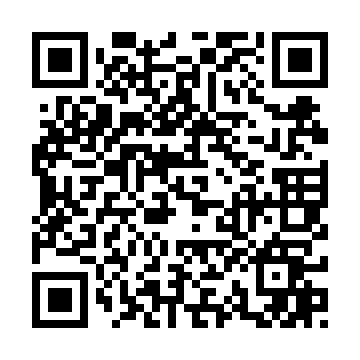~全国模試小論文1位の報告を3年連続でもらっている牛山の過去問題解説ページです。~
このページでは、慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。
2021年度 慶應大学文学部 小論文過去問題の解説
こんにちは。
本日は、2021年慶應大学文学部過去問題解説です。
今年は、吉田兼好の「徒然草」に出てくる「つれづれ」という言葉の解釈についての文章が出題されています。
今年も、要約問題が出ているわけですが、要約方法を工夫する必要がありそうな問題が出ています。
どういうことかと言いますと、
先行研究羅列パターンとも言うべき、課題文が出ているのですね。
先行研究というのは、かつて行われた、ある分野に関する研究のことと理解してよいでしょう。
例えば、今回のケースで言えば、「つれづれ」という言葉が、対象の研究がいくつか紹介されています。
このように、なんらかの研究対象に関する研究をまとめる行為を先行研究のレビューなどと言い、学問においては、非常に重要な意味を持ちます。
先行研究の整理は、学問の作法のようなものであり、同時に、基本的な態度でもあります。
つまり、大学での評価というのは、高校生までの評価とは違うと言えば、もう少しピンとくるかもしれません。
先行研究をどの角度から整理するか、どのようにレビューするか(先行研究のレビューとは、誤解を恐れずにシンプルに言えば、整理と表現可能です。)が、腕の見せ所となるわけなのですね。
それでは、この問題を解くには、何に気を付ければよいのか?
〈先行研究まとめ型課題文をまとめる際の注意点〉
こんな感じです。
繰り返しますが、大学での評価のポイントは、高校生までと大きく異なります。論文が書けると、(やるねぇ)となりますが、論文が書けないと、(ポンコツかよ)とすぐなってしまうのが、大学の怖いところです。
したがって、論文を書くための基本的な知識がある人は、(頭いいですねー)となりますが、論文を書くための基本的な知識が欠落していると、(アホで知能が低いサルですね)というくらいに、評価が激減してしまいます。(なんという恐ろしいところなのでしょうか。)
いや、でも本当にそんなところがあります。知ってるとか、知らないなんて、言ってみればどうでもいいことって感じもしますよね。だって最初はみんな知らないんだから、当たり前じゃないですか。でも、大学では、低能みたいな、非常にきつい評価になってしまうことが多いと、受験生諸君は考えておいてください。それくらいに、暗黙のルールって大事です。
ところが、論文を書く暗黙のルールって、小論文の本にまとめられていなかったのですね。そこで、私が各大学の教員はなんと述べているのか、今回の慶應文学部の課題文のように、先行研究をまとめて、整理した本「高得点小論文解法集」(エール出版社)を出版しているので、まだ読んでいない人は、ぜひ読んでおきましょう。こんなの読んでいないのに、受験なんて、恐ろしすぎると思います。
で、・・・・もう一度大事なことなので、ポイントを確認しますよ。
非常に大切なので再掲
とはいえ、
ここでは、別に高校生に、大学における学問の作法を求めているわけではないでしょう。
ですから、別にどのようにまとめてもよい・・・・
とは残念ながらなりません。
どういうことかと言いますと、大学入試では、知らず知らずのうちに、大学が求める評価軸から大学受験生が評価されていることって珍しくないのですよ。
そんなアホな・・・
なんて言っても始まりません。
研究・論文の書き方に詳しい人は、大学で評価されやすい
となります。
ただ、もちろん、あくまでも今回の入試問題は、大学受験生向けのものなので、知らないとただ損をするという、このような事情はあるにせよ、そこを踏まえて、課題文をまとめていくことが大切です。
では、どのようにまとめるかと言いますと、全体の論旨の流れを見るというやり方がよいでしょう。
つまり、今回のように、先行研究まとめ型だと、いろいろな説が入り乱れるわけですが、これらの説、持論を、グルーピングして整理することが大事だということです。
そして、この作業は、すでに、課題文の著者がやってくれています。と・・・いうことは、そこが論旨のポイントとなります。
つまり、先行研究のレビューと、その後の著者の考えの論旨をまとめてやることで、今回の課題文はきれいに整理ができるということです。
それでは、課題文の中にある様々な言説を事実だけ抜き出すとどうなるのか。以下にまとめているので、ちょっと確認してみましょう。
島津、つれづれを退屈の一言で片づけることを批判(1926)
ざっとこのようになります。
これをグルーピングすると、「つれづれ」という言葉を複雑に解釈するグループと、そうではないグループに分けることができます。
【複雑に解釈する】
【複雑には解釈しない】
と・・・・いうことは、これらをグループとしてまとめてやると、論旨が明確になりますね。
そして、先行研究をまとめた著者はどこに向かうのでしょうか?
今回の問題では、定量研究ということです。大学生に著者はアンケートを行っていますね。
大事なことは、著者の論考はこの内容を踏まえたものだということです。従ってここまでの内容を踏まえて、その上で、著者の結論を紹介するとまとめとなります。
それでは、解答例を紹介します。
はい。
設問1
320字~400字で要約しないさい
設問1解答例
島津はつれづれを退屈の一言で片づけることを批判した。(1926)また、小林は、つれづれとは、心身の環境であると主張した。(1942)類似した主張を唐木と富倉が展開している。唐木(1955)は、つれづれとは、すさび(荒び)とほぼ同義であると述べ、富倉(1956)は、つれづれこそ人生の本質的な時であると述べた。このように、つれづれに複雑な意味を持たせる論とは対照的に、安良岡(1961)や井出(1965)は退屈説への回帰を説いた。著者は大学生にアンケートを行い、その結果は退屈説が有力であった。このような学問的考察を経て、筆者は、解釈というものは、つかみどろこがないものであり、正解がある問題を考えることだけが学問かと問うている。その上で筆者は、例え得られる答えが相対的なものであったとしても、その正解を求めるという行為自体に実は大きな意味があると述べている。
要約問題は、主観的な立場でまとめるとやりやすいことが多いのですが、今回の場合、客観的な立場でまとめる方がやりやすいでしょう。先行研究のまとめ部分があるからですね。
いずれにしても、小手先のテクニックではなく、学問についての理解に基づいた本質的な対応が求められています。
そんなわけで、塾でぱぱっと学べばOK~
つまり、書き分けについても、判断基準が明確であり、そのバックグラウンドについて、十分な見識や経験があることが大事ということです。
あなたは、素人アルバイトに添削をお願いするなど、いい加減な対策に終始していませんでしたか?
ここで、ご紹介した内容は、研究や学問についての知識のほんの一部にすぎません。
それでは、設問Ⅱを見てみましょう。
設問2
正解が出ない問題に取り組むことの意義について、この文章をふまえてあなたの考えを320字以上400文字以内で述べなさい。
この問題では、意義が問われていますね。
もう一つ注意ポイントがあります。議論に参加していくこと を指します。
著者の議論に参加していくには・・・
1)賛成か反対かを述べる。
2)著者が提示した重要判断基準について言及する。
3)著者の提示した論点について自分の見解を述べる。
原則としてこのようなことだと理解しましょう。
ただし、今回の問題は、ふまえて、あなたの意見を自由に述べなさい・・・ではなく、
絶対にこの設問の要求をす無視しないようにしましょう。
解釈というものは、つかみどろこがないものであり、正解がある問題を考えることだけが学問ではない。
例え得られる答えが相対的なものであったとしても、その正解を求めるという行為自体に実は大きな意味がある
ここでは、意義について言語化していくことが大切です。
それでは、解答例を紹介します。
設問2 解答例
正解が出ない問題に取り組むことの意義とはどのようなものだろうか。正解が出ない問題に取り組む価値について、私は人の感情的な価値を挙げたい。不幸な戦争を社会から無くすことや、人の心に安らぎをもたらすことは、言うまでもなく社会的な価値である。文学作品には、このような人の心に感情的な価値をもたらす性質がある。純粋数学や物理学は、永久に不変だから、他の学問より優れているという意見を私は耳にしたことがある。しかし、本当にそうか。今私たちが生きているこの地球上の人々、後の世の人々の心に変化を起こし、二度とない人生を豊かにすることにこそ、価値があるのではないか。もしそうであれば、絶対的な解だけが価値を持つのではなく、正解を固定できない問いにも大きな価値があることになる。以上の理由より、私は正解が出ない問題に取り組む意義は、人の心に起こる感情変化による豊かさ・幸福感などの価値を人に提供することであると考える。
今回の解答例では、「どのようなものだろうか」と問いを設定しています。出題者が何を書いてほしいと考えているのか、出題意図を常に考えましょう。
今回の問題では、
「正解が出る学問」と「正解が出ない学問」の対比構造があります。
この対比構造をうまくとらえた上で、論証することができれば、点数が高くなります。
今回の解答例では、多くのテクニックを使用しているのですが、ここでは伏せておきましょう。詳しくは私が書いた本をお読みください。ここでは、みな説明しない方がよいと思います。
さて、いかがだったでしょうか。
今回は、新しい要約方法をご紹介しました。
過去問題解説者 牛山恭範
慶應大学に確実かつ短期間で合格させる慶應義塾大学合格請負人。慶應義塾大学合格の要である、小論文と英語の成績を専門家として引き上げる為、理系を除く全学部への合格支援実績がある。(学部レベルだけに留まらず、慶應大学法科大学院へ合格に導く実績もある。)短期間で人を成長させる為の知見を活かし、教え子の小論文の成績を続々と全国10以内(TOP0,1%以内も存在する)に引き上げる事に成功。12月時点で2つの模試でE判定の生徒を2ヵ月後の本試験で慶應大合格に導く実績もある。技術習得の専門家として活動する為、英語力の引き上げを得意としており、予備校を1日も利用させずにお金をかけず、短期間で英語の偏差値を70以上にして、帰国子女以上の点数を取らせるなどの実績が多い。慶應大学合格支援実績多数。自分自身も技術習得の理論を応用した独自の学習法で、数万項目の記憶を頭に作り、慶應大学SFCにダブル合格する。(その手法の一部は自動記憶勉強法として出版)同大学在学中に起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長について師事を受ける。ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。慶應合格のためのお得情報提供(出る、出た、出そう)ではなく、学力増加の原理と仕組みから根本的に対策を行う活動で奮闘中。現在、東京工業大学大学院博士後期課程在学。
執筆書籍
・「小論文技術習得講義」(改訂版あり。)
・「自動記憶勉強法」(改訂版あり。)
・「なぜ人は情報を集めて失敗するのか?目標達成論」(改訂版あり。)
・「勉強法最強化PROJECT」(弁護士・医師との共著)
・「慶應大学絶対合格法」
・「慶應小論文合格BIBLE」(改訂版あり。)
・「機械的記憶法」
・「クラウド知的仕事術」
・「小論文の教科書」
・「速読暗記勉強法」
・「難関私大対策の急所」
・「AO入試対策とプレゼンテーション合格法」
マスコミ掲載事例一部
・読売新聞(全国版)学ぼうのコーナーにて8回掲載(週間企画)
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 会社紹介 平成23年10月7日
・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 平成23年11月4日放送
・産経関西 20年前とは変わった受験事情 平成23年12月9日
『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』プレジデントFamilyClub様(メディア掲載)
クライアントの実績の一部
・三田の学部でも小論文全国1位輩出。(偏差値87.9)
・慶應4学部合格者(法・経・総・環)2年連続輩出。
・慶應SFCダブル合格者6年連続輩出。(記録更新中)
・慶應大学3学部合格者ほぼ毎年輩出。
・慶應SFC総合政策学部全国模試小論文1位輩出。
・慶應SFC環境情報学部全国模試小論文1位輩出。(偏差値85以上)
・英語全国1位(2度)輩出、現代文全国1位輩出。
・慶應大学の小論文を1万点以上添削した経験あり。
・慶應関連書籍出版数日本一。 約30冊 (自社調べ)
・慶應関連メディア掲載数日本一。(自社調べ)
外部講師活動
VIDEO
全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。
牛山執筆の慶應小論文対策本と書籍の動画解説
分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。 詳しくはこちら
「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース 詳しくはこちら
どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。) 詳しくはこちら
「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授! 詳しくはこちら
慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら
無料メルマガのご案内
慶應大学総合政策学部の過去問題を20年以上講師自ら解いて言えることについて、慶應模試2年連続全国1位(偏差値87.9)を輩出した牛山が解説します。
メルマガ特典:慶應対策丸わかりガイド
内容のほんの一部を挙げると・・・
・慶應大学に合格できる小論文の書き方とは?
メルマガ会員のみの特典となりますので、ご希望の方は以下のメルマガ登録フォームにメールアドレスを記入下さい。
~メールマガジンについて~ プライバシーポリシー ・メルマガ解除
メルマガ以外でも、ツイッターやラインで情報提供しています!⇓⇓
ライン↓↓(スマホで閲覧)
ライン↓↓(PCで閲覧)
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。
慶應クラスの資料請求・お問い合わせ

 ・慶應義塾大学合格請負人
・慶應義塾大学合格請負人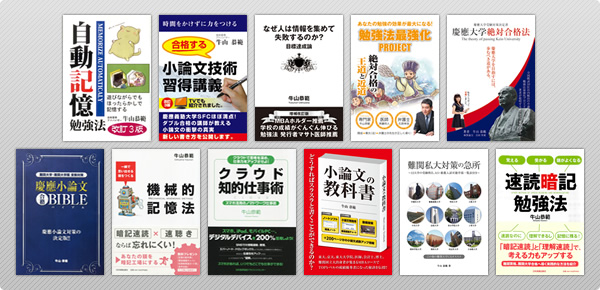
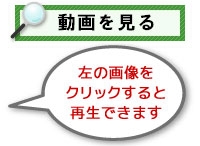
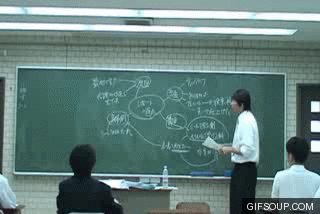





 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」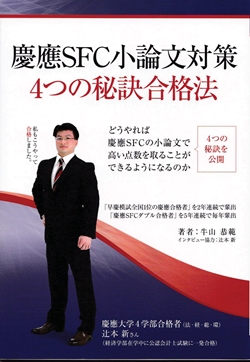 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」