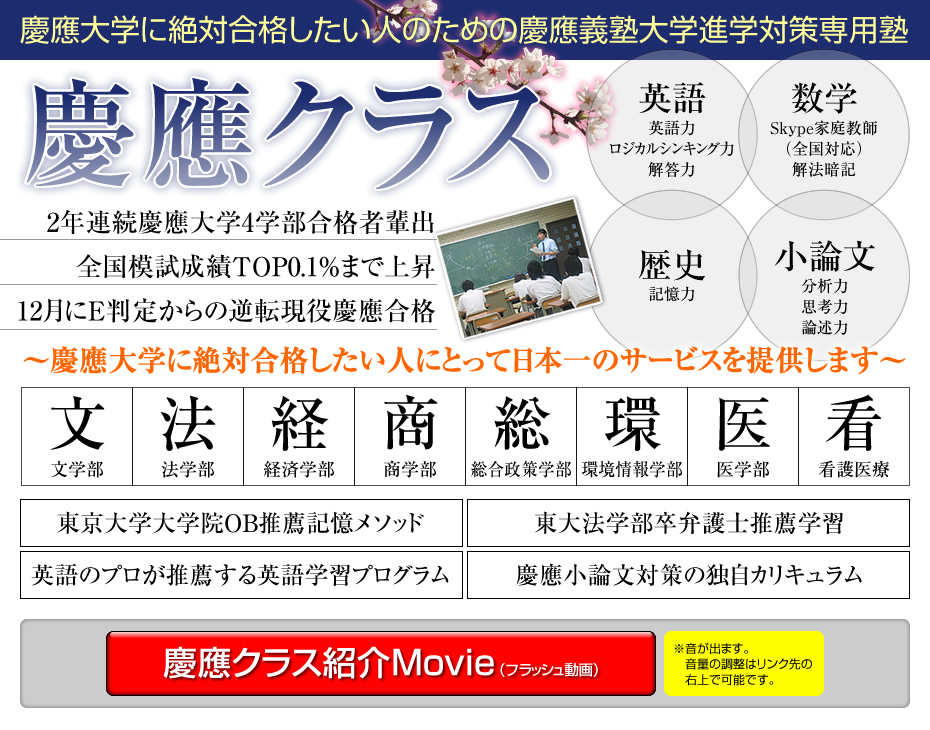メディア掲載: プレジデントFamilyClub様
《質問》 慶應大学の合格率が9割を超えるという受験機関(予備校等の類)があるのですが、本当でしょうか?
《牛山の答え》
慶應大学の合格率が9割を超えるという受験機関が
あるという事ですが、この教育業界の第1線で広告を数年間
打ち、多くの受験生をサポートした経験から言えば、
ほとんど考えられない事です。
詳しい理由は以下に述べます。
※ガチガチの固い文章ではなく、話口調で以下の文章をご案内致します。
---------------------------------------------------------------------
●慶應大学の合格率はどんな受験機関も7割を超えないであろうと考えられる理由
----------------------------------------------------------------------
慶應大学の合格率はどんな機関がいかなるサポートをしても
まず7割超えということはないでしょう。
7割はどんな機関が指導しても超えないであろうと
私が考えている主な理由は次の3点です。
1)小論文と他の科目を適切に総合的にサポートする機関がほぼ無い事
2)記念受験組みが下げる合格率
3)小論文重視の試験体制による必要時間数の増加
1)については、英語を予備校で教える事はあっても、小論文
も教える、さらに暗記のサポートもするというところは無い為
ですね。日本史の授業をする事はあっても、暗記のサポートをしている
わけではありません。基本的には10人に一人しか合格しない試験です。
ですから平均的な指導が行われれば、3科目教えても、10%に合格率は
限りなく近づきます。代ゼミと河合塾が競ったとして同じような指導が
あれば、合格率は両者とも10%に必ずなります。その理由の1つは以下にも
解説しますが、それまで勉強してきた子やしていない子が混ざる為です。
英語や日本史が伸びても小論文が伸びなければ、慶應には合格できません。
大手予備校でも、全て教えるのは稀で慶應受験生でも英語だけ教えて
もらっている人も多いのが実情です。教える側で揃っていないこともあれば
受講側がそろえていない事もあります。そうすると指導内容がいいとか悪い
以前の問題であり、他の受験生と同じように伸びない科目が多くの受験生
はあるという事になります。つまり、7割程度の数字すら超えないのです。
全科目をまんべんなくサポートしてもらっている受験生が全体の5割であれば
母集団から分子の合格者の割合が10%の試験では数学的に100%に
限りなく近い確率で、7割程度の合格率も必然的に達成できない事になります。
条件1 全受験生の5割は全科目をサポートされていない
条件2 合格率10%の試験である
上記の条件の1と2から導かれる結論は7割には合格率は達し得ないというものです。
可能性があるとすれば合格率10%の試験で、指導されていない科目
以外の科目の突出した得点で他の科目を補う場合ですが、以下の2点目と3点目の
理由から絶望的にその可能性は無くなります。
2)記念受験組みによる合格率の引き下げが二つ目の理由です。
弊社の場合もありますが、12月から、2月にかけて、お願いしますと
言ってくる学生がたくさんいます。
どんなに優れた指導やメソッドがあっても、あと3日で慶應に合格させて
くださいと言われたら、神でもないかぎり不可能です。
もちろん、ギリギリ力が及ばないとか、あと少し力が足りないという
場合は多面的な実力の内の数点を重点的に補強する事で、一気に点数が
上がり、頭ひとつ抜きん出て合格するということはあります。
2010年度合格で動画に出てくれた渡邉くんはその典型で、元々
優秀でしたが、その時期には力がついておらず、2箇所の予備校でE判定
だった状態から一気に伸びて慶應に合格しました。
記念受験ということに関して言えば、3日前も
1ヶ月前も同じですし、2ヶ月前も同じです。受験の仕事をしていない方は
イメージできないかもしれませんが、英語は苦手です、日本史もあまりやって
いません、小論文を教えてもらえば、なんとかならないでしょうか?という
質問やお願いはたくさんあります。受験生の心理からすればとにかく助けて欲しい
という事ですから、仕方がありません。しかし、センターが終ったけどダメそうな
ので、慶應を受けますと言われても、ほとんどの人が落ちる試験でカンタンなレベル
のセンター試験でダメなら慶応の本番の試験でも点数は取れるはずはありません
ので、当然ですが誰が教えても、そこから逆転はほとんど無理です。
メソッドの問題ではないのです。物理的にその年は間に合わないのです。
そういう記念の受験組みが多いのも慶應大学の特徴です。そうすると・・・
当然ですが、合格率は下がります。記念受験組みが、50人も慶應受験生を集めて
全体の30パーセントを占めないなどと言う事はほとんどありません。
10人中1人しか合格しない試験です。ラッキーはほとんどありません。
ラッキーはボーダーすれすれの最も多くの受験生がひしめき合っている中の一人が
とります。これはラッキーとは呼べません。司法試験でも2点の中に1000人の
受験生がいるなどと言われますが、こういう僅差の戦いになっている中ではラッキーはなく
当然力不足は落ち、中途半端な場合も落ち、実力があっても落ち、かなり実力があって
合格できて、場合によってはかなり実力があっても試験は水物ですので落ちる試験
が慶應受験です。
3)小論文重視の試験体制による必要時間数の増加・・・が3つ目の理由です。
慶應大学が他の大学に比べて大きく異なるのは、小論文を重視した受験体制で
あることです。このことの意味は何か?というと、合格という事にテーマを絞ると
大きなアドバンテージがある人間とそうではない人間の内、アドバンテージが
ある人間を合格させますという意味合いの試験体制に近いという事です。
慶應合格対策戦略DVDの中では詳しく解説していますが、各科目を効率よく
こなした場合の必要期間は、0から積み上げた場合で以下のようになります。
英語 6~9ヶ月
日本史 3~4ヶ月
小論文 ?~5年
英語や日本史は努力してどうにもならないかというとそんな事はまずありえません。
覚えているかどうかだけです。覚えていれば正解です。覚えていなければ×です。
ところが小論文はそうではありません。分析、思考、論述の3段階の力を見ます。
上記の科目の内、小論文の期間の意味が分からないという方も多いかもしれません。
なぜ最長で5年となっているのか?という部分についてカンタンにご説明します。
私自身も自分が小論文を教える側になるまで全く気づかなかった事ですが、10代から
上は50代の上場企業会社役員や医師の方の文章を添削して、初めて気づいた事が
あります。
小論文という科目は、極めてセンスの要素が大きい科目だという事です。
これを私は地力と呼んでいます。
50代であれば、10代の子よりも、点数が高い文章を書けるというわけではなく
それまで積み上げてきた経験や、文章スキルの総合的な力によって点数は決まるので、
運動競技のように、砲丸投げに向いていない人や、バレエやダンスに向いていない人が
いるように、育った環境によって積み上げているセンスがまったく違うのです。
ある人が優れていて劣っているというわけでもありません。
これは本来であれば、十人十色と言って、様々に評価される文章の能力が、
小論文という大学の意向でどうにでもなる科目によってある側面から評価されて
しまい、それに向いている場合は最初から大きなアドバンテージがあるけれども
向いていない場合は極めて不利だということなのです。
ちょうどイメージ的に表現すれば、芸能人のオーディションやバックダンサー募集の
オーディション会場に集められた、何千人というイメージです。
この中から、数人選ぶ場合、努力で切り抜ける事もできますが、人の長年の努力を
あざ笑うかのように、天性の才能と素質でオーディションを通過してしまうような人が
いるという事です。
中にはダイナミックな踊りを、大きな体格でする人もいるかもしれませんが、
評価基準が変われば点数は低くなります。
8割得点できるようになるまでの必要時間という観点から各科目を見た場合、
小論文という科目は一年でどうにかなる科目ではない為、1年間でほぼ合格させる
という事はその分難しくなります。
小論文の標準編、上級編、5回添削セット、各分野の解法DVD、慶應対策小論文と
徹底して小論文の授業を行い、予備校の授業より良かったと答えた回答率は100%
である当社でも、このアドバンテージを100%ひっくり返して結果を出すという
断言はできません。なぜなのかは、上記のダンスのオーディションをイメージして
もらえばお分かりいただけるかと思います。理屈で説明するよりもずっとその方が
理解しやすいかと思います。
以上、慶應大学合格率は、どのような機関がサポートを行っても
7割を超えないであろうと考えられる3点の理由をお話しました。
再度確認致します。
1)小論文と他の科目を適切に総合的にサポートする機関がほぼ無い事
2)記念受験組みが下げる合格率
3)小論文重視の試験体制による必要時間数の増加
の3点です。
これは私の数年間の経験に基づく見解ですが、
他にもこんな理由があるのではないか?という考察がありましたら、
以下のメールアドレスまでぜひご連絡ください。
digisistem.skilladviser @gmail.com
《追記》
慶應義塾大学が他の大学と大きく違う点で学生の質を担保しているとすれば
それは小論文試験です。小論文は書くだけ・・・というのは倍率と人気が
低い場合の話であり、人気と倍率が日本で最も高い場合はそうはいきません。
小論文試験は知性や知識の成熟度を総合的に見るには最適な科目です。
覚える量が増えることと、判断の質は必ずしも正比例しない為に、
純粋な思考能力や分析能力を試す事ができるのが小論文試験の特徴です。
もしも覚える量が増えれば必ず人の判断の質が上がるのであれば、日本史の
配点比率を極限まで高めれば全てはパーフェクトに問題を解決できて
必要な人材が集まるでしょう。しかし覚える事と判断の質はいつも正比例
するわけではありません。その証拠に、経験と知識が豊富な会社に何も知らない
新入社員が入社した際によく起こるイノベーションが挙げられます。
物の見方や判断の加え方、その基準となっている、目には見えず、ペーパー
テストのマークテストや知識問題では点数化して測定できない総合的な
頭脳活動を見るには文章を書かせるかモノを言わせるしかないとも言えるでしょう。
前者が小論文試験であり、後者がディベートの試験です。
今年ビジネス専用の大学として世界的に有名な大前氏が開校したBBT大学
ではこの小論文とディベートで評価基準を設けて学生を選定しています。
このような数値化しにくい頭脳活動は、短期間の訓練や特別な指導で
高める事もできますが、高める事が可能なのは多面的に存在するいくつかの
点についての能力だけです。それまで培ったセンスや地力は養成するのに時間が
かかる為に、一日中本を読んで5ヶ月1年と経過しても、ほとんど何も変わらない
可能性があります。覚えている状態と覚えていない状態という部分以外の
頭脳活動領域である為です。このあたりの事情に一番詳しいのは恐らく
出版社の編集部の方ではないかと思います。名前の知れた有名な著者の
何十歳も下の年齢のライターが、著者の手助けをしている・・・という事も
多いのではないでしょうか。若くとも文才のあるプロというわけですね。
文章のプロは思考のプロではないかもしれませんが、文才は文章の多面的な才能の
内の一側面であることには違いありません。
------------------------------------------
●ウソの合格数と合格率の特徴
------------------------------------------
世の中にはウソの合格数(率)の発表が溢れています。
自己防衛の情報が欲しい方の
為に『3つのウソの特徴』をここに掲載しておきます。
参考にしてみてください。
1)倍率の逆転現象
2)証拠の非掲載
3)真実性を出す為の1ケタの合格率
この3点が全部含まれる場合もあれば、この内一つだけが
当てはまるという事もあります。
1)倍率の逆転現象
についてまずお話します。
私は若者からの、『あの合格率は本当なのでしょうか?』
という悲痛なメッセージをもらい、独自に調べてみました。
ウソの合格率や合格数を掲載する(と推測される)機関の特徴として、
まず感じるのは本来数学的にあるべき自然な倍率の逆転現象です。
東京大学と、慶應大学では、倍率は慶應大学の方が高くなります。
私は東大がカンタンだといっているわけではありません。
学力という側面から見た場合、東大の方が母集団のレベルは高いと
思います。勉強なれ、勉強好き、天才の3種類の人間が最も集まる
大学でしょう。
倍率が低いのは、母集団のレベルが高い為です。
当然ですが合格がカンタンというわけではありません。
これが現実だと思いますが、この現実に反した合格率を掲載するのが
ウソの実績を掲載する業者の特徴です。
(東大は慶應よりも難しいので、合格率を低くしよう)
という安易な考えがそこには働いています。
(そもそも評価基準が違う試験ですので、砲丸投げでインターハイに
出るのと、短距離競争でインターハイに出るのとどちらが
難しいかという問いと同義なのですが・・・)
その結果慶應合格率は70~90%と発表し、東大合格率は60~80%
と発表するのが相場の様です。
このように本来慶應合格率10%、東大合格率33%という母集団に
対する自然な倍率が逆転します。
これは極めて不自然な数字です。
●慶應受験者の合格率も30パーセント平均で引き上げました。
●東大受験者の合格率も平均30%引き上げました
という場合は、それぞれが慶應40%、東大60%ということになるでしょう。
つまり合格率の逆転現象は起きません。
母集団が10人くらいしかいない場合は、運の要素などでクルクルと倍率が
変わる事はあっても、それぞれ1万人から受験する人気校の合格率が、逆転して
しまっているというのは、どういうわけなのでしょうか。
慶應合格率なら高くしても怪しまれないという心理から適当につけた数字としか
私には思えません。しかし現実には慶應の方が倍率が高いが故に、それだけ
極端に合格率が上がっている事は不自然です。
さらに不自然だと感じるのは、小論文試験というアドバンテージ
が大きく影響する試験であるが故に東大よりも合格率の引き上げが難しくて当然
であるというのが、何年も多くの生徒に小論文を直接指導してきた私の見解だから
です。センター試験で数学や古文の点数を85%超えさせるのにかかる必要時間と
小論文の力が無いところから慶應に安全に合格できるまで高める時間とどちらが
長いかと言えば、人によっては圧倒的に小論文の方が長いのです。科目数だけで
判断する人がいますが、元々短距離競争に向いていない体格の選手をインターハイに
出場させるようなもので、小論文という科目の
特性上、母集団の数が増えた際に合格率が平均的に逆転するということは
まず無いと言って良いでしょう。覚えれば力が上がる科目ではありません。
つまり平均的に指導する子達の力を必ず引き上げる事ができる科目ではない
にも関らず、東大と慶應の合格率を
逆転させているという部分が、不可解極まりなく、真実性が薄いと
考えざるを得ません。
(イメージで表現すれば、あなたはボクシングのコーチだとして、子供の頃から
トレーニングを積んだ体の出来たセンスのいいエリート5人を指導してプロにする
のと、いじめられていたので助けて欲しいというどう見ても闘志が沸いている
タイプではない子もプロにするのとどちらが難しいか簡単かということです。
恐らくカンタンなのは前者でしょう。素人が指導してもうまくいく可能性があります。)
これは私の数年間の経験に基づく見解ですが、他の視点もあるかもしれません。
補足説明になる理由がある場合は下記までご連絡ください。
digisistem.skilladviser @gmail.com
2)証拠の非掲載
これは普通ではありえない合格率や合格数を発表しているところの特徴です。
合格数は、大手予備校などの場合は本当であってもその営業力からは
おかしくはありません。中小零細企業が極端に多い数字を出していたら
それはほぼウソでしょう。母数が確保できないからです。
通常は最も多い合格者を出した機関は最も不合格者も多く出しているはずで
す。そうではない場合はよほど突出した指導が行われていることになります。
ただし、その仮説も、上記の【慶應合格率は7割を超えない】見解を示した
文章の内容から、現実にはありえないと考えざるをえません。
3)真実性を出す為の1ケタの合格率
これは3つ目の怪しい業者の特徴です。
代ゼミや河合塾、Z会や、進研ゼミが、全国規模の広告や
TVCMによって全国数千万世帯に広告を打ち、その結果として
東大受験生の1万人の内、8千人にアプローチした・・・という
事の結果として、合格者が数百人いるとか千人いるという事は
自然な現象です。
その結果として、1ケタまで合格率が出る事はあっても
基本的には、慶應受験組み100人の受験生を世話できるほどの広告を零細企業は
打てません。100人に告知する事はできても入会者はせいぜい数人です。
弊社の場合も慶應の受験者ということになると、そんなに多くはない
のが現状で、ほとんどの人は、普通の大学や高校を受験します。
その結果合格率は一桁まで出せません。
もちろん13人受験して9人合格したので、合格率が0.69で
69%の合格実績です!
と言う事は可能ですが、その数字の真実性は極めて低く、少なくとも
説得力を持つ統計資料としてセールス文句にするのであれば、100人は
調査しろと誰でも思うでしょう。
最初から統計などとっていないのではないかと思わざるをえません。
これと同じように、速読の
習得率も90パーセントを超えるという事はまずないと考えています。
何をもって習得したとするかは、その人の判断によりますが、
私は地方の田舎でセミナーをしたことがありますがほとんど農業を
しているような方も中にはいます。活字を読むのも
久しぶり、本を読まない、強烈に数十年で凝り固まった読み方が定着している、
普通の会話のやり取りも、少し苦労を伴うという方も、当然います。
こういう方が速読の読み方を試す時、目を細めて、なれない手つきでページを
めくる・・・・田舎のおっかさんのような方ですが、
すぐに若い子のように要領よく・・・・とは行き難いものです。
ではなぜセミナーにこういう方が来ているのかというと、お子さんの為
です。親心なんです。速読のセミナーにそういう方が来ることも私はよく
経験から知っています。
世界屈指の速読マスターという人がいたとしても、このおっかさん相手に
最先端の学習理論を伝授するというのはまず無理、時間をかけてゆっくり
手ほどきをしていく必要があるのです。
私はこういう現状を生々しく知っています。
だからいい加減な習得率や合格率がすぐに作られた数字であると分かります。
真実性を出す為の不自然な数字は、以下の2点の場合に真実性が低くなります。
1)零細企業である場合・・・まず1桁まで出すだけの受験生を世話できないので
極めてウソの可能性が高い
2)異常に高い率の結果である場合・・・速読の受講を最後まで席を立たずに
終了しましたという事をもって、速読習得としているわけではないのであれば、
速読をマスターしたという事のはずです。これも経験上、真実性が低くなる
ポイントと言わざるを得ません。
これは私の数年間の経験に基づく見解ですが、あなただけが気づいたもっと別の
理由もあるかと思います。
そういう理由があるという場合は下記までぜひご連絡ください。
digisistem.skilladviser @gmail.com
上記のご説明以外にも、合格率と合格数を詳しく考察する上で参考になる
記事をご紹介しておきますので、興味がある場合は参考にしてみてください。
http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/tensaku-mail-sample.html
《追記》
予備校の場合は合格率などが完全に把握しやすいのですが、弊社の様に通信制で
サービス提供を行っている会社は、合格数を把握できません。
そもそも合格したかどうかを報告するのは本人の意思の問題であり
義務でもなんでもありません。
したがって合格はしたけれども報告はしないという人も当然います。
教えてくださいとお願いをしても、断る方も中にはいます。
もしあなたの立場で考えていただければすぐに分かることですが
、あなたがどこかの試験に合格して、自分の名前や顔写真を出す
為に連絡をするでしょうか?
恐らくはしないはずです。
これはつまり、通信制のサービスを提供している会社は合格率が下がる
事を意味します。
弊社の場合も、密度の濃いサポートを行ったり、普通ではまず合格できない
場合に合格してしまったなど、本人の感動が大きい場合にお礼の
電話連絡などが入ったり、どうぞ使ってくださいと好意で
書面が送られてきているケースがありますが、全員から連絡をいただける
わけではありません。