 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら



75-1 不都合な真実
論文の評価は、多くのケースで先入観や感情で決まります。この点については、一般的には、大いに異論があるでしょう。
そうです。つまり、一般的には(そんなわけない)です。しかし、不都合な真実は違います。
論文の評価には、原則論と例外論が存在します。この違いをうまく理解できていなければ、一定のレベルまでは評価されてもそれ以上は評価されないでしょう。
75-2 一般的な評価軸
論文の評価は、一般的に、構成、内容、表現、発想などで評価されます。また、これらに加えて、理解などという評価軸があってもいいでしょう。
ここまでの話は、文科省の指導要領の会議で議題に上がっても全く問題がないようなお話です。
しかし、そんな一般論だけを理解しても、結局のところ(だから何なんなん?)という話になってしまいます。So what? なんですね。

75-3 論理的かどうかは、(教員は認めなくても)教員が決めている
論理というのは、学問の分野における作法やら、考え方の違いがあるにせよ、一般的には、究極的には解釈論です。
誰かが「これは論理的ではない」という場合、その論理がいわゆる「疑似科学」である場合や、多分に直観的であることもあるでしょう。しかし、問題はそういうことではありません。同じような内容について、「これは論理的ではない」と評価する人もいれば、「これは非常に論理的だ」と評価する人も現実にいるということです。
例えば、Harvardの博士号を取得している人物と、MITの博士号を取得している人物が、同様の内容を見て、「これは論理的ではない」と一方が言い放ち、一方は、「これは大変論理的だ」ということがある・・・ということです。
そんなアホな!
とあなたは思うかもしれません。なぜならば、論理的かどうかということは、一般的に学問の世界の共通認識であり、論理が無ければ、学問も科学も存在しないと言っていいからです。
75-4 数学の論理と言葉の論理
問題をクリアにしましょう。一般的に数学の論理は、限定された考察対象について、論理を組んでいくので、明快性があります。一方で、言葉の論理は、言葉が持つ範囲が広いので、どんなに学問の作法にのっとろうが、おのずと限界があります。
加えて、考察対象の各種前提を否定することも可能です。
例えば、私が知っているある京都大学の博士号を取得している教員は、社会科学全般が、ほとんどナンセンスだと言い切ります。物理学と経済学の博士を両方持っている見識の広い教員なのですが、その理由は、社会科学で扱う内容は、選択した内容について数学的に計算を行うからなのだとか。つまり、その選択の段階で、対象を十分に考察できていない、恣意的な部分があり、ここに社会科学の脆弱性があると述べます。
これが、言ってみれば、論理の解釈性です。
つまり、上記の京都大学の博士号保持者が述べることが妥当なのであれば、社会科学全般の知識・学識は非論理的ということになるでしょう。このような物言いは、京都大学らしいと言えば、京都大学らしいのかもしれません。一方で、これは有名な学術誌に掲載されているのだから、十分に論理的であると解釈する人もいるでしょう。
結局のところ、信頼性の問題なのです。
誰を感情的に信頼できるかという問題とも言えます。
私はここでFACTを提示しました。つまり、論文の論理性は解釈論だという解釈を述べているのではなく、現実に京都大学の博士号を保持している大学教員であっても、査読付きと言われる有名なジャーナルに掲載された論文を非論理的と言ってしまうという現実があり得るということです。
ただ、だからといって、その教員が他の大学教授の書いた論文を、非論理的で意味が無いとは言わないでしょう。しかし、生徒には言うことがあります。しかし、言わないこともあります。感情的になれば批判しますし、感情的にならなければ批判はしないでしょう。
75-5 分かりやすいかどうかは、説明レベルでは決まらない
ここまでのお話は、やや長かったのですが、単なる前提です。問題はここからです。ではどうすればいいのかという話です。
一般的に小論文の解法テクニックのようなものは、わかりやすいのでこの書き方が良いとか、なんとなく、慶應に受かった俺が考えたので、これがいいとか、東大に受かった僕のやり方とか、物事の両面を見ることができるので、このやり方が良いとか、いろいろな理屈があるものです。
しかし、不適当に書かれた論文というのは、結論から言えばこうです。
・全く分かりやすくない。
・物事の両面を見ていても、非論理的である。(評価したくならない)
これが不都合な真実と言えます。
しかしながら、論文の書き方テクニックには諸説あるので、こんな風に説明すればめちゃくちゃわかりやすいでしょ?だから点数が高くなるんですよ・・・などというものもあるようですね。
74-6 論文が分かりやすいかどうかは、仮説検証型の思考プロセスの程度が高いか低いか
屁理屈不要。論より証拠です。
私は国立大学博士後期課程の論文テストでも、約9割程度の点数を取得したことがあります。論文は一般的に満点は取れないので、9割程度ということは、ほぼ満点に近いと考えてもいいでしょう。
私が受験した時の制限時間は2時間。指定文字数は約6000文字と考えてよい試験です。これについて、私は完答しました。
慶應大学で最も小論文の配点が高い、SFC2学部にダブル一発合格もしていますし、大学院で精緻に論理を扱うマッキンゼー流の思考方式を学ぶ論文テストで、東大卒、東大大学院卒、東大博士号取得者、京大卒の中で成績優秀者にもなりました。
この経験から言えることは、分かりやすいかどうかは、説明しているかどうかではありません。読み手が予想している内容を書いても分かりにくい論文はたくさんあります。
例えば、原因を書いて対策案を書くという論文は分かりにくい論文の代表格です。何を言っているのか分からないからです。なぜ対策案を突然述べ始めるのかもわからなければ、原因がこれだと述べているのも根拠がないので分かりません。(それが原因だとなぜ言い切れるでしょうか。)また、原因は通常複数あるのだから、これらの原因の中のひとつがこれだと述べることの意味も分かりません。極めてナンセンスな話だからです。また、原因が仮説ですから、その自分の仮説を土台として、だから対策案はこうなんだと言われても、自分がこう思っているので、こうするのがいいと思うという論理になり、何を言っているのか分かりません。そうではなく、根拠を示せというのが論文のルールです。根拠を仮に書いていても、結局全体の論文構成が、原因を書いて対策案を書くという構成になっているのであれば、それは根拠ではありません。大前提が非論理的なら結局のところ、非論理的ということになります。根拠よりも論拠の方が、論文では強いのです。このように、論文というのは、自分の主張である仮説に対する論拠と根拠がきれいに整理されていなければ、全く説得力を持たないばかりか、論文の趣旨に反するので、なんのことなのかさっぱりわからないということになります。分かりやすいと思っているのは、そう教えられた人だけで、論文の作法をよく分かっているアカデミックポストの人物から見ると、(よくわからないなぁ)ということになってしまいます。
ここまでにお話ししたことは、「説明の分かりやすさ」よりも「論理の分かりやすさ」の方が、一般的に論文では大切だということです。だからこそ、私牛山が教える小論文では、2年連続で偏差値85を超えるような指導効果が出ています。説明の分かりやすさには限界があるということです。具体例を述べれば分かりやすいのではありません。あるべきところにあるべき説明があるのが分かりやすいのです。そのための大前提は、論理に対する考え方でなければなりません。自分が思っていることを説明されても、(なんの話なん?)と、なってしまうということです。なぜならば、学者やアカデミックポストの人物は、論文を論文として読んでいるからです。そこに論理があることを前提に読みます。仮に、論じなさいという要求でなくても、説明しなさいという要求であったとしても、やはり「小論文試験」である場合、論理的な物言いが求められます。

74-7 わかりやすいかどうかすら関係なくなるとは?
時には、非常に分かりやすい内容でも低評価になることがあります。なぜでしょうか。感情と、先入観です。
先入観とは、物事はこうあるべきという自分の考えとも言えます。物事はこうあるべき、解答はこうあるべき、論文の書き方はこうあるべき・・・という考えがどのような人でも一定程度あります。だから評価できるのです。評価とはこのように、重要判断基準からの見え方です。絶対的なものではありません。
言い換えれば、大学入試の小論文添削とは、この相対的な評価の重要判断基準と、その前提立った物事の見え方、考え方にあなたの答案を近づけていく作業とも言えます。
また、感情的になった人には、何を言っても、何を書いてもダメです。従って、論文テストで評価を得たいなら、読み手が感情的にならないような答案を心がける必要があります。
なぜならば「〇〇であるべき」という考え方は、感情と結びついており、学生があらがうことはそもそも不可能だからです。
74-8 読み手が感情的になる答案とは
ほとんどの学生は、採点者を感情的にさせようとは考えていないでしょう。
しかし、多くのケースで、生徒は採点者を感情的にさせてしまっています。分かりにくい答案を書く、たいそうな物言いで書く、姑息なテクニックですり抜けようとする、など、人を感情的にさせるポイントはたくさんあります。
内容がいいかどうか以前に、点数を取りやすい答案になっているかどうかに気を付ける必要があります。
言い換えれば、だからこそ、変則テクニックのような書き方ばかりではなく、スタンダードな書き方の方がより一層評価されるというわけです。
「僕が考えた必殺の小論文の書き方」のようなものが、昨今ネット上で散見されます。しかし、何百年と続いてきた学術の作法を何十年間と頭に刷り込んだ学者の思考回路からすると、完全に意味不明なトンチンカンな内容に見えてしまうというリスクがあることを肝に銘じる必要があります。
74-9 一般的な優れた学者ほど、物の見方がクリア
一般的に、学者の思考回路は、学者ではない人からは、理解ができないことが少なくありません。
例えば、学者の先生は、異常に先行研究にこだわります。常人にはおよそ理解できないレベルで先行研究を重視するのが普通です。論文の中に少しでも新しい概念が出てくると、
この概念はどこからきたんだ、先行研究はなんだ!誰が言ったんだ?どこで調べられたんだ!なんの根拠があるんだ!何もないなら論理の飛躍じゃないか、不確かなことを言うな!意味がわからんじゃないか、そんなものは学問じゃないんだ!!
という具合に、完全に価値0というレベルまで評価が下がってしまいます。しかし、一般書を読んでみたり、マンガを読んでみたりといった具合に過ごしてきたフレッシュな大学生は、このような反応に困惑します。(えっなんのこと)(どういうこと?)という具合に思ってしまうということです。これは誰が正しいかという問題ではありません。これから大学を受験しようとするあなたからすれば、「大学の先生はそういうもの」という問題なのです。しかし、切迫した問題は、その大学の先生が評価者であるということでしょう。
どういうことが起こっているのかと言えば、物事の認識方法、認識様式から、価値判断までが一貫して学者の先生ほど、学術の作法ややり方に沿ったという意味でクリアだということです。まず、そういうやり方、考え方がアカデミックな世界にはあると考えることが、実は大切です。
もちろん・・・そういう考えを試験から排除していこうとする動きもあるかもしれません。なぜならば、学生には関係が無いことと言えばそうですし、もしかすると、そういう考え方で試験を設計すると優秀な学生が取れなくなってしまうかもしれません。ただ、このあたりは、期待してみても仕方がない話です。そう理解しておくことも試験対策としては大切でしょう。
75-10 読み手の器も試される
試験というのは、究極的には知性と知性の対話です。出題者側が求める知性に対して、学生が知性で応じるというのが理想的な在り方です。もちろん、単なる知識確認テストや、理解確認テストのようなものもあるでしょう。しかし、それでは優秀な学生は取れません。
優れた知性が発揮されたとき、その知性に応じるだけの器が評価者に必要です。このあたりは非常に深い話なので、ウェブbookではお話ししないことにしておきましょう。
75-11 まとめ
論文の評価は感情で決まります。感情は多くのケースで、分かりやすさで決まります。分かりやすいかどうかは、一般的には学術の作法に応じているかであり、説明したかどうか、具体例を述べたかどうかではありません。従って論文の設計思想が大切です。論理的かどうかは、学術の作法に準ずるところもあるので、このあたりの理解を深めることが大切です。「僕が考えた必殺の書き方」のようなものは、一般的に通用しません。センスが良かった人が、うまく試験をすり抜けた後に、勘違いをしてしまっているケースが少なくありません。必殺の書き方が良かったのではなく、単に自分のセンスや適性が良かったから受かったというケースが少なくありません。学者は論文を厳格に見ます。その思考様式は極めて(誤解を恐れずに便宜的に説明すれば)一様的であり、物事の見方はすこぶるクリアです。そこに沿った思考様式を身に着け、作法を身に着けていくことが論文で評価される秘訣です。
 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら
 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース
詳しくはこちら
 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)
詳しくはこちら
 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!
詳しくはこちら
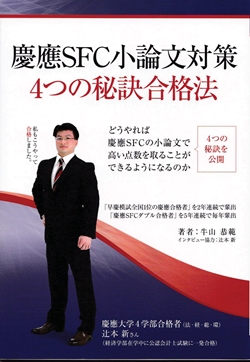 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら
小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム
慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス
※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。


ツイッター↓↓
| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓
|
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。