 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら


67-1思考が制限されてむしろ能力が低下する
私が生徒を指導する時に、一つ大切にしていることは、「伸ばす」ということです。
若い学生は教え方を誤ると、確実に能力の成長がストップします。学生の能力を育まない方法は簡単です。
方法を教えれば、学生の成長はストップします。
「◯◯法」などというものを教えるとか、「◯◯方式」などというものを教えるとか、そういうことをやると、生徒は成長がストップするということです。その理由は簡単で、自分の頭で物事を考えなくなるからです。
「この方法を使用すれば、才能不要ですよ。」
と言われれば、うれしいでしょう。
(そうなんだ。これで私も慶應に合格するんだ・・・)
などと思えてしまうかもしれません。しかし、本当にそうか?と考えることが大切です。
能力やセンス不要などと言えば耳触りは良いでしょう。しかし現実はどうかと言えば、人は、感性を働かせる方が圧倒的に頭が良くなります。
当塾では、2年連続で小論文日本一が出ており、今年は別の形で日本一になる子も現れました。また、このような実績が出る前から英語などでも日本一が出ているので、ほとんど毎年のように小さな塾から日本一が出ているということになると思います。
また、小論文については、今年も全国3位、4位、9位になる生徒が出ており、上位5%
以内、全国10位以内になる子は、ほとんど毎年のように出ています。なぜこんなことができるのかと言えば理由はたくさんありますが、簡単に言えば、「才能を伸ばす」ことをやっているからということになると思います。
そして、その才能を伸ばすためにやってはならないことが、正解を教えるということです。才能不要と言ってしまっているということは、才能を伸ばさないと言っているのと同じです。現実には、「才能不要の方法」は、思考力を制限するので、点数は高くなりにくいのです。
この原理原則は、あらゆる科目に共通します。英語も然り、現代文も然り、読解も然り、選択肢選択も然り、小論文は特にそうだと言えるでしょう。
67-2本でかじった内容を教えられる悲劇
そもそも、なぜ「◯◯法」であるとか「◯◯方式」というものが生まれるかと言えば、本でかじった内容が教えられているからです。
教育というのは、「再現の美学」です。講師ができないことを講師は教えることが本当はできません。しかし、たったひとつ、講師ができないことを教える方法があります。
「知識を理論で教える」というやり方です。
講師に何の知識も無くても、実はあまり問題ではありません。多くの教育機関では、知識が無いことはダメな証のように思われていることがありますが、跳び箱を飛べない体育教師が跳び箱を教えることができないのと同じで、本当は「できる」ということが一番重要です。
ところが、教育というのは、何かをべらべらしゃべっても教育になるので自分ができないことについて、本で調べて、「こうなっています。」と時間いっぱい話すとそれが教育ということになります。
大学で教えてもらっているならそれでもいいでしょう。大学はそういうところでもあります。つまり、学問を教えてもらうところなので、学問のスキルがある人が講師になれば良いからです。
ところが、大学受験などの世界では、結果を出してナンボです。つまり、生徒の成績が上がらないなら、話を聞いただけ無駄な時間なのです。「時間の無駄遣い」というギャグがお笑い芸人のギャグでありますが、あんな風に笑っていられません。
大学受験で不合格になれば、あなたは一生そのことについて、後悔するかもしれません。
体育教師が、「本にこう書いてあるから、みんな並んでこの通りに飛べ」と言えば、驚くでしょう。

「先生、なんで飛んでくれないんですか?」と質問するのが当たり前です。
ところが、小論文については、そうでもないようで、「本にこう書いてあるんだぞ、ハーバードの先生がこんなこと言っているぞ」と言えば、それがありがたいと感じてしまう人がいるようです。
ここで問題があります。多くの人は知らないのですが、ハーバードの教授は実際にはそん
なことは言っていなかったということがあるようです。
つまり、論文の書き方として指導しているものではないのに、ハーバードの教員がこう論文を書けば良いと言っているとか、これが世界標準のスタンダードな論文の書き方なのだと、そこまで情報がネジ曲がって、伝えられていることがあるようです。
ハーバードの教員が、このように論文を書きなさいと言っているわけではなく、例えば、問題解決の方法として、こういうアプローチや流れがあるね・・・という程度の内容が世界標準だと教えられていることがあるということです。こんな悲劇があるでしょうか。私はそれを見た時に驚きました。そもそも大学教員が書いた本に書かれている内容というのは、特定の学問における、一解釈の紹介です。
ハーバードの教員が書いたので、この考え方がこの領域におけるスタンダードになりました・・・などという性格のものではありません。そんなことがまかり通るなら、学問は世界に必要なくなってしまうでしょう。
本でかじった内容を教えられる悲劇はこのようにして、かなり深刻な問題と共に、起こっているようです。問題解決ができるなら、本にこう書いてありますと言うのではなく、実際に
やってみせればよいでしょう。
私が学んだ大学院では、実際にお手本を師範である大前研一学長が毎回見せてくれました。それは見事なものでした。ハーバードレベルではありません。大前研一氏は、ハーバード大学院を出て、博士を持っているような人材を選んでマッキンゼーに入社させ、彼らを指導していた人物です。マッキンゼーはかなり狭き門なので、ハーバードを出ているから入れるという会社ではありません。そして、大前氏は、ハーバードの双璧と言われるStanford大学で、教鞭をとっていました。
そして、
「フレームワークを使えばいいというわけじゃないからな。」と教えていたそうです。
今回私がお伝えしていることと全く同じです。方法に頼ると思考が制限されるという
ことです。大前研一氏は、ケースメソッドと言われるMBAで一般的に行われている授業について、何十年も昔の企業のケースでは、「なんちゃって教育」になるところがあると考えたのか・・・現代の問題を扱うぞ!と、一般的な大学では考えられないレベルで実戦的な学びを重視していました。リアルタイムオンラインケーススタディーという、今現実に起きている問題について、情報を集め、問題解決を論理的に行っていくという講義スタイルを彼は大切にしていました。
徹頭徹尾、自分の頭で考えるのです。これは、彼が真剣に学生を伸ばそうと考えているからこそ生まれたあり方でしょう。教育の正解はこれなんで・・・・みたいなことを彼が述べたことは、一度もありませんでした。それどころか、「私が言っていることをそのまま述べるな!」と言って、叱ることすらありました。
今でも覚えていますが、税制改革の案を学生に提出させた際に、大前氏が提唱する税制改革案におもねったような、こびた答案を作る学生を叱り飛ばし、その上で、「やり直し!!」ということなり、ただでさえ、死ぬほど忙しい毎週の論文課題が、2本だてになったことがありました。(全員です。)私はこういう教育を受けたので、本で聞きかじった内容を学生に教えていません。
自分でモノにした内容を学生に噛み砕いて教えています。したがって、私が教える時は、本の内容をほとんど書き写すような授業は一本たりともありません。すべて私が連続的に一気に3分程度で書き上げた内容を、教えています。
つまり、授業内容をデザインしているということです。
左に本やスマホを置いて、右にレジュメ作成のテキスト画面を開いて、パソコンでポチポチタイプしてレジュメを作るようなことはしていません。

短編授業も同じです。
5分程度で解説する短編授業もあわせると、授業は数百本ありますが、一気に書き上げた内容をそのまま収録しています。本を参照しなければならないような知識は、「自分でわかっていない知識」「自分でモノにできていない知識」「自分で覚えていない知識」でしょう。
そのようなことを教えてもらう学生は悲劇としか言いようがありません。先生ができないことを学生ができるようになる道理は無いでしょう。
67-3指導者が解答をイメージできないから能力が頭打ちになる
私の過去問題解説は、平均5分程度です。過去問題については、ダラダラ2時間もやりません。これは言ってみれば当然のことで、解答を再現しているので、どこがポイントかが分かるからです。
教えるということは、再現の美学と言ったのは、自分がやった軌跡を教えることで、再現性がある(生徒がそれをできるようになる)ということです。再現性が無いことを教えてもらうと、生徒もできるようになりません。知識が増えるだけです。「◯◯方式についての知識は、他の人の10倍ありますので、慶應に合格させてください」と言っても、問題解決ができる人が欲しいだけなんで・・・ということで不合格になってしまいます。最初からできるようにならなければならないということです。
67-4「私の力を疑うのですか?」とキレた話
私はある保護者の方からこんな話を聞いたことがあります。プロ家庭教師ということで、頼んだ東大卒の家庭教師が、キレたという話です。
東大卒の家庭教師が「英作文は、こんな風にやるんだよ」と教えた際に、生徒さんが、「ちょっとよくわからないので、先生書いてくれませんか」と頼むと「私の力を疑うのですか?」とキレられたという話なんですね。

東大卒だと万能の知性を持っていると思っている人も多いのですが、現実には、熟練した人の方が、優れた力を持っていることは少なくありません。本来であれば、キレる必要などなく、わざわざ家庭教師としてその家にまで上がり込んで、マンツーマン指導をしているのですから、スラスラ書いて、「例えばこんな感じですよ」とやればいいでしょう。10秒でできることです。あるいは、口頭で表現すれば、3秒で終わることです。その方が指導行為としては自然ですし、代金を頂戴して、その生徒が依頼している内容について、指導拒否にも似た恫喝を行うというのは、不自然としか言いようがありません。
なぜキレるのかと言えば、恐らくは解答を再現できないからでしょう。英語については、自然な表現や適切な表現という観点から言えば、未熟な人が書く英語にはかなりの問題があります。見る人が見れば一発で分かります。
※当たり前のことですが、東大出身者でも英語が相当できる人は星の数ほどいます。今回の事例は、若い東大生の中でも特定の事例です。一般化しているわけではありません。
そんなわけで、当塾では、海外で国際結婚をしており、翻訳業務に長年従事し、英検1級、TOEICほぼ満点の講師に英作文指導をお願いしています。彼女は(当たり前ですが)模範解答を自分で作成できます。
当塾の場合、こうやって、立論が気になる人は、私が立論をチェックし、英語表現が気になる人は、海外在住の英語講師がチェックすることで、高品質な指導を保つように、慶應合格支援のサポートを行っています。プロ家庭教師ということでも、模範解答が作れないのであれば、結局「立論」と「英語表現」の両方共が、中途半端になってしまうでしょう。頭の中で、理想的なイメージを作ることができない場合、人は教えることができません。
従って、「理想的なイメージ」ができない場合、今回のようにキレて、ごまかされたり、あるいは、「(本に書いてある)方法」が教えられます。ですから、「方法」を教えてもらって喜んでいる場合ではありません。
今回のケースでも、「簡単な英語で表現する方法で受かるんだよ」と教えられた生徒が質問をして、キレられています。小論文の場合、「この方法で受かるんだよ。」ということになるのでしょう。
しかし、講師が解答例を作成しているわけでもないので、本当にその方法で解答例レベルの表現を生徒や講師が再現できるのかどうかは分かりません。
もともと、文章を表現するというのは、一種の表現行為ですから、知識や知性が丸裸にされるものです。
講師が自分で解答例を作成せずに、業者に丸投げして、お金を払い文章を書いてもらい、その内容を「模範解答」として、公表し、本に掲載し、「この方法で慶應小論文が書けるようになって受かる!」などと指導されることもあるようです。
「方法」を教えてもらって喜ぶ人は多いのですが、現実には、「方法」と「感覚」を両方用いて、答案を設計していく方がはるかに高いパフォーマンスを発揮できます。
67-5方法頼みの指導は危険
ここまでで、3つの話をしました。
「跳び箱を飛べない体育教師の話」
「英作文を書くことを求められてキレ
たプロ家庭教師の話」
「模範解答を外部発注し、本に書いて
ある方法を教える小論文塾の話」
すべてに共通するのは、自分ができないことを教えるには、「方法頼み」になるということです。
「この方法で大丈夫だからな!」
と言われても、
「先生やってみてください」
と言うと
「このパターンなんだから大丈夫なんだよ。このパターンになっているんだから。」
と答えが返ってきます。
ところが、そのパターンとか、この種類に分けることができるというのは、後付の解釈論です。
経営学でもそのようなことが書かれている査読付き(審査が通ったもの)論文があるのですが、多くの意思決定研究や戦略論研究は解釈の後付であり、過去志向性のものだという説があるのですね。つまり、実践家ではなく、説明家的なものであり、現実には使えないということです。それでも、小論文を書いて、特定の方法で書くとスラスラ書けますよね。それはそうです。頭を使わなくていい方法で書いたからです。そして、その論文は非常に評価されにくいものです。それでも、それで大丈夫と言われたのですよね。だから方法を教える人と、評価者がセットになっているのは、恐いのです。
後付の解釈論が恐いのは、再現できない点です。
発想方法はこうやれば、万全です!と言う人が、解答例を作っていないのもよく理解ができません。
私は、発明家であり、国内で3つの特許を保有しています。だからその方法とアプローチを教えています。そして、毎年のように生徒が全国10位以内に入っています。
発明は分解するとこうなっています。だからこういうやり方がいいですよとは、私は言っていません。発明についての後付の解釈論では、再現性が無いからです。そこから発明は生まれないのです。
でも方法というのは分かりやすいです
よね。
逆に言えば、だから恐いと言えます。本当は何も分かっていないのに、分かったつもりになってしまうのが「方法」のこわいところです。
本来実践知である方法の場合、(つまり、実践家が「できるやり方」として、教えた方法)」教えた直後に生徒ができない場合でも、その方向性自体に効力があるので、グイグイやっていけば、ある段階から急速に生徒が伸びるということがあります。
一方で、
本でかじった後付の知識の場合、いくらその方法を極めたところで、再現ができません。これは当たり前の話でそもそも、上手な人はそんな方法で考えていないのです。頭の働かせ方が不適当ということになります。
別の言い方をすれば、
感覚的に状況に応じた最適化ができなければ、常に思考力や能力が制限されてしまい、臨機応変に対応できないということになるでしょう。
67-6やらないから感覚が分からない
ここまでにお話したことは、ある意味で、指導者が実際に小論文の問題を解いていないからこそ生まれている悲劇とも表現ができます。教えている側が、実際に問題を解かない場合、問題を表面的に捉えてしまうということが少なくありません。
2016年もそうでした。
他の塾が、指標問題が出ているので、指標問題が大切と言っているのに対して、私は研究計画書を書きましょうと言ったのです。そして、2017年に研究計画書を書くような問題が出ています。
このように勘が働くのは、実際に問題を私が解いて解答例を作り、その上で塾で問題を作り、学生の実力養成や、実力チェックをしているからです。そして、私が添削しています。
1)問題を作る
2)解答例も自分で作る
3)添削も自分でやる
このように、すべてワンストップでサービス提供するから、勘が働くようになります。
その結果、どういう人の成績が上がりどういう人が不合格になり、どういう人が合格したのかも、長年見続けています。
そして、さらに勘が働くようになります。そうやって、他の人に見えないものが
徐々に見えるようになっていくということです。
出題予測についても、自分で問題を解いていない人は、表面的に出題内容を捉えていることが少なくないようです。
それでも、毎年、後付の解釈論で、これが出たからこの方法でやればよいあれが出たからこの方法でやればよいと受験生は教えられることが続くでしょう。
才能不要の方法論というのは、このように、すべて「後付の説明的」であり、「こうなっていました」だから「こうやっていくといいと思います。」というものです。
このような表面的な方法は、才能不要の方法とは言えず、正確には、「才能が不要だと、私は考えました」的な方法と言えます。
本やスマホで調べて、左を見て、右を見て、方法を開発したというようなメソッドでは、本当の意味での才能不要なメソッドは打ち立てられないでしょう。

今年も、全国10位以内が何人も当塾からは出ていますが、才能不要の方法を気にしたことは一度もありません。
才能がある人はより一層天才級に、才能がその分野についてはあるとは言えない人でも、才能を開花させ、その上で、才能的な分野の頭脳活動に頼り切らない方法論で、全体の力を底上げしていくアプローチ・・・・このような、言ってみれば当たり前のことを、やりあげていく体制が、当塾の体制です。
このアプローチは、時間が立てば、花がどんどん開いていくように、次第にあちこちで花が咲くように、才能が開花されていきます。
もし仮に、私が才能だよりの指導をしているなら、「基本重視」を掲げないでしょう。才能がある若者にも、苦手な若者にも、等しく基本を重視することを私は求めます。要はセンスだなどとは言いません。センスや感性も大事であり、論理も大事です。一般的な本を参考にして論理指導をしている塾の何倍も論理を細かく指導し、センスは最先端の手法で開花させます。
才能不要論は、学生の能力を低下させます。
 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら
 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース
詳しくはこちら
 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)
詳しくはこちら
 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!
詳しくはこちら
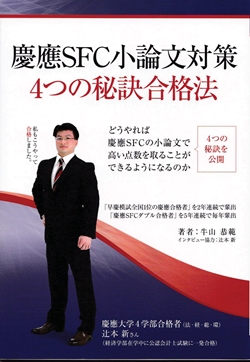 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら


小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム
慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス
※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。
ツイッター↓↓
| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓
|
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。