 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら


64-1 満足する指導は、生徒をダメにする
生徒が満足する指導を重視した場合、会社は大変儲かるようになるでしょう。しかし、その分合格率は減るでしょう。
ただ、ガサーと広告宣伝して、安売りをすれば、塾の生徒がたくさん増えて、ドカドカと不合格になりつつも、安いと塾の生徒が増え、生徒が増えると合格率が低くても合格し、結果としてたくさん不合格になっても合格者は出てくるでしょう。
そうすると、大変儲かる会社になるでしょう。
でもね・・・
という話で、そんなことを私はやりたくありません。
最後に損をするのは生徒だからです。どんな業界でもそれなりに頑張って教育指導をしている人というのは、いかにして指導品質を保つかということを真剣に考えているものです。
生徒が「お客」になってしまったら、◯◯様みたいな呼び方になってしまい、厳しいことも言えなくなってしまいます。生徒はほめれば喜びます。退会率もただただ、ほめていれば減ります。
また、本当のことを指導しなければ、退会率は減り、教育系の企業は利益体質になっていくでしょう。例えば小論文指導でも、頭を使わなくてもいい指導をすれば、生徒はすぐに喜びます。
(あっこれだったらスラスラ書ける♪)

そうです。何も考えていなければスラスラ思ったことを書けます。
なぜ沖縄県の人は、平均寿命が高いのか。
それは、魚を食べているからである。
それは、湿気が多いからである。
それは、海に近いからである
それは、踊るからである。
それは、時間にルーズでストレスが
たまらないからである。
それは、なんくるないさーの方言がいいからなのである
それは・・・
もう言いませんが、そんなことをあてずっぽうで言いまくっても論文にはなりません。
こういうことは、何も考えなくても書くことができます。だからスラスラ書けます。
「自分がどう思っているのかを書けばいいんだよ。」
と指導すれば、生徒はにっこりして(それだったら簡単!♪)と喜ぶでしょう。
もし、私が小学生を教えているのであれば、同じような指導をするかもしれません。
ただし、「原因を書け」とは指導しません。
もし私が小学生の作文指導をするなら一番心に残ったことや、人に伝えたいことを書いてごらんと指導するでしょう。
ただ、それは論文指導ではなくて、作文指導です。これから大学を受験しようという高校生や、浪人生、大学院を受験しようとしている学生に対して、原因を何でもいいから思ったこと書いてごらん
とか
分析して原因を書いてごらん
などとは言いません。
手元にデータもないのに、分析もヘチマもないからです。
・楽だけど成果がでない嘘のようなことを教える
・生徒がダメなのに、ただほめるだけ
・厳しい指摘をしない
こういうのは、塾が儲かるかもしれませんが、不合格一直線指導です。
だからやらないのです。もちろん、ほめることがダメと言っているわけではありません。よくできているところはほめることもよくあります。ただ、一つだけ言えることは、テクニックでほめてはダメだということです。
本当にダメなら、私は何もほめません。
それは、生徒に対しても失礼だからです。嘘でも褒めればいいなんて考えていれば、嘘がばれるでしょう。真剣に学ぶなら、真剣にやる必要があるでしょう。
本気で慶應に合格したい人しか、教えるつもりはありません。
64-2 実は不満足になる指導は大変効果的であることがある
一般的に、生徒は何が成果につながるのかを知りません
また、
自分の実力が高まっていることについても、分かっていないことが多いです。
また、
合格後もそれが分からない人もいます。
さらに、
(こんなの何の意味があるの?冗談やめてよ)
というような指導が恐ろしく効果的であったりします。
一方で、練習っぽい練習が何の意味もないとか、練習っぽいだけで、成果はあまり出ないなどという指導は大変多いのです。なぜそうなるのかと言えば、「っぽい」ことが成果につながるわけではないからです。私が中学の時、私が通った中学校は大変無意味に見える練習をさせることで有名でした。しかし、成果は断トツで、インターハイ常連校でした。結局それっぽいことに意味がないのです。
練習っぽい練習というのは、
ダッシュを50本やれ!
とか
筋トレやれ
というものです。
こういうことをやっていると、いかにもやっている感が出るでしょう。しかし、そういうことをやれば勝てるのかと言えば、話は別です。成果につながることしか意味がないのです。
ところが、一般的に受験生は、それっぽいことが効果的と思い込んでいるところがあるので、それっぽいことをやりたがってしまいます。しかし、ここまでにお話したとおり、それっぽいことをやれば練習成果が出るわけではありません。

そもそも、練習せずに成果が出るならその方がいいこともあるでしょう。
しかし、練習だけすれば成果が出るに決っているという「練習至上主義」の人にはそれが分かりません。ビデオ学習をする方が、走り幅跳びの飛距離が伸びることもあります。
それでも練習至上主義の人は、走り幅跳びの練習ばかりをするでしょう。
自分のフォームがダメダメで全く飛べないフォームであったとしても、とにかく人よりもたくさん練習していれば、それだけで、確実に他の人よりもたくさん飛べるようになると強く思い込んでいるのです。
こういう人は、ダメなフォームを練習により、より一層固定化させて、絶望的に飛距離が伸びなくなってしまいます。場合によっては、このような強い思い込みを取ることが、最高の対策になることがあります。ところが、こういうことをやると不満が出てきます。
▼もっと練習しないとインターハイに出られないよ
▼もっと実戦的にやることが成果につながるはずだ
こういう風に考える人は反発します。例えば、私が小論文の授業で、うぬぼれを無くし、心のあり方を学ぶ授業をやったとしましょう。そうすると、強く反発する人が出てきます。
(こんなことやって何の意味があるんだ!意味ないよ、過去問やりたいよ)
こういう風に思う人がいます。
しかし、こういう人の答案はこうです。
--------ありがちな答案------------
◯◯すればいいのである
◯◯が原因である。
私は対策案が3つある。
◯◯すれば問題は解決する。
◯◯であろう。
そして◯◯であろう。
◯◯は、◯◯が分かっていないのである。
◯◯の考えは浅はかと言えよう。
私が提案する方法で全部解決するのである。
----------------------------------
少し強調して書きましたが、こういう答案を書けば、大体不合格になります。これは論文ではないからです。しかし、書いた本人は、自信まんまんです。こういう人に「心の授業をやります。」などと言えば、大きく反発し、そんなのやっても意味ない!と不満になるでしょう。
そもそも、心とかそういうフレーズはバカが言うことだという強い思い込みがあるからです。精神論に意味はないし、効果的かつ合理的なトレーニングメニューが最高だと思いこんでいることが少なくありません。
ところが、社会科学の分野で分かっていることは、うぬぼれは大きく人の推論能力を引き下げるということなのです。
つまり、
自分の考えていることは正しいに決っていると考えている人は、どんどん考えられなくなっていくということです。
少なくとも、科学的に考えるのであれば、心の状態は非常に重要と言えます。
一つずつ複雑にからみあった糸を解きほぐすように、学んでいけば、大きく飛躍することができるということは珍しくありません。
・ところが、理解するのも大変
・自分の心と向き合うのは苦しい
これが人間というものです。
・理解も苦しい
・自分と向き合うのも苦しい
・自分を変えるのはもっと苦しい
だから、
・もっと楽をしたい
・もっと考えたくない
・理解もしたくない
・自分なんて変えたくない
という具合いに、人はなりがちです。
つまりこういうことです。
| 楽さについて |
満足しやすい指導: 楽ができる 不満足になりやすい指導: やや苦しい(が効果的) |
|---|---|
| 理解について |
満足しやすい指導: 理解しなくていい 不満足になりやすい指導: 自分と向き合う |
| 自己変革について |
満足しやすい指導: 自分を変えなくていい 不満足になりやすい指導: 自分を変える |
| 成果について |
満足しやすい指導: 出にくい 不満足になりやすい指導: 出やすい |
現実はどうかと言えば、小論文に関しては、不満足になりやすいことをやる方が断トツに伸びます。
私が教えて日本一の生徒が出ているのは、私が学生を甘やかさないからです。
よくみんながんばっていると思います。
【本当のことを指導するAパターン】
本当のことを指導すれば、生徒は不満になりやすいのです。しかし、成績は上がり、合格しやすくなります。ただ塾の退会者は増えるでしょう。
【嘘を教えるBパターン】
嘘を教えれば、生徒は簡単に満足するでしょう。しかし成績は落ちて不合格になりやすくなります。ただ、塾の生徒は増えるでしょう。そして、安売り経営をしていれば、さらに増えやすいでしょう。そして、ドサドサ不合格になっても、学生のポテンシャルでな
んとか合格するという現象が起きるでしょう。
64-3 どちらの指導をやりたいか
【本当のことを指導するAパターン】
【嘘を教えるBパターン】
この二つを比較した場合、AよりもBの方が収益はいいでしょう。
私がどちらの指導をやりたいかと自分に問うた時、Aパターンでした。
だからこの現象と法則性に気づいた時(そうだ!塾の生徒を減らそう!)と思いました。
そして、スタッフにこの現象があることを伝えた上で、
【本当のことを指導するAパターン】
【嘘を教えるBパターン】
どちらの経営をやりたいかと質問すると、スタッフは
【本当のことを指導するAパターン】
と即答しました。
よい社員に恵まれてよかったなと思います。
64-4目先の喜びと合格のどちらを取るか
親御さんと話をしていると、特に男性の親御さんに多いのですが、
(娘のテンションが上っていません。)
と心配になる人がいます。
テンションを上げるのは簡単です。
今伸びていない所についても、ほめちぎっていればいいからです。
・よく書けているねぇ
・すごいねぇ
・これでいいですよ
・論理的です。
実際そうではないのに、こんなことを言っていれば、とことんダメになります。
そもそも学ぶということは、ディズニーランドやUSJに行くことではありません。
受験本番まで目をキラキラさせて、余裕で受かると思っていた人が、不合格通知を受け取って、膝から崩れ落ち、他の人が進学するのに自分だけが遅れてしまい、一年間の努力がすべて結果につながらないということを知り、死ぬほどつらい思いをする時、
そのことと、今のテンションと、どちらが大切なのかを考える必要があります。
もちろん、
私は「褒める教育」を否定しているわけではありません。ほめるかほめないかの二元論ではありません。
問題は、学ぶことに対する理想が高すぎる場合、損をするのは本人であるということです。
このことを念頭に置き、学ぶということが本来どういうことであり、どういうものであるべきかについて、親子で十分に教育が行われるのは理想的と言えます。
ただ、それは難しいことが多いでしょう。
もちろん、家庭内での教育ができないからこそ、塾に任せるというご家庭もあるでしょう。それはそれでもいいのです。
しかし、最低限のコミットメント、(決断と考えてもらっても構いません)もない状態で学ぶと、塾でも救うことが難しくなります。
また、
いや、そんなことはできると謳う業者は常に現れるでしょう。なぜならば、ここまでに述べたように、利益主義的な教育事業者は存在するためです。
64-5 そうだ!塾の生徒を減らそう
そこで、私はスタッフと話し合った結果塾の生徒を減らすことにしました。
つまり、すべての教え子が常に得する方を選択するということです。本当の
ことを指導すれば、不満は増えますがその分彼らが合格しやすくなります。
私は合格しやすくなることに価値を置いて、指導品質を高め、学習成果を高めることにフォーカスすると決めました。
不満がある方が伸びて、
不満が無い方が伸びない
こういうことはよくあります。
あなたがどこで何を学んでもこのことを覚えておきましょう。きっと学びが加速するでしょう。
 「小論文技術習得講義」
「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。
詳しくはこちら
 「慶應小論文合格バイブル」
「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース
詳しくはこちら
 「牛山慶應小論文7ステップ対策」
「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)
詳しくはこちら
 「小論文の教科書」
「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!
詳しくはこちら
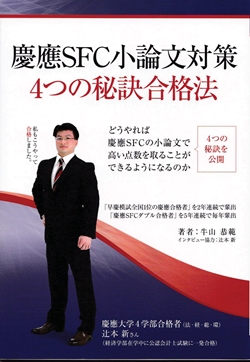 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」
「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。
詳しくはこちら


小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム
慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス
※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。
ツイッター↓↓
| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓
|
メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。