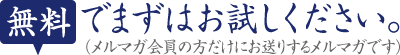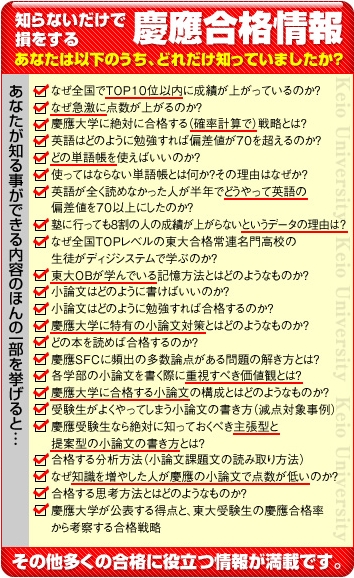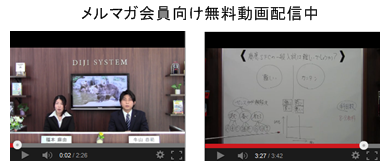このページでは、メルマガで流した慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。
慶應クラスでは、構造ノートや構造議論チャートを使ってもっと詳しく細かく各学部の過去問解説を動画で行っています。
慶應大学文学部 2018年 推薦入試 小論文 過去問題解説(2017年度実施)
こんにちは。
牛山です。
本日は、慶應大学文学部 推薦入試2018年(2017年実施)の問題解説です。
【1】総合考査Ⅰ
この年は、「ひとりの哲学」という書籍の課題文が出題されています。
【問題1】
傍線部に「ひとり」を孤独だとか、孤独の親戚であるかのように扱う言動とありますが、著者はそのことをどのように考えていますか。親鸞と福沢諭吉の例を挙げながら説明しなさい。
【解説】
こんな問題が出ていますね。
この問題はどのように解けばよいでしょうか。
課題文の中で、3つのポイントを把握すれば、この問題は解答できます。
- 1)著者が重視する「ひとり」についての考え方。
- 2)親鸞が説く「ひとり」についてのモデル。
- 3)福沢諭吉が説く「ひとり」についてのモデル。
設問では、「そのこと」が何かを把握する必要があります。
ここでは、『ひとりを孤独だとか、孤独の親戚であるかのように扱う言動』とあり、この部分が、『そのこと』にあたるわけですから、
『ひとりを孤独だとか、孤独の親戚であるかのように扱う言動』について、著者はどのように考えているのかを述べる必要があります。
そうしますと、著者はこのような考え方を否定的に見ており、自立という言葉を重視していることが課題文から読み取れます。
そこで、上記のポイントを再現するように、これらの内容を解答に盛り込みます。

- 1)著者が重視する「ひとり」についての考え方。
- 2)親鸞が説く「ひとり」についてのモデル。
- 3)福沢諭吉が説く「ひとり」についてのモデル。
以下が解答例です。
問題1 解答例
著者はひとりという概念について以下の二つのモデルを紹介している。親鸞は自分ひとりが万人の中から浮かび上がる非対称的な様子について、「ひとり」という言葉を用いた。この意味で、親鸞のモデルにおける「ひとり」は万人との対比である。福沢諭吉は、学問を志すものは、何よりも気力を確かにもって「一身」の独立をはかれ、と述べている。この意味での「一身」すなわち「ひとり」は、「国家」との対比である。このような考え方を示した上で、著者はひとりという概念について、自立という考え方を重視している。
【問題2】
傍線部にヤスパースの語る「真の人間」の可能性こそが、この日本列島に存在する「ひとり」の問題を考える時の有力なてがかりになるだろうとありますが、それはなぜですか。著者の主張に基づいて説明しなさい。
こんな内容が問われていますね。
ここでは、なぜかということが問われていますね。
なぜかと問われた時にどのように説明するのが良いのか、少し卑近な例で考えてみましょう。
A君のことをB子さんが好きだと思う。
こんな命題で考えてみましょう。
A君のことをなぜB子さんが好きなのか、説明しなさい。
こんな風に変換すると、同じことですよね。
例えばこんな風に説明しましょうか。

A君は、パンクロックが大好きな人間だ。
そして、B子さんは、パンクロックが大好きだ。
B子さんは、パンクロックを一緒に楽しむ人を探している。
従って、B子さんは、A君のことを好きになると思う。
こんな風に説明することができます。
これは、何をやっているのでしょうか。
つまり、以下のようになっています。
前提1:A君は、パンクロックが大好きな人間だ。
前提2:そして、B子さんは、パンクロックが大好きだ。
前提3:B子さんは、パンクロックを一緒に楽しむ人を探している。
結論:従って、B子さんは、A君のことを好きになると思う。
ということは、今回の問題も同じように、論理関係を再現するように、前提を列挙していけばよいということになります。

以下は重要な前提+結論という流れになっています。見てみましょう。
問題2 解答例
ヤスパースは、紀元前五百年前後に注目せよと述べた。なぜならば、この時代に人類の精神変革があったためである。その上でヤスパースは、孔子などの偉人を「真の人間」と述べた。真の人間とは、人類の精神変革に貢献したという意味である。同様に、我が国に目を向ければ、十三世紀の思想家が同様の役割を果たしていると著者は説いている。親鸞を筆頭に、我が国における精神変革に大きな影響を与えた五人には圧倒的な存在感があると筆者は主張する。その中の親鸞は「ひとり」の精神について、自説を展開している。そのため、筆者は「ひとり」の問題を考える際に「真の人間の可能性」について考えることが「ひとり」の問題を考える手掛かりになると考えている。
総合考査Ⅱ
【問題】
大衆迎合主義や人気取り政治が、なぜデモクラシーにとって問題となるのかを事例などを挙げつつ述べなさい。
概ね上記のようなことが問われる問題が出ました。
法学部のようですね。
今回の問題では、同じように「なぜ」と問われていても、前提や一般原則ではなく、因子を述べてもOKです。
事例を挙げるわけですから、考えられる因子を述べていく形になります。
今回のように、原因を問われている場合、考えられる原因を書きましょう。問われてもいないのに原因を書く必要はありません。
構文で小論文を書くことを誰かに教えてもらった人はここで大きく損をしていることがあります。
詳しくはこちらのページに書いているので読んでみましょう。
多くの受験生の最大の不合格要因:本質的な問題点
今回の問題では、近年問題視されているトランプ大統領の事例や、ヒトラーなどの分かりやすい事例を挙げるのは一つの方法です。
特にトランプ大統領は、アメリカ最優先(第一主義)を説いており、この意味では、大衆迎合主義的と考えることもできるでしょう。
今回の答案も、ここでご説明した前提を列挙する書き方で対応可能です。

それでは、解答例を見てみましょう。
解答例
ポピュリズムはなぜデモクラシーにとって問題となるのだろうか。
一般的に国民は常に政治に関心を持ち、十分な知力と知識を獲得しようと努力しているわけではない。また多くの国民は、自分たちの権利を拡大することや自由の拡大に関心がある。一方で国家の戦略とは中長期的な視点と高度な判断力を必要とするものである。判断力や熱意、正義への関心が不足する国民が、リベラリズム的な判断により為政者を選ぶことで、ヒトラーによる非人道的な政治や、「批判が集まっているトランプ大統領」による非倫理的政策が実行されやすくなることがある。国民が望んでいることと、国民のために必要な改革は常に符号するわけではない。国民の満足する政策は必ずしも国民の満足する結果につながらない。
従って、ポピュリズムがデモクラシーにとって問題となる最大の理由は、ポピュリズムが衆愚政治につながりやすい性質を有している点にあると私は考える。
このように、論理とは、常にピラミッドストラクチャーのような形ではなく、A→B→C→Dという論理関係を明示することでもあります。
AならばB、BならばC、CならばDという関係が分かることで、読み手が内容を深く理解することも論理的です。

なかなか論理的に書くことは難しいことですが、少しずつチャレンジして上手にできるようになっていきましょう。