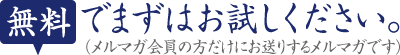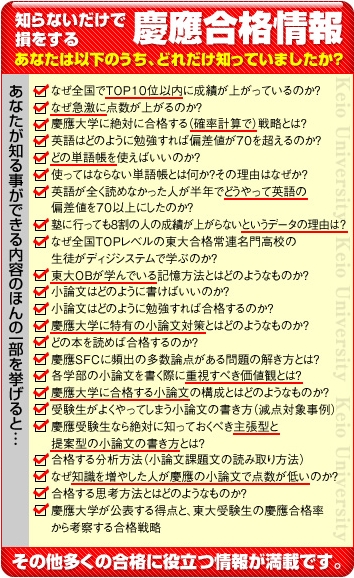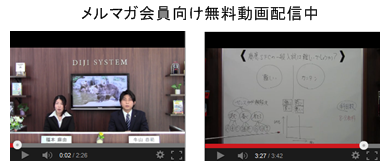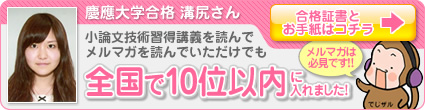このページでは、メルマガで流した慶應大学の文系学部の小論文問題の解説を掲載しています。
慶應クラスでは、構造ノートや構造議論チャートを使ってもっと詳しく細かく各学部の過去問解説を動画で行っています。
慶應大学文学部 2016年 推薦入試 小論文 過去問題解説(2015年度実施)
こんにちは。
牛山です。
本日は、慶應大学文学部 推薦入試2016年(2015年実施)の問題解説です。
【1】総合考査Ⅰ
テーマ
今回は、「科学・人間・社会の未来」というテーマの文章が出題されています。宗教、倫理など、幅広いテーマで書かれた文章です。
設問1
設問1は説明問題が出題されています。
ただ、説明問題と言っても、実質的には抜き出し問題に近いです。
設問の要求は、以下のようなものです。
------ここから-----
「この両者はある意味でかなり異質なものだと思われる」とあります。どのように異質なのか、著者の主張に基づいて説明しなさい。
-----ここまで-----
ちょうど課題文に該当箇所がありますので、著者が述べている部分を抜き出し、文章を設計しましょう。課題文の中では比較的広範囲で説明されているので、まとめるのが大変かもしれませんね。
いろいろなところに盛り込むべきポイントが散在しているので、気を付けながら文章を作っていきましょう。
設問1 解答例
民俗学的・歴史的な関心と、未来や科学や宇宙への近代科学的な関心の違いは大きく二つある。第一の違いは、それぞれが捉えようとする対象を推し量る「時間軸」の違いである。民俗学・歴史学は古い時代から存在する地域の神社が発するメッセージ等に関心が向かうが、近代科学は短期的にしか物事を捉えない。第二の違いは、近代科学が取り扱う均質に流れる抽象的な時間と、民俗学・歴史学的関心に基づく時間の深さ等を扱う非均質的な時間の違いである。前者は、一本道の科学とでも呼ぶべき一元的な解釈の上に成り立っており、後者は関係性、多様性、に関心を向ける新たな科学のあり方である。
設問2
設問2は以下のような要求になっています。
------ここから-----
「地球倫理」が求められるのはどのような理由によると著者は考えているか、著者の主張に基づいて説明しなさい。
-----ここまで-----
この問題については、課題文の中で明確に「理由」として、述べられている文章があるわけではないので、課題文の該当箇所を理由化してまとめることが大切です。
間接的に説明してしまうと、何のことなのかよくわからなくなってしまうリスクがあります。
なるべく直接的に理由を説明することを試みましょう。
設問2 解答例
地球倫理が求められる理由は大きく二つある。第一の理由は、従来のキリスト教やイスラム教などの普遍宗教同士が互いにそのままの形で共存することが困難になっているためである。近代に至るまで、地球上の各地域間の交易はある程度限定されていた。そのため、各普遍的宗教は、地域別のすみわけができた。しかし現代はそれが難しい。第二の理由は、地球上の各地域に存在するアニミズム等の自然信仰が、各普遍的宗教において、価値を与えられなかったためである。地球倫理は、これらのローカルな性格を持つ自然崇拝に積極的な評価を与える。
【2】総合考査Ⅱ
(1) 問題
総合考査Ⅱでは、以下のような問題が出題されています。
------ここから-----
次の文章を参考にして、「社会を成す」とはどのようなことか。あなたの考えを述べなさい。
-----ここまで-----
課題文は大変短い文章です。
ヘイトスピーチについての文章が出題されていますね。
読み取りのポイントは、他国と日本が対比関係で語られており、
著者は日本人を批判的に見ていることです。
他国・・・ヘイトスピーチへの激しい反応が見られる。
日本・・・ヘイトスピーチへの激しい反応が見られない。
この対比関係を問題意識として把握しましょう。

設問に答える際に、この問題意識に応答するように、答案を設計することが大切になります。
解答例
社会を成すとはどのようなことだろうか。近代的国家成立の歴史は、人権闘争の歴史であった。憲法人権規定の源流は、ヨーロッパの王政に対する反省から生まれている。ヨーロッパのように、地理的に異民族が入り乱れる地域においては、早くから人権への意識が高まり、法による支配の原理が発達してきた歴史がある。一方で日本は島国の単一民族国家であり、世界最古の国家である。従って、人権が本格的に法の規定に取り入れられたのは、戦後GHQ占領下で規定された憲法が最初と言える。このように日本国における最高法規である憲法の獲得は、闘争の結果成立したものではなく、他国から与えられたものである。我が国の国民の人権意識が希薄である理由はこのような社会的背景にあると考えられる。
従って、「社会を成す」とは、実質的には本来不文律となっている倫理意識も含めた人権意識を、その国家の国民が持つことだと私は考える。