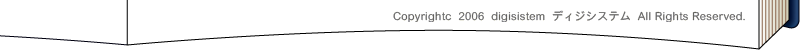Ⅲ 小論文の実力とは
(1)イシューツリーによる小論文のスキル分解
小論文の実力は分解すると次のようになっている。

(2)小論文試験の一般的配点
一般的な小論文の配点は以下のとおりである。従って配点に応じた自分自身に不足しているスキルを高めることが、王道の対策となる。
1)内容力(論理的思考力・スキル)⇒考えられない問題に該当。
2)構成力(論理的思考力・スキル)⇒考えられない問題に該当。
3)表現力(文章表現力・スキル)⇒書けない問題に該当。
4)発想力(クリエイティブな思考力)⇒思いつかない問題に該当。
5)理解力(読解力・スキル)⇒読めない問題に該当。
(3)センス・感性が与える影響
それでは、センスは上記の1〜4のどこに該当するのか。原則としてすべてに影響すると考えておく方がよい。
(4)A:理解力とセンス
小論文の問題にしろ、現代文の問題にしろ、問題をロジカルに扱うことはできる。言い換えれば、人が納得するように説明することはできる。しかし、いわゆる「分かりやすい説明」と、「実際の思考」は一種別のところもある。納得している側が、勘違いしていることもあるからだ。教えている側が勘違いしていることもある。実態を把握することと、理解することの間は大きい。言い換えれば、何かを分かった気になることと、本当に理解することは違うとも言える。「何かを分かった気になること」は誰でもできる。しかし、「本当に理解すること」は一部の人にしかできない。物事をロジカルに説明するということは、物事の複雑性を無くし、情報をそぎ落とすことでもあるからだ。この時に、本当に重要なことまでそぎ落とされることが多い。
何かを説明した時に「あーなるほど、へぇー」と言っていた生徒が、「では、説明してみてください」と言われると、何も言えなくなるのは、本当に理解できていないからである。
(4)B:分析力とセンス
センスは分析に大きな威力を発揮する。私が過去問題の分析をする重要性を強く説き、あえてハウツーを掲載しなかった理由はここにある。分析をハウツー化しても、人は分析などできやしないからだ。
私は教え子からも「思考のプロ」などと言ってもらえることもあるが、MBAホルダーであれば誰でも分析が得意かと言えばそんなことはない。私が通った大学院では、学長が特に厳しく、実践経営を重視していた。通常MBAのコースでは、50年ほど昔の企業が置かれた状況、事件などをケースとして扱い、皆で議論、分析を行う。ハーバードのMBAですらそうなのである。しかし、このように昔のケースを扱っても、その企業はすでに倒産している、あるいは、事業環境が激変しているなどの理由から、どうしても導かれる答えは、「もっともらしい正解」にならざるをえない。そのことを強く教授に指摘すれば、「いや、これは勉強用のアレなんで」と、弱気な答えが返ってくるという。そこで大前氏は、今現在リアルタイムに起こっている事例を扱わなければダメだ!という厳しい哲学を持っており、当時学生だった我々は、大変な思いをしながら理系のケースなどをリアルタイムに扱っていた。今となってはいい思い出である。
当然そのような場合には、理想的な分析手法はあるが、コレを使えば分析できるというようなものはない。問題解決学の手法そのものをハウツーだと思っている学生も中にはいるが、そんなことはない。そもそも、問題解決の手法を手順化などすれば、そのような手法はその瞬間に陳腐化する。このような手順化思考は、もっとも考えることに関する素人が陥りやすい罠である。そして、レーダーチャートや手順をもっともらしく「分析」などと言ってしまう。それは分析でもなんでもない。ただの「ハウツーレベルのティップス」にすぎない。(※ティップスというのは、小技、お得情報の類い。)
問題解決学には、理想的なアプローチが存在する。それは問題解決の原理原則に照らして、妥当なものと言える。ところが、仮にこのような問題解決の手法をハウツーとして見た場合どのような問題が起こるか。
目の前の問題を特定のフレームワークに当てはめて、ガチャガチャを回すように思考回路ゼロの状態で、適当なことを述べることになる。
少しイメージしづらいと思われるので、分かりやすく言えば、「恋愛のハウツー本を読みまくった人」のようになるのである。恋愛本によれば、異性の気を引くためのポイントを分析する手順からいくと・・・・などというおよそ現実からかけ離れた恋愛対策が成される。例えるなら次の写真のようなものである。
「陸上部の彼のハートをゲットするために、傾向に合わせた筋力トレーニングを1年間がんばったわ」

あの男子は、運動をいつも激しくするような傾向で行っているからして、「傾向と対策」の考え方から言えば、激しい運動をしているあの男の子の気を引くには、私も激しい運動をしている女子になればいいんだわ!(きっと)・・・・というように、まったく現実にそぐわない考察がなされてしまう。
そもそもこの文章を読んでいるあなたも感じているように、異性から魅力的にみられるポイントはそのような「傾向と対策」などというざっくりしすぎたどんぶり勘定からはじき出されるものではない。なぜならば、傾向がそうだからと言ってその対策が有効かどうかはわからないからだ。また、その傾向と呼んでいたものが、果たして傾向と結論付けていいのかどうかも、はなはだ疑問である。感性が不足した物事の分析とは、このようにどうでもいい点を重く受け止め、「ズレた分析」に「ズレた対策」を行うような悲劇になりやすいのである。
「編み物好きのあの娘に告白するために、編み物の練習さ。」「まだ一度も話したこと無いけどね。」

こうやって紹介すればいかに馬鹿げたことが日々クールに知的な雰囲気の中で「多くのごまかし」と共に行われているかが分かるだろう。大手のコンサルティングファームのやり取りですら、このようなごまかしはいたるところにあり得る。私たちが問題解決学を学び、本当に小論文に効果的な分析や思考を学ぶ際には、ハウツー本のような考え方をしないことが大切だ。分析には感性が必要なのである。
ナンパに長けた男なら、女性を見て少し話をすれば、いつの間にか相手に合わせた話をしているものだ。異性との付き合いがうまい男性は、会話を盛り上げるのもうまい。芸能人で言えば、お笑い芸人の陣内氏はその典型かもしれない。
本当の分析は、「限界まで細かく研ぎ澄まされた論理思考」のことであり、もっと言えば、「極めて感性的なもの」である。ここについて、ピンとこない人は、そもそも思考の練習が足りていない可能性がある。なぜ本当の分析は、「限界まで研ぎ澄まされた論理思考と感性」になるのか。
その理由は情報収集には常に限界があるためだ。時間と資源が限られている中では、物事を分析する際に、何が重要なのか、物事に重みづけを行う必要がある。この作業を「情報のあたり付」などと言う。このような作業は、事実を集めることでも可能となるが、事実を集める前にも必要になる。従って常に何が重要なのかという仮説を立てながら私たちは考察するしかない。
(5)C:思考力とセンス
思考とセンスは大きな関係がある。ここまでにお話ししたように、物事の発想にセンスは役立つからだ。(情報のあたり付けのことである。)考察するということにセンスや感性が必要ないと考えるのであれば、相当考えることが苦手である可能性がある。あるいは、適切な頭の働かせ方を学んでいない可能性がある。
人の脳は左脳と右脳に分かれている。左右二つの脳の働きについて、脳科学では主に以下のような特性があることが分かっている。
・左脳・・・論理をつかさどる。
・右脳・・・感性をつかさどる。
物事を考えるとき、左脳メインで考えていくと、考える幅が極端に狭くなる。何も書くことができない場合に、とにかくネタを詰め込もうとするのは、「左脳的な頭の働かせ方」の典型的なパターンだ。
物事を考えるとき、人は言葉でも考えることができるが、言葉以外でも考えることができる。抽象的な概念、人の感情、空間、時間などを頭の中にイメージしながら、考察し、最後に自分が「見えたもの」を言語化する。このような頭の働かせ方ができないのは、センスが無いからというよりも、「センスを働かせる頭の使い方」をしっかりと教わっていないからとも言える。感性を働かせる頭脳活動ができないということは、あなたの頭脳のポテンシャルの半分も使っていないのに等しい。

センス・感性を働かせる思考のイメージ図
右脳的なイメージによる頭脳活動と、左脳的な言語をメインとする頭脳活動では、数万倍の開きがあるとも言われている。現実に右脳をフルに活用する記憶方法を駆使し、円周率を覚えている人物は10万ケタ程度円周率を記憶している。(ギネスブックに載っている。)イメージで物事をとらえないということは、言葉で捉えるしかないということでもある。音、空間、抽象的概念、感情、時間などをぐるぐると頭の中で動かすことができない状態は、言ってみれば10〜20年前の動作の遅い処理速度が全くないパソコンに作業をさせているようなものだ。

このようなことをやっているから(何を書いていいのか分からない)という悩みを持つようになるのである。本当は何を書いていいのか分からないのではない。単に、何も思いつくことができないだけだ。このような生徒が何も思いつくことができない状態に対して、多くの小論文講師は、「知識が足りないからだ。」あるいは、「ハウツーを学べ。」「型にはめろ。」と言ってしまう。肝心要の頭の働かせ方を教えてもらっていない人が、いくらハウツーを学んだところで、情報処理の速度がまったく変わっていないのであれば問題は起こり続ける。考えてみて欲しい。旧式のパソコンで、処理をさせられている状態を。(例えるならば)単に最新式のパソコンに変えればいいのである。
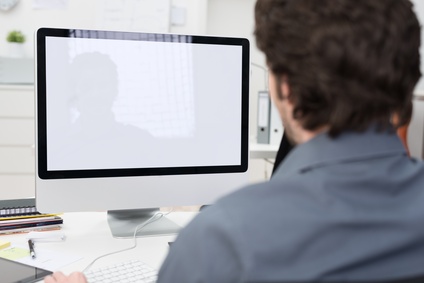
感性を働かせる思考方法とは、より一層あなたの頭の中に流れる情報量を増やし、妥当な考察ができるようになることを試みることに他ならない。
(6)価値観のすり合わせと説得力とセンス
近年小論文の問題でも、IQだけではなく、EQが試される問題が増えてきている。このような問題に対処するには、感性が重要になる。あなたの知人や友人が涙を流しているときに、どのように声をかけるか。このようなことも、感性を働かせればそれだけうまく対処しやすくなる。

ディジシステム HOME