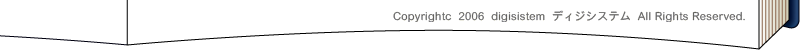4)良質なインプットが点数引き上げのカギ。(学習機関によって論文指導のレベルが違いすぎる。)
インプットなくして、良質なアウトプットはありえない。
慶應大学の小論文はこうやれ!と自信満々にユーチューブで解説している人が慶應に落ちている・・・なんてことがある。
AOはこうやれ!と教えている人がAOに落ちていることがある。
そういう指導を真に受けて、従う人は不幸である。
良質なインプットとは、こうやれば点数が高いという道である。
やっかいなのは、自分のレベルがそれなりでなければどの指導のレベルが高いのかはわからない点である。
わからない場合、あっているかどうかが目安になってしまう。しかし、あっているかどうかは、いやではないという程度のことであり、実はあなたの合否には関係が無い。
あっていることだけやっていたいなら、新宿や渋谷をブラブラして、あそびまくっていても、このやり方は自分にあっている!
ということに、極端な話だが、なってしまうだろう。自分がやっていて楽しいことをやることが、合格への道ではない。
間違ったことを教えられれば小論文では点数が下がる。そして、この不合格パターンは、慶應受験では非常に多いのである。
論文指導はそもそも博士課程を経た人が行っている。その意味で、学部卒で論文指導ができる方がおかしいと考えられるのが一般的である。
ところが、小論文なので何を教えてもいいだろうということで、わりとここはいい加減に考えられていることが少なくない。
小論文という科目は、軽量的な簡易版なので、まぁまぁいい加減でもいいのだ
という考えはあるようだ。しかし、近年の慶應大学小論文の出題を見る限りでは、
どうも学術に対する理解が不足していると不利になるような問題が頻出である。
研究スキル、アカデミックスキルがあると、点数を取りやすい問題が多く出ている。
結局のところ、論文をどのように構成すべきかという問題は、論文そのものの設計思想によるところが大きい。
大学教員が「これは論理的である」とか、「これは論理的ではない」と言うときに、必ずしも論理そのものが、評価対象になっているわけではない。
そのため、論文や研究の構成や設計に詳しくなければ、なぜここにこれを書かなければならないのかということが、根本的に理解できない・・・ということになってくる。
学士レベルでの指導の場合、そのような根本的な問題に直面した時に「これが決まりだから」とか「おれがそうしたから」とか「とりあえずこれで受かっているから」など、
まったく指導でもなんでもない内容が教えられてしまうことが少なくない。
序論には何を書くのか、なぜ序論があるのか、序論が論文で果たす機能 とはどういうものか、論文全体の構成はどうであるのがよいのか、 その理由は何か、どうあれば論文は美しいのか、論理に一貫性があるとは どういうことか、論文の構成の内、序論にはどこまでを書いていいのか、 研究はどうまとめるのか、なぜそれがいいのか、なぜ世界の論文はこの ように共有されているのか、自分が学術をやるとはどういうことなのか、 どのように論文が扱われるのか、序論はどのように読まれるのか、 どのように序論を書くとどのように思われるのか、どのように書くことが 評価される序論の要件なのか、論理的であるということの意味はどういうことか、 序論でどのように論理設計の役割を果たすべきか
など、大事な考えを列挙していけばきりがない。
このような問いに、論文の経験が浅い人は答えられない。だから大学教員は一般的に博士課程を経ている。
5)合格率のごまかし方法に詳しくないとあなたが騙される。
そもそも小論文が受験科目にない大学をならべて、ここのどこかに受かっています・・・という報告は慶應大学を受験する人には何の参考にもならない。
合格率は、ごまかしの手法が悪質であり、多くの人が勘違いをしている。合格率を計算するには母数も大事である。
成績が良い人間を母数とすれば確率は大きくなる。母数にもってくる数字を意図的に操作されると、数字がくるくる変わってくる。
情報の裏が取れない以上、最初から気にしない方がよい。また、そもそも合格を取るという作業は、主体的な作業である。
どのように自分が主体的であるかという問題を放置したまま、合格率がどうかを気にしすぎてもあまり意味が無い。
たとえば 合格率が低い方がよい指導が行われていることもある。どういうことか。
きちんとついていけば受かる指導をする学習機関は、ダントツに伸ばす力があるだろう。
ダントツに伸ばす力があることと、だいたい塾の生徒がやめないことは、本来まったく別のことである。
厳しく良い内容を指導できるから、やめるということもある。塾の生徒がついていけない高いレベルの話をしないことは、塾の生徒が減らない方法であるかもしれない。
しかし、生徒の力量も上がりはしない。この意味で、わかりやすければ、それでいい、それだけでいいという考え方は根本的に間違っている。
難関試験に合格するという作業は自分と塾との主体的な取り組みの成果であり、何かが勝手に化学反応を起こして、自動的にうまいぐあいに努力もせずにうまくいくことにかけるようなギャンブルではない。
硬派な塾は合格率が高く誰でも受け入れる塾は合格率が低くなるだろう。
このように、本来統計的な発想で物事を確率評価する際には、統制できる指標を統制した上で、比較を行わなければ意味のある比較にはならない。

■小論文の添削サービス 〜DVDで解説を聞いて高得点の解き方とポイントが分かる〜
記憶術、速読、英語など各種技術習得をサポートするディジシステム HOME