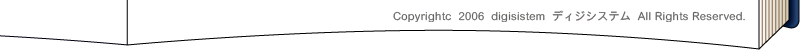Ⅴ フレームワークとは何か
1. 「主」は思考であり、「従」がツール(フレームワーク)
フレームワークとは、あくまでも道具(思考ツール)である。主従関係で言えば、「主」はあくまでも思考そのものであり、「従」が思考ツール(フレームワーク)である。 4. 記号思考とピクチャー思考
数字と言葉で思考をするのは、記号的思考である。一方で、自分が見えたものを思考するのは、ピクチャー思考と表現できるかもしれない。イメージで物事を捉えるとは必ずしも視覚的イメージで物事を捉えることではない。イメージで物事を捉える際には、概念的なイメージも存在する。概念的イメージも、時間軸のイメージも、視覚的イメージも複合的に頭の中で実態を捉える時に、数字や記号では捉えきれなかった現象を捉えることをやりやすくなる。 5. 枠の範囲内の思考となる
最初から物事をフレームワークで考えた場合、狭い枠の中で物事を認識し、狭い範囲で頭を働かせるようになってしまう。これがフレームワーク第一主義の弊害である。
フレームワークによって問題を解決できると考えてしまってはいけない。私自身、フレームワークを小論文の世界に持ち込んだ人間として、この点を強く強調しておきたい。
フレームワークによって問題を解決できると考えれば、「従が思考になる思考法」になってしまう。
劇的ビフォアアフターというリフォームのTV番組がある。この番組では匠(たくみ)と呼ばれる建築士が、依頼人の要望を聞いて、一つずつ設計を行う。ひな形のテンプレートを用いた思考とはこのような状況ごとの対策を考察せず、90歳の足の不自由な老婆と、30歳の働き盛りの一人暮らしのビジネスマンに同じ家を提案するようなものである。当然そこに真の問題解決は無い。
2. 主従関係が逆転する思考の末路
主従が逆転する思考は、現実とズレるため、現実に対応できなくなることも多い。また、金太郎飴を切ったように、工業製品化された思考が行われるため、どの思考も何の面白みも無くなる。多様性が失われ、画一化される。入試問題が仮にこの状況に対応できるものになった場合、慶應SFCの問題は腰が砕けるほど簡単になり、皆の点数が均一化するばかりか、思考力が無い学生の集まりになることが予想される。もちろん、現状ではこのような金太郎飴のような対策有効に機能することはなく、問題解決力の素養が計測されやすいように、問題が工夫されている。
3. 自分の目で見て、自分の頭で考えなさい
「自分の目で見て、自分の頭で考えなさい」とは、私が大学院の入学式で当時学長が言われたことである。主は、フレームワークではなく、自分の思考である。その思考を行う際に、自分に見えたものが大切だ。
数字や言葉で物事を捉えようとすれば、数字化できない部分や言語化できない部分は考察の対象から外れる。情報不足の中で考察を行うようになる。
6. 小論文の『型』と『構成』とフレームワーク
小論文は型にはめて解けばよいという指導がある。これは大変危険だ。その理由は、問と、答案がずれることが多いためである。受験生が用意した型に対応した問題を大学が設計している場合はうまくいくが、対応していなければ、ズレたことを書くので、大変評価が下がってしまう。求められていないことを書くからである。まとめると以下のようになる。
【型】
・基本的に型にはめて解かない。
・原因を書いた後に対策を書くという書き方は、原因が仮説となるため、分析用の資料を提供されていない場合は用いるべきではない。(確証の無い仮説を元に持論を展開してしまう。)
【論文の構成】
・論述問題の場合・・・問題設定⇒意見提示⇒理由(データ)⇒結論
・述べる問題の場合・・・構成は設問で聞かれた通りに設計する。
※一般的に論文の構成は、序論、本論、結論で書くと言われており、問題設定⇒意見提示⇒理由(データ)⇒結論は、その設計思想と全く同じ。小論文用に問がついているだけとなっている。
【フレームワーク】
・あくまでも補足的に使う。
7. 規格外の次元で考察する意義と価値
考察過程が小さくまとまれば、考える内容は自ずと小さくまとまったものとなる。皆金太郎飴で切ったように、同じことを考え、小さくまとまり面白みが無くなる。
フレームワークを用いる時には、この点に注意して、フレームワークを用いるメリットを最大化させることが必要だ。そして、間違ってもフレームワークを主として考えないことが重要である。フレームワークはあくまで「従」であり、考察の道具として使用することが大切だ。
あなたの合格を願い、筆を置きたい。
ディジシステム HOME ・ 慶應クラス ・ 速読情報活用塾 ・ 文和会