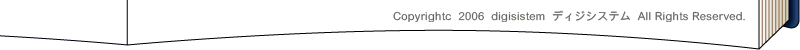第四章 牛山が伝えておきたいこと
勉強の基礎体力が無いのに、勉強するのは、筋力の無いアスリートを養成するようなもの
記憶力を強化すると言えば、難しいと感じる人も多いようだ。勉強のアプローチを変えるだけで、ずっと記憶しやすくなる。勉強のやり方を知らなければ、大変な努力を重ねても成果につながらないことも珍しくない。このような失敗を避けることが大切だ。不合格になってからでは遅い。
勉強の基礎体力とは、速読力や、記憶力のことである。速読や記憶が得意になれば、基礎体力があるアスリートのようになる。勉強時間が伸びれば伸びるほど、差がつく。
その理由は次のようになっているからである。
勉強時間×勉強の基礎体力=成果

学習アプローチを柔軟に変更して結果を出した事例
勉強のアプローチを変えることは、少し大変なことだ。多くの人はあまり自分の学習スタイルを変えようとは思わない。柔軟にスイッチすれば、急に結果がついてくるということは珍しくない。以下にご紹介するのは、勉強のアプローチを変えて、60冊程度の記憶処理を実現した辻本さんが書いた本である。(部分的に執筆しています。)
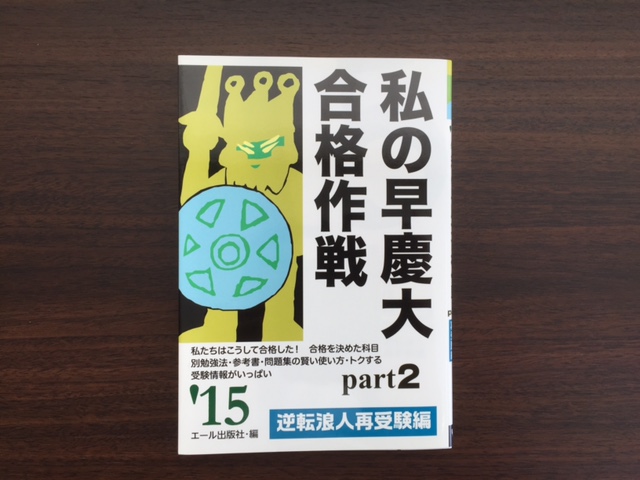
図:慶應大学4学部に合格した辻本さんが書いた私の早慶大合格作戦
多くの人は大変な遠回りをして受験しているから勝つことが難しい
多くの人は、遠回りをしている。多くの人は、勉強のための勉強をしてしまっている。
【偏差値を上げる教育】
〜受験に役立たない理解を作りすぎる無駄〜
偏差値を上げる教育は労多く、益が少ないのが特徴である。近視眼的で、長期的な視野が無いからだ。短期的な記憶しか目に入らなくなりやすい。偏差値を上げることに一般の受験生が腐心している間に中高一貫校の生徒は、さっさと理解作業を終えてしまい、暗記に徹する。当然暗記に徹すれば、学習密度は高まる。試験は記憶で決まっている。偏差値を上げる教育はこのような受験戦略を取ることができないので、膨大な無駄な時間を投資して、時間をかけて偏差値がゆっくりと上がる。
当然だ。力を分散しているからである。長期的に結果を出す視点がないのだ。
受験本番の記憶量が軽視されているので、ゆっくりとまんべんなく全科目の理解度を引き上げる教育が行われてしまう。その結果どの力も中途半端に引き上がり、結果につながらない。
【英語の教育を受けていた人があっさり慶應、海外のトップスクール合格】
〜実務に使えず、受験でもとんがりを作れない作業に膨大な時間を費やす無駄〜
英語ができる人は、あっさりと慶應大学に合格することがある。受験英語の範疇でしか英語を鍛えていない人は英語を読めず、英語でものを考えられず、英語を話せない。付け焼き刃の勉強で英語が難しい試験を受けるので、慶應大学にも受かりにくい。また、英語の能力が中途半端だと、海外のトップスクールには合格できない。一方で小さな時から英語を鍛えていた人は、海外の名門校に合格することもある。最初から逆算された教育を受けていないので、すべてが中途半端に仕上がってしまい、成績の向上も中途半端になってしまう。まず英単語を覚えて、その次に、文法をやり、構文を覚えて、英熟語をやり、英語長文をやるなどという一般的な勉強スタイルで勉強をしていると、英語の力は高まらず、ギリギリ受かることもあれば、受からないこともあるという状態になる。逆算できておらず、中学受験、高校受験、大学受験と、その都度あわてるように対策をしているので、すべての力が突出しないのである。中学専門、高校専門とそれぞれの受験にあわせて最適なサービスを選択しているようで、実は近視眼的な対策になっており、勉強をやる気も高まらず、勉強時間が伸びず、記憶量もその場しのぎで伸びず、学習の進捗状況も悪く、英語の実力もほったらかし状態になってしまうという失敗を世の中のほどんどすべての受験生が犯してしまっている。目の前の偏差値の高さに一喜一憂する、その時の順位に一喜一憂するということをやってみても、いざ就職する時にはそのようなことはほぼ考慮されない。
【就職の際に困る発信力の無さ】
〜さんざん勉強してきたのに、いざ就職になると(使えない)と思われる教育の無駄〜
受験勉強のほぼすべては、就職する際にまったくと言っていいほど役立たない。就職の面接で確かめれられるのは、あなたの発信力である。発信力とは、話す力やその土台の考える力である。ところが日本の教育は発信力を育まない。大学を卒業する時になってはじめて、自己PRや、小論文の力を試される。文章も書けない、自分の考えも話せない、自分で考えることはやったこともないという状態で突然就職セミナーなどに通うようになる。これも大変無駄なことと言えば、無駄なことである。大学受験の際に、面接の練習や考える訓練を受けている人は、就職の際にあわてふためくことはないのである。
【ビジネスマンになってからの英語と速読の勉強】
多くの人はビジネスマンになってからもずっと英語の勉強をやる。英語の勉強や速読を勉強し、問題発見や問題解決を学ぶ管理職の人も多い。これらのスキルは受験時代に鍛えておけば、後になって慌てる必要はない。また、問題発見や問題解決のスキルは、受験に役立つ。問題解決の力があれば、日常の生活を改善し、自立して物事に取り組むことができるようになる。受験の際には、問題発見能力や問題解決能力を試される慶應大学を受験することもできる。
本人も周りの大人も誰も気づかない内に本当はリスクが大きくなっている
ここまでにご紹介したことは、無駄というよりも、大変恐ろしくももったいない出来事の事例である。日本の教育システムは、実社会とほとんどリンクしていない。学校の勉強をすることこそが、将来につながるのではないか?という理論にかけることにより、若い時に思う存分勉強することが出来る時期に、大切なことを学ばず、受験で何ランクも志望校のレベルを引き下げ、受験術も知らず、自分の才能を活かしてAO入試などで、慶應大学や早稲田大学、京大や東大に推薦や特別入試で合格することもできなくなる。
さらに、本を読むことも日本の教育では推奨されないため、ほとんど本を読まずに成長している若者が少なくない。このような若者はすぐに答えを求めようとしてしまう。自分で調べ、自分で考える癖がまったくない。若者に責任はない。教える側に責任がある。
日本の教育は、この考えるという教育が大変軽視されている。それを象徴するのが、センター試験である。共通試験のマークシートでどれだけ覚えているかだけをチェックされる。海外で小論文に該当するショートエッセイで、自己PRや、思考力を試されるのとは対照的な教育が日本では支配的だ。ところが就職する際になると、急に実務で必要となるクリエイティブや、オリジナリティー、自己PRなどが求められる。したがって日本の一般的な教育システムで勉強をしてきた人は、学校の成績と順位に目が奪われている間に、大学受験で勝てない状況になりつつあり、その後も苦労するようになる状況に自分自身が追い込まれていることにあまり気づいていない。
言い換えれば、受験生活以前の中学1年生から、大学を出るまで、相当大きな遠回りをして、実際に使う知識と経験を鍛えない。
的はずれな反論や取るに足らないやっかみが多いので念の為に言及しておく。私がここで述べていることは、文脈から判断出来る人は既に気づいていると思うが、一般的なキャリア教育や受験教育の観点から、子どもや親が望む目的に手段が全く合致していない損失についてである。
多くの受験生も、保護者も、より一層高いレベルの大学を受験することを望む。大学の側も同様の評価軸を持っていることが少なくない。しかしながら、双方がこのようにハイレベルな教育を高く評価しているにもかかわらず、そのように高いレベルの教育を受けるチャンスを小さくしているのである。
そして、さんざん結果につながらないことに、全体の時間の90%程度を注ぎ込んだ挙句、頭が良い、頭が悪いということを、大学のレベルを基準にして述べる。学校のランクでその人の頭の良さが決まっていると思い込んでいる人は、財界人やトップレベルの知識人でもまったく珍しくはない。
競争要因を考慮せずに、評価が行われる。評価する側も、受験する側も、教育する側も、大学側の人間も、すべての人がこの教育問題については、教養教育、自由、権利、美徳、理想など、雑多な論点から論じることで話がまったくかみあわず、お茶を濁しているのである。
ここに気づいた人は、勝つのが早い。この受験というゲームの本質は競争である。競争である以上、競争要因が違う。
従って東大と慶應を同列に扱ったりすることに本質的には全く意味が無い。
ところが、偏差値や世間の基準で、同列に扱い序列化することができると思い込んでいる人も多い。 こういう人は、ハーバード、ケンブリッジ、東京芸術大学、東京工業大学は工業系で世界トップ10入りと聞くと頭が混乱してくる。序列化しか頭のなかに無いからだ。
序列化できないものや、他の評価軸が意味を持つものになると頭が混乱してくる。
頭が混乱しない簡単な方法がある。大学別の困難性と異質性を理解することだ。
現実には異質な困難性が大学ごとに存在している。世間基準を無視して、スキルギャップと知識量のギャップから各試験を見ると、合格する道が透けて見えてくる。

難関試験に不思議と何度も不合格になる人は、序列化した考えでいっぱいである。難しい試験なので、難しいことをやらなければ、、、と考えていることが多い。
過去問題をやることが大切なので過去問題をやらなければ、、、という考えも同じである。両方共先入観なのだ。
過去問題をやる目的は何ですか?と質問してもこの手の人は答えることができない。そもそも考えたことも無いからだ。
場合によっては、過去問題分析のためだなどと、もっともらしいことを言う人も出てくる。
なるほど、ボクシングの試合に勝つためには、相手選手の動きを研究することは悪いことではない。こんな具合に、徹底して分析することも役にたつことはあるだろう。

ところが、現実にボクシングの試合で、あなたが対戦相手と向かい合った時、TVで分析した内容と違うということに気づくだろう。
現実の世界はこうだ↓

TVで分析した内容と違う。分析以前に、パンチが見えない。気がついたら殴られている。相手は仕留めにくる目でこちらを見ている。頭がフラフラする。みぞおちを殴られて息ができない。苦しい、こちらのパンチが当たらない。
おかしい、方法を教えてもらったのに。勝てるテクニックを教えてもらったのに。なんで勝てないんだ・・・と思う前に、あなたは、(怖い)と思うだろう。
単純な話、実力が足りていないのである。過去問題をやる?というのは、練習せずに、ボクシングのビデオ研究をやっているようなものだ。
基礎体力がない、力が足りない、練習をしていない、基本がなっていないのである。
もしも、バスケがうまくなりたかったら、(実践形式だと思うので)マイケルジョーダンと3オン3をやっていればうまくなるなんて言えば、マイケルジョーダンから、「冗談だろ?」と言われるのがオチである。(ジョーダンだけに。)
本番形式だったら最短で実力アップできると考えるのは、なめているということなのだ。バスケもボクシングも、小論文も勉強も同じである。
多くの人は過去問題はやるものだと思っている。そうではない。過去問題は、年度別と分野別でやる意味が全く変わってくるものなのだ。年度別は、捨て問の選別など、解答力を引き上げるためである。後者は、必要なスキルを見極めるためである。このような目的意識が無い人は単にやることが目的になる。現実には高いレベルでスキルを発揮しなければ、合格できない論文試験も数学の過去問題のように考えてしまい、過去問題ができれば、合格できるなどと錯覚するのである。そんなことはない。
単にやることが目的化した人は膨大な無駄な作業をするようになる。
受験も同じだ。単に受験勉強をやることになっている人、単に勉強をしている人、何の目的で、どの試験を受けるためにやっており、いつどうなるかの予測ができない、こういう勉強は労多く、益少ないのである。