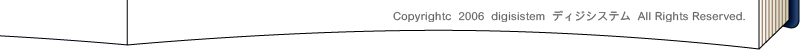最大手予備校が威信をかけて作った問題集で60点の現実
そもそも、最大手の予備校が威信をかけて作り上げた問題集を1冊記憶しても、早慶などの大学を受験した場合、約60点程度しか点数を取ることができない。(どの問題集をやれば合格するのか?)と考える前に、東大に1000人程度合格させている最大手の予備校の資金力と熟練した講師の力をもってしても、これらのテキストを全部覚えてそもそも、不合格の点数しかとることができないという現実を受け入れることが大切だ。
ここで何が起こっているのかを考えなければならない。
何が出るかを当てることができる人などいない
基本的に、英語や歴史については、特にそうだが、何が出るかを当てることができる人などいない。仮にあたったからといって、それを喜んでも意味が無い。
なぜならば、そんなことでは合格しないからだ。私が運営する塾から慶應大学合格者がバンバン出ているのは、はなからあたるかどうか、ギャンブルのように受験準備を進めることを推奨しないからである。
「ギャンブル的に出題されるところをあてるので、なんとかあたってくれたら、あなたの点数が3点〜6点上がりますよ!」というメッセージにすがるような受験生ばかりでは、全員が不合格になっても不思議ではない。最初からズボッとダントツに、圧倒的に覚えれば合格するのである。
もちろん、最初から出るところが分かっていたら受かるのになぁ・・・と考えてしまうのは仕方がない。しかし、そのようなスケベ心では難関試験にはラッキーでしか合格できない。
例外は予備校の熟練講師が作る予想問題
例外的にゲットしていいものがある。大手予備校の熟練講師が予想する数学の問題などである。これらの問題は予想問題集として、手に入れる価値がある。
逆に過去問題は、もう二度と出ないので、過去問題に出てきた分からない問題を覚えるような勉強はもっとも非効率的な勉強だ。
合格させる資格試験(一定のレベルに達しているかどうかを気にする類の試験)と、競争試験は、その意味合いが違う。
資格試験を作る時には、毎年一定程度の難易度になるように、過去問題の中から問題が選ばれる特性がある。しかし、競争試験ではそのようなことをやる必要は全くない。いちいち過去問題の中から、問題を選ぶ必要が無いのである。
過去問題はやる必要があるが、それはシミュレーションと実力測定、弱点を見つけるためである。
予備校業界は「当たった」と言うために問題を乱発する
予備校業界は大学受験に限らず、「当たった」「的中しました」と言いたい。そのためにどうするか。ボリュームを増やすのである。
公認会計士試験対策の問題集が異常に膨れ上がる、簿記の問題集が異常に膨れ上がる理由はここにあると言われている。
つまり、大ボリュームにしておけばどこかで何かがひっかかったような印象を与えることができるので、受験後に「当たりました!」と叫ぶことができる。
しかし、当然だがあれもやらせる、これもやらせるということでは、受験生の側は何がポイントなのかは分からない。そして予備校業界の「当たりました」に付き合うための勉強を余儀なくされる側面もある。
さらに言えば、出題されるところが当たっても、暗記科目でなければあまり意味が無い。小論文試験の場合は、その当たったものについてどれだけ深く考えることができるようになっているかが重要であり、実質的にテーマが当たっても、問題で点数を取ることができないことが多い。
原則として試験では記憶量と解答力で点数が決まっている
試験で点数を取るにはどうすればいいのだろうか。記憶量を増やし、解答力を引き上げればよい。
試験は記憶の量で点数が決まっている。だから時間を突っ込むことができる人は強い。試験で点数が良いということは、言い換えればそれだけ時間を突っ込むことができたということである。
解答力とは、読解力、記述力、評価されやすい記述作法などである。
記憶量を増やす原理原則
問題集の良し悪しは、記憶量を増やしやすいかどうかが大きな判断の基準になる。ただし・・・・問題集そのものによって、記憶しやすいかどうかはあまり決まらない。そもそも問題集を加工した方が、どれを選ぶかで迷うよりも、はるかに記憶効率を高めることができるからである。
問題集は加工する
問題集は加工するものである。その理由は、もう一度言うが、加工する方が、記憶効率が断然よくなるからだ。そのまま問題集を使うことがある意味で論外なのである。もう一度確認する。あなたの試験での点数は、記憶量で決まる。記憶量は、記憶効率で決まる。記憶効率は、問題集の使い方で決まるのである。
時間があるやつが圧倒的に強いだけのゲームに?
点数がいいと、頭がいいと言われる。点数が悪ければ、頭が悪いと言われてしまう。まるで、点数が悪いことが、すべてであるかのように世間では見られるのをあなたは何度も目の当たりにしてきたのではないだろうか。
この世界では、時に試験の点数はすべてなのだ。だからこそ、名門校、難関校は、点数がいい人間だけがその門をくぐることができる。点数が良ければ知性が高い。点数が良ければ頭がいい。点数が良ければ優秀なのである。
しかし、ここであなたはちょっとした疑問を感じるかもしれない。ようは試験勉強をすることができる人間、やった人間が記憶量を増やし、より一層よい地歩を歩むことができる。ここにまやかしがあることも、不条理があることも、おかしな現象があることも、世間の裏側でそっと闇に葬られつつ、世の中は回っている。
時間が無い場合や、資源が限られている場合は、何らかの工夫が必要になってくる。
東大医学生が合格する参考書を聞かれて述べたこと
東大医学生がある受験生に「どの参考書がお勧めですか」と聞かれて、なんでもいいと答えたり、「一日に何時間勉強したらいいですか」と質問されて、「進めるだけ。」と答えたりすることがある。また、「計画はどうすればいいですか」と質問されて、「最初に覚えたものが終わってから、次に進むだけ」というように答えたりすることもある。
本当にこの通りなのである。「何をやったらいいか、分かりません。」とか、「何からやればいいのか分かりません」と質問する受験生は、あまり勉強しないことが多い。自分があまりやらないことが前提となっているのである。本当に難関試験に合格したいのであれば、そのような考えを持たないことが大切だ。
読むべき本などに至ってはさらにひどい状態が
小論文については、どの本を読めばいいのかをよく質問される。私もお勧めの本を紹介することはある。しかし、あくまでも気にする人がいるのでお勧め本を紹介しているだけであって、本当は何もかも読んでいくべきなのである。
(そんなアホな)
と、あなたは思うだろうか。しかし、本当である。本当を言えば、慶應大学の文系に合格したいのであれば、本を読んで読んで読み倒すくらいでちょうどいい。本を読まなくても合格することはあるだろう。しかし、だからといって、そんなことが本を読まなくていい理由になどなりはしない。
本の読み方というのは、10冊程度、ドンと机の上に置き、猛烈にページをめくっていくような読み方が本来の読み方なのである。じっくり1行ずつ読んでいくような本の読み方が当たり前だと思っていると、大変非効率な読書になる。
実際に慶應大学法学部法律学科に合格した、私の教え子であった星君という若者は、政治経済の本を年間500冊読んだ。私も添削作業をしていたが、当然彼の点数は他の受験生よりも高かった。
誰も批判しない「天声人語を読め」というアドバイス
一般的には、「天声人語を読めばいいよ。」などというアドバイスがよくある。しかし、この手の助言は相当いい加減と言わざるを得ない。確かに、「天声人語を読め」というアドバイスは、誰も否定しないだろう。しかし、それだけだ。
このような当たり障りのないアドバイスは世の中にあふれている。
難しい本がオススメされがち
さらに良くないアドバイスは、とりあえずレベルが高そうな本をお勧め本として薦めるアドバイスである。(難しい本だなぁ)と思ってもらえれば、このような本を薦める人はレベルが高いのだと思ってもらえるのではないかというような考え方から相当どうでもいい本が小論文対策のお勧め本として薦められがちである。
その極みは、大学でしか学ばない専門書だ。医学部の小論文入試で専門の医学書の内容を読んでいればそれだけ点数が高くなるような問題は出たことは今のところない。それもそのはず、裏口入学でもあるまいし、そのような問題を作ったからといって、受験生の知性など推し量ることができるはずがない。知識があるかどうかは、一般科目で十分に確かめられている。