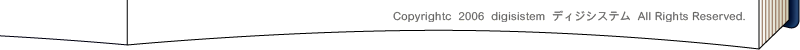-------------ここから(慶應大学絶対合格法より引用)-------------
| 《慶應義塾困難性のまとめ(大項目)と対策》 慶應大学の困難性は、合格に必要な記憶事項の多さと、小論文の実力の引き上げにある。逆に言えば記憶を誰よりもできて、小論文ができれば慶應に限りなく合格しやすくなる。 【対策】 慶應大学を専願するなら、高校1年か高校2年から小論文だけはやっておきたい。必要な記憶項目数を確保する期間は慶應文系の場合、高速学習で9ヶ月前後(一日10時間)である。 |
私はこの2点(小論文対策と記憶対策)が抜群に得意な人間だ。日本の歴史上初の、記憶サポート専門の塾である、記憶塾を立ち上げ、学習を支援する会社を経営している。クライアントには、東大OB、東大の大学院OB、弁護士になる為の司法試験受験生、弁理士受験生、公認会計士受験生、税理士受験生、東大受験生、早慶受験生など、日本及び海外の難関試験、難関大学院を含む受験生をサポートして、続々と合格報告が寄せられている。それらの合格報告は、文系だけではなく、理系の国家試験も難関大学も含む。野球でホームラン王になりたかったら、ホームラン王ではなくて、ホームラン王を100人量産しているコーチの方があなたをホームラン王に成長させる事ができる。慶應合格に関しては『記憶量』『小論文』が2大困難性なのである。
小論文に関しては、日本最難関とも言われる慶應のSFCにバンバン合格者を出している。教え子の小論文の成績は全国3位とか、全国約1万人中10位など、TOP0,1%まで引きあがる事例もある。
《データとの比較による仮説の検証》
次の文章は、東大合格者で慶應併願者の合格確率を記載した文章である。ちょっと読んでみよう。
----------------------------------------------------------
東大文Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ生が併願する法・経済・商学部の例年の併願成功率は法学部が約50%~60%、経済学部が約55%~85%、商学部が約80%~95%。すなわち、滑り止めにしようなどというような甘い気持ちで受験すると、手痛い竹蓖返しを受けることになる。その上、2012年よりこれらの滑り止めに使用されていたと思われるセンター利用方式が全学部で撤廃されるため、全ての受験生が慶大独自の対策が必要となってくる。
ウィキペディアより引用
-----------------------------------------------------------
●商学部 80~95%の東大生が合格 小論文の実質配点比率0%(国語知識問題の為)
●経済学部 55~85%の東大生が合格 小論文の配点比率16%
●法学部 50~60%の東大生が合格 小論文の配点比率25%
●文学部 データ無し 小論文の配点比率28%
●SFC データ無し 小論文の配点比率50%
私が提示した困難性は2要素だが、この困難性ファクター2要素の要素比率(実質的には記憶の困難性は全てに含まれる為に、小論文の困難性比率)が増えれば増えるほど、データが示すように、慶應への合格率は下がっている。東大受験生は小論文が増えるほど落ちている。(もちろん東大生は日本一学力が担保された集団であることは疑いも無い事は確認しておきたい。)商学部に小論文は(実質的には)無い。経済学部はあっても点数が低い。法学部は400点満点中100点の為に、小論文の配点比率が比較的高い。商→経→法の順番で困難性の要素比率は増加しているわけだ。それに伴い、東大受験生の不合格率が上昇している。東大受験生の学力の質は担保されている為、他のデータが混じっているよりも仮説の検証はやりやすいと感じる。東京大学と京都大学は同列に見られる事があるが、慶應、早稲田の併願組みの合格率を見れば、東大受験生と京都大学受験生の圧倒的な力の差が分る。ちなみに慶應理工学部は東大受験者の96%が合格している年もある。もちろん小論文は無い。付け加えれば、文学部の小論文は現代文の要素が強い為データがあっても参考にしにくいかもしれない。
慶應の法学部はその記憶の困難性の性質が東大二次試験とは異なる部分が大きい為、この数値になっている事も十分予測できる。ただし、この点を割り引いて考えても、慶應義塾の困難性は記憶作業のレベルと、小論文にあると考えて良さそうである。
さらに加えて言及しておきたい。高校での成績と大学に入学してからの全成績の間には強い相関があるのに対して、小論文の成績と大学に入学してからの全成績の間には相関が見られなかったという研究結果がある。この研究が示唆する事は、分りやすく言えば、勉強ができても小論文は書けるわけではないという事である。スポーツに例えれば、砲丸投げと、短距離走のような違いがあるという事だ。
慶應義塾の困難性の2大特徴の一つは、小論文にある。学力テストエリートは認めたくないかもしれないが、私も経験から、学力(英・国・数・社・理)と小論文の実力には全く相関が無いどころか、マインド的な理由から逆に、学力自慢者は、小論文の点数が低い傾向にある事を痛感している。
ここでさらにポイントを加えれば、記憶の困難性と、小論文の困難性はどちらが強いのか?ということだ。これが学部別の対策の難易を決定する事になり、あなたの戦略決定の重要な判断基準となるのである。結論から言えば、今の手持ちのコマ。あなたの学力のカバー範囲のバランス(何が得意で何が不得意か)にあるという事になるのだが、もう少し詳しく見ていってみよう。※東大合格実力が十分にあり、慶應を仕方なく受けている人は退屈かもしれないがご容赦いただきたい。