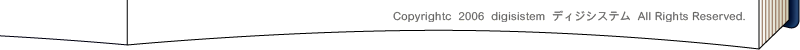15 良いか悪いかの意見は世界で最も安いものである
「人の意見はこの世の中でもっとも安いものである」という言葉がある。
自分の頭を使うことが大切だ。良いか悪いかという意見はこの世で最も安い。なぜならば、世の中の99%の言説は非論理的なものだからだ。根拠はない。常に一昔前の時代を基準に皆考える。従って人の意見に従うということは常に時代遅れになる危険性がある。今の時代は最先端かもしれない。しかし、未来の時代遅れである。その時代遅れの基準に合わせるのは、より良いアプローチが何かを考えることから目を背けることだ。それを本当に考えるには、何千冊と本を読まなければならないかもしれない。真剣に考える必要があるかもしれない。研究をする必要があるかもしれない。実験も必要かもしれない。物事の妥当性を多面的に検証しなければならないかもしれない。私はそれをやってきた。異常に思えるかもしれない結果はこのような仮説と検証、問題解決から生まれている。
16 どっちが本当なの?
(1)アイディアが評価の対象にならないという言説
発想は評価の対象になる。慶應法学部の試験では、発想力が評価の対象になるとはっきりと明言されており、慶應SFCのウェブサイトでは、「発想、論理的構成、表現など総合的能力を問う」と記載がある。そもそも論文や研究で発想力が評価の対象にならないなどということがあるはずがない。デタラメな個人的見解はあらゆるところに転がっているため気を付ける必要がある。
(2)本は読まなくてもいいというアドバイスの危険性
本は知識を得るためのものではない。見識を得るためのものである。
知識はネタとしてしか使えないが、見識は考える土台になる。
受かりやすくなるということである。
本は読まなくてもいいというアドバイスは、大変無責任なアドバイスだ。もちろん、本を読まなくても合格した事例はある。しかしだからといって、本を読まなくてもいいということにはならない。本を読まずに合格している人物はたまたまスキルアップに間に合っただけだ。小論文については、何もやらずともそれなりに書くことができる人がいるためだ。また、このような人物がラッキーで合格することもある。
本は知識を得るだけのために読むものではない。ヒラメキを生む触媒になるものである。従って「知識が無くても受かる」などというのも、反論の論拠として不適切だ。
「構想力、表現力を問う」「発想、論理的構成、表現など総合的能力を問う」などと慶應のウェブサイトに明記されている。本は構想力を得るための触媒となる。本は表現力を得るための貴重な学習機会になる。文章を書くことができない人は文章を読んでいないことが多い。
本を読めば、知識力、構想力、表現力がつく。
要は差がつくのである。
競争が厳しくなればなるほど、本を読んでいる人は有利になる。
本を読まなくてもいいというアドバイスを受けた不合格になった多くの人がかわいそうだ。
※ただし、ネタ本は読まなくてもいい。
(3)小論文はセンスではないというアドバイスの危険性
小論文がセンスではないという意見については知識不足である。詳しくはこちらのウェブブックに書いた。センスを磨けば、安定して合格できる。
「小論文にセンスが不要と考える危険性」と「センスを磨く7つの対策」
感性を用いないと、あなたは半分以下の力で受験することになる。自分で自分の頭を悪くするようなものであり、このような考え方は一生を通じてお勧めできない。一方で、 感性を働かせる頭の使い方を教わった私の教え子は、慶應SFCに現役合格し、その後世界一の理系大学である、マサチューセッツ工科大学の博士課程へと進学した。慶應大学に進学後も、「大学で考える際に、教えてもらったことが役に立っています。」と彼は語っていた。
※海外の大学院(トップスクール)の場合、本当にわずかな人数しか博士課程で学ぶことができない。
慶應クラスで学んだ人は、慶應大学に進学した後も、付き合いがあることが珍しくない。大人になってからも役立つことを教えている。受験の時だけ役立つ内容を私は教えていない。違いを作る違いとは、人生を変えること、自立すること、自分の頭で考えること、より深く考えること、人よりはるかに精緻に考えることなどを含む。
17 絶対合格と合格の違い
慶應大学絶対合格法とは、言い換えれば、(合格するといいなぁ)というような対策か、必ず合格するための対策かの違いだ。
運が良ければ合格するような勉強を絶対合格法ではやらない。あらゆる手段を尽くして、確実に合格することを目指すのである。
・英単語を覚えたが、試験当日間に合わない勉強はしない。
・繰り返して勉強したが頭の中にイメージできない勉強はしない。
・勉強をがんばったが記憶しきれない勉強方法は採用しない。
・最初から併願できる手法を用いる。
・併願可能なスケジュールと条件で学習を進める。
・一般入試と推薦・AO・FITも考慮に入れる。
・「対応できる」ことにギャンブル的にかける勉強はしない。
・小論文のスキルギャップを段階的にステップバイステップで埋める。(そのためのカリキュラムがある。)
・モチベーションの浮き沈みで不合格になるような過ごし方はしない。
・時間ばかり過ぎて成果につながらない的外れな理解作業で時間をつぶさない。
・絶対合格する状況から逆算したカリキュラムを徹底して実行しきる。
18 「絶対合格って本当なの?」という問いはナンセンス
慶應大学に絶対に合格するということが本当かどうかを問うことはナンセンスだ。考えてみて欲しい。因子を考察すれば、方法だけですべてが決まっていないことが分かるはずだ。ここまでに述べたように、問題解決はアプローチである。競争要因や大学側の要因を考察しながら、合格するように動いていくしかない。方法で合格できるのか?と問うている時点で、その人はすでに合格しにくい。競争要因を考慮に入れて、他の人の何倍もの学習密度で学習を実行し、効果的に学ぶからこそ、合格率が引きあがるのである。合格率が50パーセントを超えるところまで実力を伸ばすことができれば、私が提唱した6アタックストラテジーを用いれば、確率的に99%合格する。このことをもって絶対合格と表現している。絶対合格の「お得な方法」があるなどと仮定するから判断を誤るのである。
99%は、100%ではないと誰かが言っても、計算してみればわかるが99,9パーセントには簡単にできる。「残りの0.1%の不合格率があるのでだめだ」などと言う人は最初から受けなければいいのである。試験は水物で努力しても0.1%パーセント程度の不合格確率は存在する。同様に、数学の確率計算についても、一日試験会場に行けば、独立した施行には厳密にはならないという揚げ足取りも無視していい。実質的には変わらない。
何を成し遂げたいのであれば、1パーセントの確率でも勝負できるくらいでなければ成し遂げられない。最初からソロバンをはじいている時点で、マインドに問題を抱えている。自分を信じることができない人は合格できない。自分が合格率を高めるのである。マインドに問題があれば判断が狂う。判断が狂えば合格できない。常勝というのは、0.1%の不合格にビビるマインドからは生まれない。なぜ慶應クラスが常勝なのか。その理由は絶対に合格する、合格するように動くというマインドから鍛え上げるからである。獅子の外見でも羊のマインドなら負ける可能性がある。勝つと確信しているから勝てるのだ。
慶應大学絶対合格法に書いた「獅子の咆哮のようなものである」とは、お手軽一般論勉強法ではないからである。徹頭徹尾すべての側面から問題解決学的に戦略立案した結果、絶対合格を可能にする戦略軸を取るためだ。