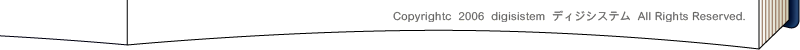4 問題解決学的な戦略提案を方法と勘違いすると失敗する
絶対に合格する「方法」は存在しえない。当たり前である。そんな方法が存在するわけがない。しかし「絶対合格を実現するアプローチ」は常に存在しうる。慶應大学絶対合格法とは、問題解決学で言うところの、「問題解決アプローチ」のことである。「慶應大学絶対合格方法」ではなく、「慶應大学絶対合格アプローチ」なのである。
もう少し言えば、慶應大学に合格するための、合格率が低い受験アプローチと、絶対合格に近いレベルの、大変合格率が高い受験アプローチの違いだ。
|
学術的裏付けと戦略 |
合格する確率 |
学習の有効性 |
慶應大学絶対合格アプローチ |
○あり |
高確率 |
○学術的裏付けと証拠あり |
一般的な受験方法 |
×なし |
低確率 |
×単なる方法と思い込み |
「慶應大学に合格する方法」と「慶應大学絶対合格を目指すアプローチ」の違いとは何か。「方法」と「アプローチ」の違いは、「問題を解決する原理に沿っている」か「問題を解決する原理原則に沿っていないか」の違いである。この部分の理解は慶應SFC受験生は特に大切なので詳しく見ていく必要がある。慶應大学絶対合格法とは、問題解決の視点から見て、もっとも合格確率が高まる戦略軸の提案に他ならない。むしろ、単なる「こういう風に勉強すればいいと思う。」「こんな風に小論文を書けば、私はいいと思う。」という個人的持論の方が、「方法」でしかないという点において、大変危険だと言えるだろう。
問題解決学の世界では、プロブレムソルビングアプローチ(Problem Solving Approach)と表現される。(PSA)プロブレムソルビングメソッドではない。なぜ方法ではなく、アプローチとして表記されるのだろうか。その理由は、問題を解決する際に、「単なる方法」では非力だからである。プロブレムソルビングアプローチとは、問題を解決するための原理原則にかなったより一層効果的に問題を解決するアプローチのことだ。問題解決を志向する慶應SFCを受験する人はこの部分に特に注意してほしい。
私が拙著「慶應大学絶対合格法」に記載した絶対合格アプローチは、因果を「方法」だけに限定していない。当たり前である。世の中は方法だけで結果が決まらないからだ。従って問題解決学が必要になる。何らかの手っ取り早い方法だけで問題は解決しない。それを分かっていながら、方法はダメだと他者の方法を批判した上で、自分が単なる方法を教えているのが、今の受験業界なのだ。
そして、各人が述べる勉強方法というのは、その論拠が(私が正しいと思うので)という根拠でもなんでもないものが根拠になっている。こんなに恐ろしいことはない。
5「思っているだけの勉強法」と問題解決学的アプローチの違い
問題を解決する際に重要なことは、本質的な問題点を定義すること、大きなアップサイドが見込める対策をすること。「慶應大学絶対合格法」と「慶應小論文合格バイブル」は両方ともこの問題解決のアプローチで書かれている。事実に基づき対策案の方向性を示したものである。ところがほとんどの受験生は「こうやるのが正解です。」「これがいいです。」という個人的な持論を参考にする。だから不合格になりやすくなってしまう。何度不合格になってもそのことに気づくことができない人もいる。なるべく早く気づくことが大切だ。ほとんどの人は、自分がこうやってやれば合格できるという理論にかけているのである。
【間違いだらけの常識】
・英単語を覚えてから長文を読んでいくといいと思う。
・過去問題は実力がついてからの方がいい思う。
・過去問題の文章を理解することが大切だと思う。
・過去問題をやれば、本試験でも合格できると思う。
・偏差値が高い方が難しいと思う。
・慶應のSFCは適正試験のようなものだと思う。
全部思っているだけである。
要は、純粋に勘違いしているだけということも圧倒的に多いのだが、多面的に事実に基づき、その対策がいいという判断を下していないところが最大の問題である。現実はこうだ。
【慶應合格の真実】
・英単語を覚える前に長文の中で英単語は覚えた方がいい。
・過去問題は今すぐに見た方がいい。
・過去問題の文章を理解しても受からない。
・過去問題をやれば本試験に合格するなどということはない。
⇒全統模試で、高校2年生の段階で全国1位になっていた大変優秀な子ですら過去問題しかやらないと慶應大学は全滅だった。
・偏差値が高い方が難しいわけではない。各学部の困難性に難しさがある。⇒慶應大学4学部に合格した辻本さんも同じことを早慶合格体験記の中で述べている。
・慶應SFCは適正試験ではない。対策次第で合格できる。全くSFC向きではない子をSFCにダブル合格させた経験が私にはある。
なぜ多面的に判断を下すことが大切なのか。事実に基づき多面的に判断を加えれば、効果的に問題を解決できることが多いからである。
慶應クラスでは、4月や5月の時点から、積極的に英語長文を倍速再生で聴きこんでもらっている。他の受験生がシコシコ丸暗記をしているのとは対照的に生きた英語をまるごと頭にインプットしていく。
覚える順番が逆なのである。
英語は、1万項目程度の暗記をできるかどうかで決まる。覚えていれば合格なのである。ただし、多くの受験生は、丸暗記していく方が1つずつやることができるので、早いと思うという理論にかけて勉強している。かけているのだが、そのことに気づいていない。気付くのは早い方がいい。
記憶は「記憶の質」(どれだけイメージできるか)「記憶の確実性」(覚えたけど次の日には忘れたので、そのまま試験を受けたなどとならないようにすること。)「記憶のスピード」(ゆっくり思い出していたのでは受からない。)の3つが必要だ。
要は、この3つの記憶の要素が十分に満たされる形で勉強を進めているかどうかが重要になる。「繰り返しが大切だ」とか、「思い出すことが大切だ」などという、記憶の一般論でしか対処しないから、試験当日に「あれ・・・読めない、分からない、時間が足りない」ということになるのである。勉強法と呼ばれるものの情報は99%勉強法の一般論である。私が他と違うのは、一般論ではなく、徹底した問題解決を徹頭徹尾行っていることだ。ここが一般的な勉強法を教えている塾と、慶應クラスの大きな違いである。
英語の授業も含めて通常教師は、「週に何コマの授業をやります。」というように、最初からコマ数を割り当てられる。そのコマ数を消化することが、授業の目的になってしまう。「上から頼まれたので」、「これこれの時間はめいいっぱい英語の話をしないといけないので」、どういう授業をしようかという話になる。そして、「構文の話をします」「今日は文法をやります。」などという話になるのである。英語の文法は文法書をさっと読めば一日で完了する。それを中学、高校と6年間かけて教えてもらうのが、「授業のための授業」なのである。
それでは、約1万項目程度の記憶の質を完全に高く保ち、慶應大学に合格できる頭づくりをより一層誰でも確実にできるようにするにはどうすればいいのか?という問いの先にあるのが、より一層効果的な学習方法なのだ。
一般的には、「力がつく」だとか、「この方法は私にはあわない」などの感覚論で勉強法が語られる。本当は自分にあわないのではない。自分が理想としている勉強理論に合致していないだけで、純粋に勘違いをしていることが多い。こうやれば合格するのではないかという理論と合わないだけなのである。「この方法は私にあわない」と言った人で慶應大学に合格した人を私は今までに見たことが無い。倍率が6倍以上程度ある試験なので当たり前と言えば当たり前だが、それなりに学習効果が高いことをやっていかなければ受からない。
男性が筋力トレーニングをする際にも科学的なメニューはある。この筋肉のつけ方は自分には合わないといって、重いものを持ち上げないトレーニングをする人は、10万回腕立て伏せをしても腕は太くならない。なぜならば、赤筋と言われる持久力がある筋肉がつくだけだからである。記憶も然りだ。原理原則に沿わない学習はいくらやっても効果が薄い。合うか合わないかではない。より一層科学的なメニューをこなすのか、非科学的な一般論で勉強するのかのどちらかしないのである。
そして、最後には「万人に効果的な勉強法などない」という極論かつ、あたり前すぎる言説で物事にフタをしめてしまおうとする。要はお茶を濁されていることに誰も気づかなくなってしまう。
こういう妄言を信じれば、当然だが学習密度は落ちる。「そうだ、誰にとっても最高の勉強なんてないんだよね」という精神安定剤的なセリフで自分の気持ちを納得させて、今日めいいっぱい覚えるのである。そして、受験当日、さきほど述べたように、「あれ・・・読めない、分からない、時間が足りない」ということになるのである。
当たり前だ。最初から問題を解決することから逃げた結果、「変わらない」という選択をしているのである。そのつけは受験生が支払わされる。アドバイスをしていた善良な第三者のように振舞っている人は、「あなたは能力が足りなかったんじゃないの?」などと言っていることに、その時になってあなたは初めて気づくだろう。私はこの逆である。どんな能力の人でも必ず伸ばして見せる。最初から記憶の問題解決を徹底して行うためだ。思考方法も然り、モチベーションも然り、慶應小論文対策も然りである。
筋力トレーニングに科学的なメニューがあるように、一般的に効果的な学習アプローチは十分に研究されている。従って適正論を最初から持ち出すのはナンセンスだ。私が弁護士、医師と学習方法についての本を共著で書いた時も最初に話し合ったのはこの点だった。東大法学部卒の弁護士と話をして、最強の勉強法ではなく、「勉強法最強化」というコンセプトに決めた。これは、学習を最適化することで問題解決を図るためである。学習に重要な原理原則は存在する。この原理原則から外れると、大変非効率的な学習になる。このことを踏まえた上で、さらに学習に推進力を持たせていく各種テクニックを紹介する本になっている。
誰でも、どんな人でも、結果を叩き出すためには、何が必要なのかということと、真剣に向き合う必要がある。プロブレムソルビングアプローチが有効だ。問題を解決すると決めて学習と対峙するのである。限界の記憶密度に挑戦せずして、どうしてあなたの頭のなかの記憶量を増やすことができるだろうか。できる道理は無い。慶應大学4学部に合格した辻本さんは、慶應クラスで学び、英語だけで約60冊を頭に叩き込んで合格している。やった量ではない。覚えた量である。
私が「慶應大学絶対合格法」という名前に込めた想いは、上記のような「あなたは能力が足りなかったんじゃないの?」などという無責任極まりない考え方の真逆である。私が運営する塾が他の塾と圧倒的に違うのもこの点だ。あけすけに言えば、徹底的に合格にこだわりぬいた塾である。慶應大学に絶対に合格することを目指す塾だ。従って、あらゆるあなたの行動は、結果につながることに集中してもらう。
「力がつくといいね」という勉強法をやらない。
何かにかけるようなことはしない。最初から合格することがわかっている中で、合格するための準備を着々と進めていくのである。
「万人にとって最高の勉強法はない」というのは、単なる前提の一つにすぎない。そんなことは百も承知の上で、適正論に対処していくのが問題解決である。
慶應クラスという塾では、全体の95%の塾生には、リスニングで英語力をつけてもらうが、残りの5%は、音読をしてもらう。これは学術的裏付けがある。全体の5%程度はディスクレシアと呼ばれる聴覚学習が苦手な人がいるためである。このように、適正論という問題があっても、より一層効果的な方法を選択する。リスニングを土台とするのも、研究結果があるからだ。学習効果の実験で音声学習をメインに置いたグループの成績が最も良いという実験結果がある。学習の波及効果が何倍も違う。リスニングは出ないので、リスニングはやらないというのは、言葉で考えてしまっている。また、多くの生徒指導の経験から、学習実行率を考慮に入れた場合、音声学習が優れていることが分かった。最初からダントツの結果をすべての学生に叩きだしてもらうために音声学習を実行してもらっているのである。
こんな勉強法が良いという意見は星の数ほどある。しかし、私は感覚論や一般論、単なる思い込みや、一受験生の経験談に基づいてアドバイスをしていない。慶應クラスで実行してもらっているカリキュラムは、裏付けのあるものである。そして2年連続慶應大学4学部合格、英語で日本一、慶應法学部の英語の問題で、45分余らせて合格(星さん)など、成果も折り紙つきのものである。星さんなどに至っては、慶應法学部入試で、英語の問題が簡単に感じたと述べている。
慶應クラスは常勝教育だ。最初から勝つべくして勝っている。すべて理由がある。意気込みだけでやっているわけでもなければ、単なる人の揚げ足取りからカリキュラムを編成しているわけでもない。徹底してあなたの合格にこだわり抜いた運営体制をブレずに貫く。結果につながることしかやらないのである。
本ウェブBookの最初にご紹介したのは、慶應大学の困難性である。言い換えれば、慶應大学受験における本質的な問題点(困難性)を厳密に定義することを試みているということだ。このようなステップを踏むのは、「単なる方法」が非力だからである。単なる方法が非力な理由は、結果につながらない対策をするようになるからだ。
・学力が下がった⇒塾に行ってみる。
・勉強ができない⇒家庭教師をつける。
・英語が読めない⇒単語を覚える
このような対策がなぜ空回りしやすいのか。その問題が発生した真因を無視しているからである。
・なぜ学力が下がっているのかを調べずに対策を打つ。
・なぜ勉強ができないのかを調べずに対策を打つ。
・なぜ英語が読めないのかを調べずに対策を打つ。
・なぜ小論文ができないのかを考えずに対策を打つ
結果を決定づける重要因子をリサーチせずに対策を打つと大体失敗する。
このような失敗をしないために、問題解決学的アプローチが必要になるのである。