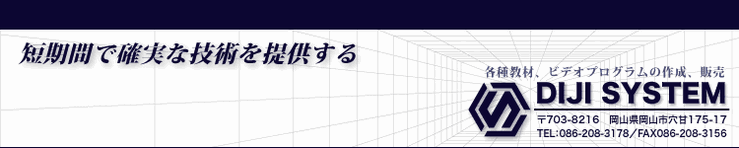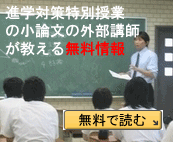こんにちは。
牛山です。
今日は嫌なニュースを見ました。
19歳くらいの若いカップルが、
民家の前にホテルで産んだ赤ん坊を置いて
、その赤ん坊が死んでしまったという
ニュースです。
少し前に赤ちゃんポストをめぐって、
論争がありましたね。
赤ちゃんポストについてあなたの意見を
自由に述べなさい
という問題があったとして、
まず1段落目に何をどう書きましょうか?
赤ちゃんポストはあった方がいいのだろうか?
と書く人がいます。
これは×ですね。
あった方がいいに決まっているじゃない!と
思う人がいるからですね。
問題提起としてはまずい。
赤ちゃんポストをめぐる問題について述べて
いきたい
と書く人がいます。
これも×です。
小論文は独り言の一人思考遊び文では
ないからです。
あくまでも論文です。作文ではありません。
ところでなぜこういう事を今日は取り上げた
かと言いますと、電話がかかってきまして、
慶應志望の子なのですが、こういう質問を
いろいろ話す中でしますと、出てこない
んですね。この子をバカにしているのではなくて、
私自身もやっぱりスッとは出てこないんですよ。
『それで30秒くださいね』
と言って2パターンの問題提起を出しました。
わりと適切に問題を提起するところは難しい
んです。
なぜ難しいかと言うと、問題提起というのは
単独で独立してあるわけではなくて、結論と
セットなければならないし、小論文の要求そのものと
セットでなければならないし、
小論文の正解のイメージとセットでなければ
ならないからです。
書きゃいいってもんじゃないんですね。
この子は書店で本を買って読んでいるのですが
やはり小論文に関する理解がまだ浅いので
以下の様なイメージがないんです。
■解答に至る正解の道筋
■小論文そのものの全体像
■小論文を解く時の思考法
これらは小論文の本を10冊読んでもあまり
改善されません。害になる本もあります。
なぜか?
と言いますと、理由はいろいろありますが、
まず、小論文とはそもそも何かという事に関する
適切な言及がなされている本があまり書店に無いからです。
ウェブサイトはいわずもがなです。
なぜ弊社の小論文は文和会という名前なのか?
それは小論文の根っこの部分にある議論の精神のような
ものが、和を作るという類のものだからです。
ところが批判したり、相手をやり込める事に
価値があると、指導している本があります。
これは×です。
自分がどういう立場で相手側の主張をやり込めよう
とも、そういう主張と言うのは評価が低い。
ある立場の人からは拍手喝采がもらえるかもしれな
いけれども、ある立場の人からは拍手がもらえない
んですね。
ところがオバマ大統領の演説はどうでしょうか?
多くの人が共感して拍手を送る。
これは、国を超えて、他国の人からも評価される
という事なんですね。
そういう風に言うと、この言葉を額面通りにとって
表面的に演説の文章を真似てしまう人がいるんで
すがそういう事ではないですよ!
まず小論文の書き方を深く理解する。
浅くではありません。深く理解するわけです。
小論文には答えがあるというのも正解ですが
小論文には答えが無いというのも正解です。
こういう事も深い理解があれば、心から
納得できるのですが、浅い理解だと、
この文章の意図している事がチンプンカンプンに
なります。
小論文とは何か?
という問いと
合格する小論文とはどういう小論文か?
という問いは別なんです。
だけれども、小論文とはほにゃららである。
こういう文章を読んで、あっそうかぁ
小論文は要するにほにゃららなんだよねと
頭の中でシナプス一本で理解されるような
一元的な論理解釈があると、小論文を書く時に
ズレズレの小論文になってしまうんです。
ところがこういう事は
まっっっっっったくと言っていいほど理解されて
おらず、毎年の様に受験シーズンに勘違いに
よる玉砕という名の悲劇が起こるんですね。
・・・で、今日かかってきた電話の子の場合は
まず何が問題だったかというと、これからやろうと
している勉強の方向性が既に問題だったんです。
慶應のSFCに合格する為にどういう勉強が
必要かという認識がずれていたので今日軌道
修正しました。少しだけ。
小論文とは何かという認識があればさらに
いい方向へ軌道修正ができるので、勉強時間が
無駄になりにくいでしょう。
変な方向に10時間勉強するのと
正しい方向に2時間勉強するのが
五分五分
小論文とはそういう世界でもあるので、
いかに浅い理解が恐ろしいか、今日のメルマガ
で分かってもらえたでしょうか?
第1段落には○○を書きます
第二段落には○○を書きます。
ハイ、小論文はこう書きましょう!
というのでは、まずいという事なんですね?
どういう風にまずいかというと、
今回のメルマガにも書きましたが、
問題提起が浮かばなかったですよね?
なんで?
それは、第二段落や第三段落は単独で
あるわけではなくて、論文のパーツとして
存在しているので、正解の方向というのは
ビシッと一本くしでささったようにはっきり
くっきりあるものなのに、そういう認識も
理解がなければ生まれようもないからです。
じゃあどうすればいいの?
深く理解したい!
という人の為に小論文講座を設けています。
※重要●文和会で教えている小論文は書店の本の指導とは別のものです。
一般的に言われている小論文はこう書け
という内容とはずいぶんと違うようですね。
主張は変らないかもしれないけれども、
内容が違うというのは、どういうことでしょうか?
書く事ができるようになる為の指導内容が違うという
事です。
例えば野球を教える監督でも色々な教え方を
しますね。
それと同じ事です。
以上、カンタンですが、小論文講座の内容も少し
ご紹介しました。
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.