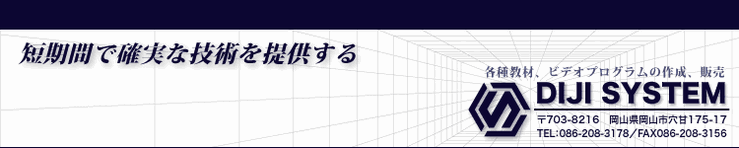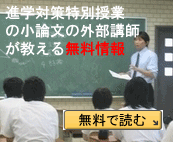こんにちは。
牛山です。
皆さんは小論文の書き方が気になっている
と思います。
今日は、その書き方よりも、もしかすると
大切かもしれない事をお伝えしますね。
●私が添削した子達の平均点と、
●問題がある人(基礎ができていない)の割合
●最も多い問題
の3点についてお話をします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●平均点について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平均点は、大雑把に50点です。
AからEの5段階評価で、大体Cが一番多い。
Bは今まで3回しかつけたことがありません。
Aは一度もありません。
うなるぐらいにいい答案でBです。
うなると言っても内容でうなっているの
ではなく、C評価が多いので、突出して良く
見えるので、Bなんですね。
Dもけっこうあります。
平均点がここまで低いという事は逆に考えれば
チャンスなわけです。
少し点数を上げれば、かなり大きく差をつけることが
できるという事でもあります。
しかしそのちょっとに力と時間を使う人がいないんですね
~
もったいない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●問題がある人(基礎ができていない)の割合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全体の9割、大体10人中9人が大きな問題を抱えて
います。
基本ができていないという問題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●最も多い問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最も多い問題は、題意把握ができていないという問題です。
設問の要求に答えていないんですね。
今回はこの題意把握について少し説明しておきます。
私が拙著【小論文技術習得講義】に小論文には答えがある!
なーんて書いているわけなんですが、これは正しくもあり
間違ってもいるんです。
あくまでも一般論として、小論文には答えがあると言っている
わけなんです。どういうことかというと、一般的に、つまり
多くの場合、小論文の問題は明確な答えに近いものが用意
されているという事です。
慶應や東大のような特殊な問題は除きます。特殊な問題が
出た他の大学、就職試験も除きます。
多くの場合は、答えがある。
これは、題意把握しなさいよ、もう答えがそこにあるじゃん
という事なんです。
もう少し詳しく話しましょう。
論文と言ったら、大学で書く論文、受験の小論文、司法試験
、弁理士試験などの論文があります。
この内、テストとして明確な題意把握が要求されるのが、
小論文と司法試験などの論文なんですね。
いいですか?
特に司法試験などの論文に関しては、試験後に論点の公表
が行なわれたりします。ここが論点だったんですよ。
ここを中心にあなたは論じましたか?
OKなら合格、ダメなら点数ありませんよ
という事です。
時々答えがありますと言うと、(子供の自由な発想を
否定するのですか!!)
なーんて、的外れな指摘をする人がいるわけなんですが
これこそ論点がずれているわけなんですね。
私がここまで主張してきた事は、試験での要求に答える
意味での答えがあるかないかという事についてですから
ここが論点です。
関係の無い突っ込みを入れたら、話がズレてますよという
事なんです。
ところがこういう事を答案でやってしまう学生が全体の9
割なんです。
採点する側はどう感じているかというと、
一言で言うと、イライラか、う~ん・・
です。
だから点数がガクッと落ちてしまう。
この論点のズレ、題意把握ミスというのは、直接構成に
影響します。
構成を型で学んでしまっている人はその本質を学んで
いないので、確かに~しかし・・・と書くと深い意見に
なるんですね・・という風に超!(超とか書いてしまいました)
短絡的に考えてしまいます。
確かに~しかしと書いて深い意見になるのは、
自分の反対意見の論拠を崩した時だけなんです。
ところが、これをとにかく使えば構成OKという風に
考えてしまうと、まずいんですね・・
うーん。もったいない!!
こういうもったいないミスをしないようにしましょう。
毎月小論文の実力を引き上げる塾コースがあります。
http://maishu.kir.jp/base/sixyouron/sr/nixyuujixyuku-tennsaku.html
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.