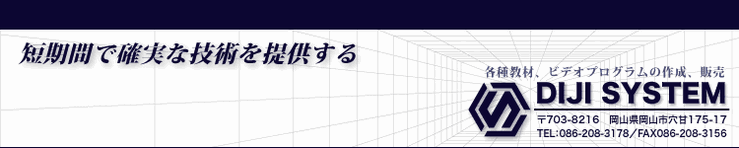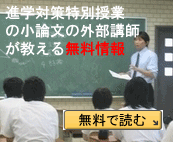こんにちは。
牛山です。
今日はみなさんにとって大変興味がある
合格数・合格率についてお話をしたいと思います。
データから仮説・推論を述べるのが小論文
でもありますので、頭の体操だと思って、
----------------------------------------------
合格数・合格率が高い予備校は、利用価値が高いという
主張についてあなたの考えを自由に述べよ
----------------------------------------------
という問題があったらどう書くか?
なーんて考えながら読んでみてください。
文和会では、一応インターネットで告知する
事で全国に小論文を学ぶ人がいる形となって
いますが、実質私が添削した人で慶應受験希望者
の合格率は、50%くらいではないかと思います。
2人に一人が合格です。
(選抜なしの数字です。選抜については以下に書きます。)
添削用紙には、志望大学が記載されています。
そうすると、ああ、ここの大学を受けるんだね
という事が分かりますので、大体の合格率を
把握できるわけです。
よく合格者数を気にする人がいますが、
合格者数は全体の母数で決まるので実は全く
意味がないんですね。
------------------------------------------------
※ここは重要でけっこう多くの人がいいように
騙されています。皆さんは騙されないようにしましょう。
広告宣伝能力は資金力に比例するので品質とは必ずしも
相関関係は高くないわけです。
SFCの過去問題で世論の形成過程について述べさせる
問題がありましたが、実学重視の問題ですよね~
宣伝能力が世論形成に影響するという事は、
資本主義の大きな構造上の問題点でもあるわけです。
こういう視点が無いと、問題把握していないんですから
有効な対策など思いつくはずもありません。
------------------------------------------------
北海道の釧路市の予備校が5000人に宣伝して
生徒を集めた場合と全国の家庭5000万世帯に
チラシ折込広告を行う予備校では合格者数が違って
当たり前だし、違わないと相当に指導品質が低い
という事になるでしょう。
ただし、当然ですが母数の数が増えるとその分
合格率も下がります。
したがって多くの場合数しか宣伝されないわけです。
合格者数と合格率が両方高いという事は、
その母集団の質がかなり高いと同時に、良質な
指導が行なわれているという事が予測できます。
つまり、母集団が既に厳しく選抜されている
状態ですね。
合格率だけを気にするのであれば
スーパークラスという選抜クラスを作り、
そのクラスは優秀な人しか入れないように
すればいいのです。
だいたい予備校はクラス分けをしますが、
後で合格率を発表する場合はこういうクラスの
合格率が発表されたりします。
そこで、
合格数と合格率から品質を推測する為の最低材料と
して以下の2点が挙げられます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●合格者数と合格率から品質(指導内容)を考察する判断材料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合格率→母集団の形成過程が精査される必要がある
合格数→母集団の数が精査される必要がある。
以上が必要最低限の判断材料ですね。
ただ、問い合わせの電話の中でも合格数を聞いてきた
人はいても、母集団の数を聞いてきたり、母集団の
形成過程について聞かれる事は一度もありませんっ(笑)
そう考えると、話はそれますが、慶應の法学部の学生は
本当に優秀ですよね。
司法試験の合格率と合格数が共にBEST3入りです。
文和会はクラスの選別を意味が無いのでやりません。
B判定の解答を書く子だけ集めたら限りなく100%に
合格率はなりますけども。
宣伝の為に分けるのも、そんなことは最初からしないので
やらないし、できない状態をできる状態に変えるのが
私の仕事なので分けることに意味がないんです。
レベル別の問題を用意するのは数学では意味があっても
小論文では、あまり意味が無い。
数学の場合は頭の中に入れた材料が無いと応用問題を
解けないことがありますが、小論文の場合はそうではない
からです。
う~ん。
でもね。
・・・と言いますか、合格する為には、合格率とか合格数
という基準よりも、何が問題を解決するのか?という
長期的な視点と、戦略、戦術の方がはるかに重要なんです。
例えば、Z会の利用方法でも、岡山大学の医学部の子と
話をしていると、東大受験経験がある子もいるわけなんです
が、数学は非常にいいと、東大対策の、数学はZ会が
絶対にいいと、言うわけなんです。
でも他の科目は使わなかったりします。
きちんとギャップを埋めていく為の勉強をしていて、
センター試験でも800点以上取り、合格しているんですね。
ところが過去問題とのギャップの中で問題解決をはかっていく
という考えが無い人は、あれがいいらしい、これがいいらしい
という風になって、判断基準を人に丸投げしたりしている
わけです。
そうすると問題解決の判断基準がズレているので当然に
合格できない・・
そういう構図があるのをいろいろな受験生と話をすればする
ほど、痛感します。
以上。
合格数と合格率のお話でした。
http://maishu.kir.jp/base/sixyouron/sr-2/tensaku.html
↑文和会では、問題の添削だけではなく、問題を解く思考過程と
解法パターン、減点につながらない解答力を養成します。
通常の添削は問題点を指摘されるだけですが、それではどんな
問題が出ても迷わず解答できる力はつきにくい、そういう問題を
解決する通信添削塾です。
単なる論理力ではなく、ハイコンセプト時代の、高い問題解決
能力が要求される慶應SFC受験者には特にお薦めです。
問題解法のコンセプトを、一般的な指導とは違った角度から
解説します。
追伸
数学の伸び悩みや、国語の伸び悩み解決を医学生と話している
とかなり痛快です。
こういう内容を記憶塾の塾生の方にはDVDでお送りしています。
合格の為に何をどう考え、具体的に何を実行すればいいのか?
その判断が一つ違うだけで、1000時間の勉強時間を500時間に
する事ができる場合もあるでしょう。
http://www.skilladviser.com/base/jixyuku/index.html
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.