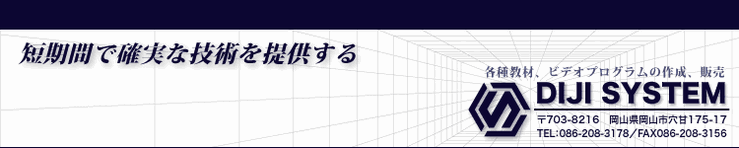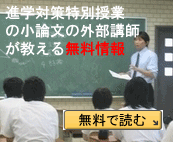こんにちは。牛山です。
ところで皆さんはこんな問題が出たらどうします?
------------------------------------------
女性が男性に恋をするって、
とってもとっても自然な事なんだよね。
------------------------------------------
そんなちょっとバカな内容も含んだ本日の内容です。
でも小論文の極めて本質的な部分に関する
内容ですから、ぜひチェックしておいてください。
さて、今日は昨日のメルマガの疑問に答えます。
疑問1 出版社が間違う事なんてあるんですか?
答え はい。あります。
私が高校生だった頃、古文を教えてくれる先生が
よく出版社に文句を言って、図書券をもらって
いました。
出版物の古文の解釈が違うと、指摘して、それが
当たっていると、御礼が届くんですね。
かなりあちこちで指摘しているらしく、けっこう迷惑
な先生だったんですが、古文を愛しているんですね。
古典研究、古典勉強マニアだったんです。
疑問2 小論文には、正解があるのですか?無いのですか?
答え
小論文には多くの場合理想的な答えがあるというのは、
本当ですし、無い場合もあります。
(パターン1)
明確に答えがあるのは要約問題の場合です。
(パターン2)
自由に意見を述べなさいという問題でも多くの大学
では理想的な答えがあるケースが多いんですね。
例えば、二つの課題文が問題にあり、その二つが
対立した意見である場合。
恐らくはその分野を専門に深くふかーく研究している学者
の先生は自分の中で明確な答えがあるでしょう。
長年の研究に裏打ちされた自分なりの理論と解釈、
調査、研究、考察の賜物。
これが論文になっているわけなんですよ。
自分が世界に向けて発信している論文がありますよね?
こういうところにからんだものを、出題したいなぁ~
というのは、問題作成者の心理としては、非常に
ありえるわけです。
(牛山せこいっ!せこいけどリンガメタリカは同じ
考えで出版されているんだよ。)
私が、多くの場合には理想的な答えがあると言っている
のは上記のケースです。まあ、だいたいがそうなんですが
もちろん、そうではないケースもありますよ。
ここの見分けが非常に、非常に大切です。
それでは、理想的な答えなんていうものは無い!
可能な限り自由に考えてみなさいっ
っていうのはどういう問題なのでしょうか?
90%以上の確率で、これは提案型という問題です。
主張するんではなくて、提案するタイプの問題。
残りの10%は、主張型だけど、極めて課題文があいまい
なタイプ。どういう風にでも取れる課題文。
これは雲をつかむ様な問題ですからよりいっそう合格の
為には厳しい嗅覚が必要なんですね。
一つ目の提案型から、具体例を紹介すると・・・
(問題)日本の教育現場で、異文化の人々とのコミュニ
ケーション能力を高める為の教育を実施する場合、
どのような授業が望ましいか。あなたの意見を自由に
800字以内で述べなさい。
というパターンかな。
残りの10%は、ほとんど出題されません。
10%ですからね。
ではこの残り10%についてはどう考えるべきなの
でしょうか?
実は既に答えを私は述べています。
-------------------------------------------------
恐らくはその分野を専門に深くふかーく研究している学者
の先生は自分の中で明確な答えがあるでしょう。
長年の研究に裏打ちされた自分なりの理論と解釈、
調査、研究、考察の賜物。
これが論文になっているわけなんですよ。
自分が世界に向けて発信している論文がありますよね?
こういうところにからんだものを、出題したいなぁ~
というのは、問題作成者の心理としては、非常に
ありえるわけです。
-----------------------------------------------------
こことつながっているんです。
どういう事?
それは、小論文という科目は、非常に面白い科目で、
現代文の記述式と違って採点官とのコミュニケーションの
側面があるということなんです。
人間が作るもので文章は人間が読むものですから、
仕方がないことです。
問題用紙のいくつかの課題文の関係だけで完結して
考えるものなのか?
それらの課題文と出題者の意図や考え、メッセージを
一緒に考えるものなのか?
どちらだと思いますか?
答えは後者です。
前者ならそれは現代文です。小論文という看板を下ろして
現代文で入試をやりますと、言うべきでしょう。
代々木ゼミナールの出口先生はよく言います。
現代文は自分の勝手な解釈を排して、筆者の主張を
読み取りなさいと・・これは、テスト用紙の中に書いてある
事の関係性だけをつかみ取りなさいという事です。
コレに対して小論文はいくら要約問題があっても読み手
がいる事が前提なんです。
この本質的な違いが無ければ、クンクン嗅ぎましょう
なんていう事は私は言いません。
つまり、小論文の答えというものがもしあるとすれば、それは
常に読み手の中にあるのであって、テストの用紙の中にあるわけ
ではないということです。
ここから逆算する事が大切です。
(課題文1)
彼女は先日好きな人にフラれた。
(課題文2)
彼女は、一週間泣き続けた
(課題文3)
彼女は、もう一度告白する事にした
(問題)
女性が男性に恋をするって、
とってもとっても自然な事なんだよね。
この↑文章を読んで、課題文1、2、3を
参照した上で、あなたの意見を自由に述べなさい。
っていう問題があったとしましょうか。
(もっと難しい形でこういうタイプが過去に
有名大学であったんですよ)
こういう問題の場合は、主張型で明確に読み手に
答えがあるというわけではなく、ほとんど提案型に
近いという事なんですよ。
つまり、読み手の心の中にある漠然とした答え
以上のモンを出してみなさい、出してもらえたら
すごいよね。っていう事です。
もし仮に読み手に明確すぎる答えがあるならば
もっと論点を明確にして、あいまいな課題文は
出さないはずです。どういう風にでも取れる文章
を出しているところがミソです。
立ち回りの自由度が低い問題は論点が明確すぎる
特徴があります。それに対して、立ち回りの自由度が
高い問題というのは論点が不明確。わざと明らかに
しない事で自由な立ち回りを期待しているわけです。
優秀な子がやってしまいがちなのは、
現代文のアプローチでこの問題を解くっていう事
です。
青天井でどういう風にでも爆発的に力を発揮できる
問題に対して、こじんまりとまとまってしまおう
とするわけです。
こうすると、読み手の中に答えがあるというルール
からはずれるし、それを提案した瞬間に読み手の
中でキラッと何かが光って、あっこれはいい答えだよね
という共感も得られなくなってしまいます。
ここまでいろいろと説明をしてお分かりいただけた
かと思いますが、答えがあるケースというのは
既に読み手が明確に答えを持っているケース。
答えが無いケースというのは、読み手が書き手に
自分の中の答え以上のものを期待しているケース。
答えがある場合はそれを察知して書く。
答えが無い場合は、期待通りうまく激しく立ち回る。
という事が大切ですね。
くれぐれも問題集の答えが答えという風には考え
ないようにしましょう。
特に東大と慶應の志望者は注意してください。
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.