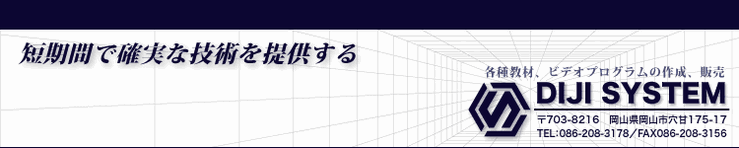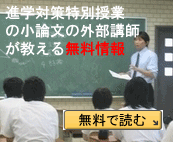こんにちは。
ディジシステムの牛山です。
今日の内容は、答えがある問題と答えの無い問題です。
なんでこんな内容かといいますと・・
私に添削を頼んできた子が、添削内容の解答例
が、Yゼミと、赤本で似ているので、これが正解
ではないでしょうか?
という意見を持っていたからです。
非常に優秀で真面目な子なんですが、もったいないので
いろいろと話したんですね。
それを皆さんとシェアしようというわけです。
皆さんはどう思いますか?
ちなみに、その時の問題は、要約問題が1問
その後に、課題文の内容を参照して、課題文4の
文章を読んであなたの意見を述べよというものです。
さて、ここで問題になるのは、正解があるのか?
それとも無いのか?
という問題です。
それを考える前にまず
添削内容の解答例
が、Yゼミと、なぜ似ているのか??
を考えてみましょう。
私の意見はこうです。
Yゼミと赤本の模範解答が同じ意見になっている
のはどちらかが片方を参照して解答を作った為。
理由は、あまりにも表現が似すぎている。
同じコンセプトを表現するとしても、言葉の表現
の豊富さからもっと違った表現であっていい
ところが、わざわざ同じような表現になっている為。
根拠としては他の資格試験や大学の模範解答
というのは、他の予備校や、専門学校の解答速報を
参考に作られることが多い。
理由2
こんな解答例を仕事でたくさん作る人は、仕事の
能率を上げ、自分のミスを防ぐ為に有名大学の
解答例などは特に他の解答例を参照するのが
もっともいいやり方であると私自身が経験を通して
感じるため。
以上の2点を根拠として、私は上記の様に、
参照したと考えるわけですね~
まあ、現実にはワカランですよ。
でも私の直感はそう言っています(笑)
問題を見た上で。
私はこういう問題構成になっている事を考えると、
問題1は要約問題を課して正確な読解力があるかを試し
問題2は、個人の資質を見る為に課している
と思いますね。
要するに大学側としては、読解力が無い奴はいらん!
そして、読解力があるだけの奴はいらん!
と思っていると・・・
そうじゃなければ現代文でいいですからね。
じゃあ次に、
正解があるのか?
それとも無いのか?について詳しく述べていきますね。
私の本を読んだ人はもう知っているかもしれませんが
、多くの小論文は、自由に意見を述べなさいと
書いてあっても答えが実はある・・・
もしくは採点者にとっての理想的な答えがある・・・
というケースがけっこうあります。
では全てのケースについて、答えってあるんで
しょうか?
自分の意見の筋道や、方向性についてパーフェクト
にあるのか?
それはね。無いですよ。
もしあったら、それは国語問題です。
やっぱりすべてにおいては、無いわけなんですね。
常に私たちは、試験を受けるときになぜこの試験なの
か?という問いがあるのが理想です。
なぜこの学部は国語ではなく、なぜ小論文なの
だろう?
なぜ配点が●●ではなく●●なのだろう
なぜ小論文は小・論文なのだろう
こういう基本的な部分に関する問いかけがないと
自分自身で作り上げた色眼鏡を通して世界を見る
事になります。
どんな人でもこういう先入観という色めがねを
かけてモノを見てしまうのは仕方が無いことですが
私たちはなるべく色眼鏡をかけずにモノを見る
必要があります。
本当のようなウソを見抜け!という本を書いた
セブンイレブングループの鈴木氏はこの典型的な
モノの見方と分析眼を持つ世界的に有名な方です。
一体この人の頭の中はどうなっているのか?
という本が出版されるくらいですから、その真実
を見抜く眼がどれほど社会から評価されているかは
想像に難くないでしょう。
■なぜこういう現象が起こっているんだろう?
■なぜこの部分にこの文章なのだろう?
■なぜこんな問いをこの問題で出したのだろう?
問題が出題される社会背景や過去との問題の比較
大学の特徴、文化、主張のあり方と度合い、
こういうものから総合的に分析判断する事を
私は本の中でクンクン問題のにおいを嗅げ!と
表現したんです。
現代文ではなく、小論文を受験科目に用意している
理由の一つは・・・
皆さんの立ち回り度合いを見たいからです。
どんな思考をするのか?その思考プロセスや
分析力、推測力、洞察の深さ、自分の主張の
理論的な背景や他の理論や考え方との整合性、
今までの考えの延長上の思考なのかあるいは
相対性理論のように、全く既存の学問の枠組みに
なかったような突拍子も無い考えなのか
あるいはそれを裏付ける明確な根拠の提示が
できるのか、その手法が優れているのか?
こういう総合的な立ち回りを見たいから
というのは、理由の一つです。
現代文ではこういう資質を見る事ができない
んですね。
どんな国語の先生が見たってこれが正解ですよね~
という範囲でしか、問題は作る事ができないわけ
です。
まとめますよ。
添削内容の解答例
が、Yゼミと、赤本で似ているので、これが正解
ではないでしょうか?
という質問に対する答えはNOです。
こじんまりまとまった考えが出来る人間が欲しくて
たまらない大学の問題ならそうかもしれませんが、
小論文ではかならず立ち回りが許される範囲があります。
それから逸脱しないようにもっと高次の思考の
枠組みで問題を捉えなおして、意見を述べることが
許される面白い科目なんだ・・・
という事は覚えておいてくださいね。
■■■■■■■■まとめ■■■■■■■■■
理想的な答えは多くの場合はあるけれども
そうではないケースもあり、解答例が正解という
わけではない。設問の要求からはずれない
範囲で高次の問題の捉え方、あるいは深い
思考で立ち回るべし。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
出版社がミスをするとか、文法的に間違った
解説をするとか、そんな事は日常茶飯事です。
私も学校の授業である学習院大学の過去問に対する
出版社の答えを国語の先生の前で論理的になぜ
間違いなのかを説明した事があります。
先入観を壊す為にも。
ぜひこのあたりに気をつけてがんばってください。
考え方のレベルをアップさせる方法は、小論文の
DVD講座、標準編・上級編で詳しく解説しています。
http://maishu.kir.jp/base/sixyouron/sr-2/7days.html
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.