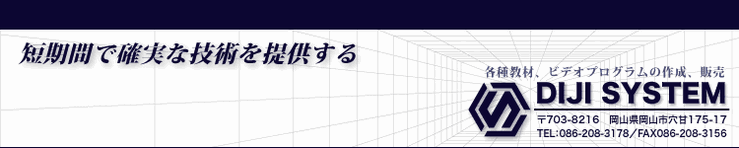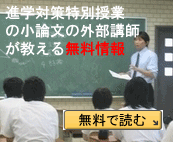こんにちは。
牛山です。
今日は以下の様な質問に理由も含めて
お答えします。
■質問:2週間後が法科大学院の試験です。
今からの最善の対策をおしえてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●牛山の答え
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでは対策を書きます。
前提)
今、日本の小論文指導は、小論文試験を経験したことが無い人や、文学部畑の
人が指導するものがメインです。その事によって、恐らくはこういう風にすれば
小論文は点数が高いだろうという様々な理論が生まれ、その理論に基づいた
指導が行なわれています。
また、このような状況下で、小論文という言葉の定義が近年どんどんあいまいに
なり、小論文なのか、プレゼン文章なのか、考察文章なのか、専門分野知識披露
文章なのか、良く分からないような状況になっています。一つの小論文指導そのものが意味を成しにくい状況ができあがりつつあるという事です。
それと同時に、問題の制作側も、多種多様な出題方法、設問の作成方法を行なう様になりました。
結論)
このような状況下では一元的な指導の意味が希薄になり、それどころか指導を受ける側の不合格リスクを増すような、おかしな現象が生まれます。
例を挙げれば、2段落目に確かに~という文章を持ってくる型にはめる指導。
→問題が多様化している為にムリに型にはめる事が、おかしな文章、設問の答えになっていない文章を生むことになり、大きな減点につながります。
アウトラインが最も大切という、卒論や投稿論文と同じ評価基準からの指導。
→先方の評価基準が、別のところにある場合に、整理されただけの文章では評価を得られないのは、卒論などの経験があればピンとくると思います。どのような新しい知見と考察がそこに加えられているかも当然ですが大きな評価基準でしょう。現実にはもっと多くの評価基準があり、多面的に自分の答案をアピールする必要があり、これが一つ一つの点数に直結しています。
具体的な対策)
1、すぐ書店に行き、小論文技術習得講義を立ち読みする(本質理解)
2、得るものがあった場合は小論文7日間プログラムを購入する
3、身近に添削してもらえる人がいる場合は必ず7日間プログラムを見終わった後に、
問題を解き、添削してもらう。
4、添削をしてもらえる人がいない場合は、すぐに小論文添削を申し込み
速達で送られた問題文を解いて送り返す。
(3回以上)
基本的な問題は意味が無いと思っている人が時々いるのですが、
実は、基本的な問題だからこそ、土台を作りやすいのです。
私の経験では法科大学院などもっともロジカルなところを受験する人で
基本部分の減点が無かった人は0%。
年齢に関係なく基本部分でごそっと大失点をしない人は20人に一人くらい
です。
したがって
添削に関しては5回添削コースを利用する方が
大学院の過去問題をなんでも添削というコースで送ってくるよりも
はるかに有益だと私は考えています。
多くの場合、考察過程を複雑にされているか、課題文の文章が難解というパターンが大学院の小論文なのですが、これでは基本となる部分の力をつけにくい
のです。
なんでも添削のコースにはDVDがつきませんが、弊社で用意している
添削のコースには、解法指針を解説するDVDがつきます。
そして重要な事は、問題の難易度は、課題文の難易度だけでは無いという
事です。
難関大学と呼ばれるところほど、考える力を試す為に多様な質問形式で
質問してきます。
何種類も或る設問の作り方への応答パターン、答案構成パターンを身に付ける
方が、最終的な得点力は上がると私は見ています。
(経験からそのような結論に達しました。)
こんな例え話だと分かりやすいかもしれません。
ここにバスケットボールのチームがあり、
大学生のチームだったとします。
マイケルジョーダンがこのチームを2週間後の試合の為に
鍛えるとします。
どう感じるでしょうか?
1(素晴らしい!それでは最上位のテクニックを話そう)
2(最初の3日は、基礎の話しかしないぞ、まずはその確認と徹底だ)
私は、恐らくですが、2番だと思います。
マイケルジョーダンの練習は非公開、マスコミ遮断の元に行なわれる
と言います。
どんな基礎の徹底を行なうのかはわかりませんが、
多くの場合問題はバラバラに存在しており、基本部分と応用部分と
細かい問題が点在しているというのが現状です。
バスケであれ、小論文であれ、それは同じです。
そして、
最終的な合否は得点で決まります。
点です。
その得点はバラバラに存在する多様な問題を個別に解決する
事で、あるいは優先度の高いものから確実に解決する事で
点数が底上げされて、
最短時間で最高の得点を実現できます。
どうすれば最も短い時間と労力で、費用対効果の大きい対策を
立てる事ができるかの答えがこれであり、
その具体的な手段がここまでにお伝えした具体的な対策です。
コストパフォーマンスが高いのは様々な角度からの質問に
対する対応力をつける事。
コストパフォーマンスは落ちても最終確認がしたい場合、
過去の大学院の問題を解いてお送り下さい。
以上が私の経験から生まれた考えです。
----------ここまで------------------------------------
他の方とシェアできる質問がある場合は
送ってみてください。
それでは、今日も読んでくれてありがとう!
がんばってください。
小論文の添削はこちら
既刊図書
 なぜ人は情報を集めて失敗するのか 目標達成論 (YELL books)  合格する小論文技術習得講義―慶應SFCダブル合格の講師が解説 (YELL books)  自動記憶勉強法―遊びながらでもほったらかしで記憶する (YELL books) |
■学生向け無料情報■
学生向けお薦めサービス
受験生向けお薦めサービス
Copyright© 2009 ディジシステム 小論文添削 All Rights Reserved.