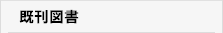お問い合わせ時間 平日PM12時~PM17時
〒706-8221 岡山市中区長岡334-1

![]()
ここからは、石原弁護士から、『新・記憶の技術』大量記憶マニュアルDVD講座についてのご感想をいただきましたので、その文章を掲載しますが、その後に、私はきちんとこの講座の良くない部分も含めて皆さんにお伝えしたいと思います。石原先生は、『勉強法最強化PROJECT』(エール出版社)という書籍を執筆する際に、ご一緒させていただいた先生です。 石原先生は、「辛口で・・・」と言及されていますが、基本的に私は大変優しい性格の先生だとお見受けしましたので、それでもやはり性格上優しい見方をしてくださっている部分があると思いました。ゆえに、私がよくない部分をもっとハッキリと言わなければならないという衝動に駆られました。 まずは石原弁護士の『新・記憶の技術』に関するご感想(主にテキストについて)をご紹介します。 -------------ここから------------- 牛山氏の「新記憶の技術」を拝見した 最初に言っておくが、自分は辛口である。 生まれは、東京下町の江戸っ子だから、お世辞はいえないし、自分自身も、極限まで修行した受験者であるから、本質でないものは認めようがない。 どうしても、見る目は厳しくなる。 その自分からみても、「記憶の技術」は、以下のようにうなづける部分が多い。 牛山氏がいうように、人生のほんの短時間だけ、氏につきあって、学んで十分 見返りがあるだろう。 まず、実践にこだわっているのがいい 氏が、認めているように、記憶術には、うさんくさいものが沢山ある。 ちょうど、「着けるだけで喧嘩無敵の~、」と同じような年頃の子供をだます、 まがいものを、自分は大嫌いだ。もちろん、実践性などまるでない。 また、ちゃんとしてても、読むだけで、一ヶ月かかるもの、氏の言う「高尚なもの」も意味がない。人の時間をなんだと思っているんだ、って話になる。 これも、実践的でない。 受験道にとって、必要なのは、「実際に」覚えることで、覚える技術は、補助だ。 たかだか、おまけに、一ヶ月はかけられない。 氏は、それを認めて、「人生で一日だけ付き合ってくれれば」といっている。 その点で実践できる もちろん、中身も、きちんと、具体的な手段を提供してくれている。 イメージや、聴覚優先という、王道のコアを提供し、それにとどまらず、イメージづけに使える時間の示唆、聴覚優先にする科目試験、そうでない科目試験の区分けなども教えてくれている。特に、イメージ付けは、具体例が、まれにみる豊富さでのっている。 そして、氏の、ウリは、実践だから、下ネタも含め、とにかく、日々覚えるときのイメージ付けの方向性を明示してくれている。 たとえば、アウトプット=書くことや解くこと、でなく、アウトプット=記憶、の部分。そうなのだ、アウトプットというと、単に問題演習と思う人がいるが、 何のためにするか、理解していない人は多い。読者はわかるだろうが、覚えるため、覚えこむため、氏の言う「記銘」のためである。 たとえば、他の方法との組み合わせや個人差を否定していない点。 同じ一流の学校や資格試験に受かった同士でも、方法は、コアは共通しつつも、細部はみな違う。これも、習熟して初めてわかる本質だ。 たとえば、無駄な努力は否定しても、努力自体は否定していないこともきわめて重要だ。 「アヒル現象」という言葉を、「記憶の技術」で始めて知ったが、一部、うそつきが、努力を否定する傾向があるが、真っ赤なうそだ。出来るやつは、めちゃくちゃ努力している、開成高校、東大、法曹界とみてきた自分が断言する。 これも、「出来るやつ」には、周知の本質である。 他にも、多々あるが、氏は、自身の修行や、沢山の生徒を指導する修行を通じ、「本質」を習得されたのだろう。 氏が、「本物」である証拠である。 結局、本物の氏が、本気で製作した、本書籍、本DVDは、やはり、本気の本物なのである。 それを、一日で、かいまみれるなら、体験してもいいんじゃないかと、辛口にしても、思う。 -------------ここまで------------- 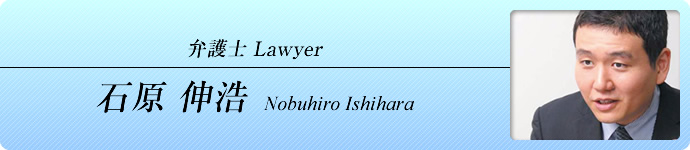
結果、「記憶の技術」は、受験をやりきったものだけが到達する、「本質」を共有させてくれる。
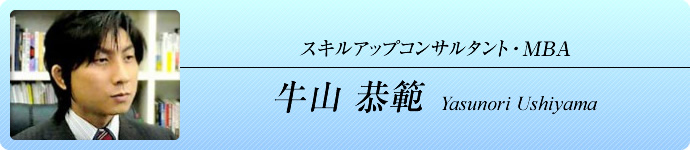
以下に、この『新・記憶の技術』製作に関する背景について、やや長くなりますが、お伝えいたします。その上で、良いところも悪いところも詳しくご紹介できると思います。
ところが、記憶の方法をいくら調べても、記憶の方法に詳しくなれど、具体的にはどう記憶していけばいいのかが分からないことが多かったのです。本や論文では、各方法の違いを説明しきれません。ある人は、声に出して読むのがいいと述べ、ある人は黙読がいいと述べ、ある人は書くのがいいと述べます。何を根拠としているのか、その仮説が正しいのかどうかも含め検証は困難を極めます。なぜならば皆違うことを勉強しており、環境も違えば、能力も違い、置かれている状況も違うからです。

アカデミックな世界を無意味だとは、私は全く思いません。しかしながら、一方で多くの人が、実用面からアカデミックな世界が乖離しているという感覚を抱いているのも確かです。その理由は恐らく、学問の世界でなされる研究や、先生方の力量にはありません。一部の人が、アカデミックな雰囲気をたてにして、「その難解さを伝えること」を通して、多くの人よりも上の立場をとろうとしてしまうことにありはしないでしょうか。
このような人は、全体のごく一部ですし、「本人も気づかない内にそうなっている」とか、「いつの間にか誤解されていた」ということも多いでしょう。このような仮説があたっているにせよ、外れているにせよ、いずれにしても、本質的にはアカデミックな世界と、実用面は、その目的という点から言えば、どこか方向性が違う部分もあるのは事実です。アカデミックの有効性についての論説として私がこのようなことを書いているのではありません。そのようなことをすれば、学問の世界に身を置く人は、大変傷つくでしょう。
また、そもそも私は学問の世界を否定するようなつもりも全くないのです。むしろ、学問的な立場が軽視されすぎる風潮は危険だと思っています。
ではなぜこの章で、学問について触れたのでしょうか。その理由は、「カッチリしていること」と「学問」を混同するきらいがあるからです。
◆学問・・・・・・実態に即す(学問的に)
◆カッチリ・・・・実態に即していないことを気にしない風潮あり。
◆知恵・・・・・・実態に即す(実践的に)
このように大変もって回った言い方となってしまったことについては、お詫びしなければなりませんが、この分野は大変ここを気にする方も多いので、この程度は前置きとしてお話しておきたいと感じました。
いつか弁護士になることを夢見ている人も、いつか東京大学に合格することを夢見ている人も、決していつも楽しいとは言えない勉強に、打ち込むことがあると思います。だからこそ、私は、こういう泥臭くも、しんどい作業をする人にとって、役立つサポートを開発できないかと考えたのです。ゆえに、大量記憶マニュアルDVD講座『新・記憶の技術』では、大変恥ずかしい方法や、アカデミックとは言えない内容も豊富に収録し、盛り込みました。よく言えば、「実践的」であり、悪く言えば、「体裁が悪い」のです。何のために、そのような形になっているのかと言えば、実践を重視するからとしか言いようがありません。
ここでよくありがちな誤解とは、情報について正確な情報、正確な知識という形で認識される誤解です。そもそも正しい知識とは何でしょうか。「正しい知識」という表現に対して、私は大変大きな違和感を抱きます。情報については、事実と解釈の2種類しかありません。正しい情報というのは、事実に基づくあるいは事実に準ずるという認識で語られるのかもしれません。ところが事実に準ずるということは、解釈であるということです。従って、やはり情報には事実と解釈しかありえないのです。
ここで問題が生じます。解釈としての論考、つまりどのように人は記憶作業を行っていくことによって、より多くの記憶を作ることができるのかということについては、各種前提条件を整理して、学問を横断的に見ていくしかありません。脳科学、心理学、言語学、各種事例研究などを通して、実態を明らかにして、どのような事実がそこに存在するのかということを、様々な論説、理論、事実を集めて多面的に見ていくことによって、有効な戦略案(記憶作業の方向性案)を導くことが恐らくはできるでしょう。この際に、問題解決学の手法を用いて、各種前提を学問的手法により、より一層確実に処理することが望ましいのは言うまでもありません。
斉藤先生は、医師の仕事という激務の中、仕事の合間をぬって、勉強情報を発信している先生でした。また、石原弁護士は、法律事務所を経営し、兄弟そろって東大法学部卒の弁護士(ご兄弟は存じ上げませんが、石原先生は開成高校のご出身。)という、勉強についてはまさしく最高の経歴と、実績を持つ方でした。
勉強の勘所、記憶作業の勘所という点において、このような優れた人物のご協力をいただけたことは、大変幸運でした。そして出来上がったのが、『勉強法最強化PROJECT』(エール出版社)だったのです。この本は出版ルートに掲載できるギリギリのラインまで、攻める本となっています。王道の勉強として一家に一冊、勉強の指針として参考にしていただける内容と、奇抜な策や、原理原則も一緒に提供する本です。
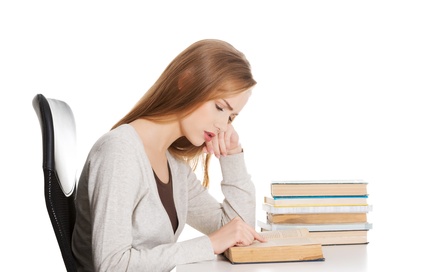
本という媒体には、限界もあります。第一に文字数の制限があります。印刷コストの問題で、多くの文字を記載できないことが一般的です。第二に、情報の性質です。映像で見せることはできません。第三に情報の文化性です。書籍を出版するということは文化的活動でもり、言い換えれば、学問上でも1つの実績足りえるものです。その出版活動においては、各ジャンルごとに独自の文化がありますが、文化的行為から外れる内容にすることには、若干の抵抗を覚える人もいるものです。本は確かに魅力的な媒体ですが、世の中を常にありのままに伝えるものかといえば、そうではないところもどうしてもあるかもしれません。
(1)ユーモアやジョークを追求しすぎるリスク

本という媒体の限界を超えることについては、一定のリスクもあります。良くない点もあるということです。例えば以下にご紹介するユーモアはその1つかもしれません。ユーモアの度合いが大きくなることについては、「良い」とみなす人もいれば「良くない」とみなす人もいます。簡単にまとめると、以下のような形です。
【良いとみなす人】
・面白いのだから良い。
・実践的で良い
・堅苦しくなくて良い。
【悪いとみなす人】
・軽薄だ。
・真面目にやって欲しい。
・堅苦しい感じで書かれていないものはレベルが低いものなのだ。
どちらも、正しいとも、間違っているとも言いにくいので、好みの問題も多分にあるかと思われます。
(2)多分に勘所を述べるリスク
事実だけを述べていくと、実態からズレるということはよくあります。分かっていることや、毒にも薬にもならない、あたりさわりのないことばかりを述べるとどうなるでしょうか。往々にして実用的ではなくなります。情報を発信したことがある人ならすぐに分かることですが、本という媒体の限界は、よくも悪くも「一般的」に問題が無い範囲をそつなく述べる性質にもあります。ブログや、メルマガ、でしか言いにくいこともあれば、電話相談でしか言いにくいこともあります。このような情報の性質は以下のような解釈があります。
【良いとみなす人】
・間違いのない情報で大変良い。
【悪いとみなす人】
・毒にも薬にもならないことが述べられており、実用面で頼りない。
感覚的なことを含めて述べることに対して許可を得ていない状態で述べた場合、
(堅苦しい雰囲気こそがアカデミックで高尚なので、レベルが高いことなのだ)という堅い信念を持っている人は
「日記のようなものだ」
「役に立たない」
「どうしようもない内容だ」
というように感じることもあります。
従って本で述べにくいことは、一般的に実際に会うか、塾や学校で教えられます。 この『新・記憶の技術』については、上記の(1)と(2)のリスクがあります。ですから、あなたがどちらのタイプなのかを見極めて、ご自身にあいそうかどうかをご検討ください。

~下ネタで覚えてもいいかもしれない?~
ただ、ここはこの記憶の冊子(『新・記憶の技術』)の良くない部分でもあるのです。ふざけたことを、軽薄であるとみなす人も世の中にはいます。ユーモアであると評価することも可能かもしれませんし、軽薄なのだ、あるいは、文章が低俗になるのだ、とみなす人もいるでしょう。
例えば、いわゆる死語となった「なーんちゃって」とか、いわゆる「だよ~ん」などの表現はこの典型かもしれません。このような表現を使うことはすなわち、文語としての日本語を卑しくするものであると認識する人もいれば、「そのくらいのことで目くじらたてなくてもいいじゃないか」と主張する人もいるでしょう。
冗談や遊びを勉強に取り入れながら自由に勉強する、感覚に違和感を抱くなど、物腰や対処方法が柔軟なことに対して嫌悪感を抱く人も世の中にはいるかもしれません。そういう人には、この『新・記憶の技術』大量記憶マニュアルDVD講座は向いていません。お申込みされないことを強くオススメします。「記憶の○○」など、やや固めの本などを手に取り、厳かな雰囲気の中で、日々の学習を行うことをお勧めします。
その理由は、戦略そのものが持つ難解さにあるでしょう。例えばある人は問題解決の学問的手法で方向性案を論考すれば、それが戦略であると説くかもしれません。しかし、私は少し違ったイメージを持っています。戦略ということを分かりやすく解説することは可能です。しかし、それが戦略の全てではないのは、戦略的な発想を常に行う人はもっとも理解されているのではないでしょうか。
例えば、以下は羽生氏の言葉です。
-------------ここから-------------
「恐れず、客観的に、相手の立場になること。そうすると自分自身や相手、場によって生み出された、勝負を複雑にする雰囲気から距離を置くことができ、結果につながる道筋が見えてきます。」
-------------ここまで-------------
これこそが戦略的発想です。戦略とは「無限の打ち手の中から浮かび上がるもの」です。逆に言えば、学習については、何が人に戦略的判断を提供することができるのかということこそが大切であると言えるかもしれません。
ハウツーを学んで失敗する人が後を立たないわけ
私の経験から言えば、ハウツーをハウツーとして学ぶ人は、失敗しやすいようです。一方で、ハウツーを、活用する目的で学ぶ人は短期間で成果を出します。
◆ハウツーを「ハウツー」として学ぶ・・・・戦略なし(盲目的)
◆ハウツーを「活用する目的」で学ぶ・・・・戦略あり(活路を見出す)
慶應大学進学専門の塾を運営する中で、このような傾向に気づくようになりました。
ハウツーにこだわる人は、判断を大きく誤ります。成果につながらないことを、継続してしまいます。そのことで、取り返しのつかない大きな損をすることもあるのです。ゆえに、まずはこのような失敗を繰り返さないためには、きちんと内容を理解し、信頼関係を築き、高いレベルでより妥当な学習アプローチで、勉強を確実なものとしていくことが大切です。

能率というのは、短時間でそれなりに生産性を上げることです。一方で効率とは、成果を出すことです。多くの人がハウツーを学び成果を出せない原因は、能率と効率を混同し、部分最適な手段を選択してしまうことにあります。
戦略とは、最後の結果につながる道を浮かび上がらせる道筋と方略です。
ゆえに、戦略とは、(勉強の世界ではなく、一般的に言うと)
・ある時は、わざと負けることであり、
・ある時は、遠回りをすることであり、
・ある時は、皆とは真逆の道を行くことであり、
・ある時は、中核的な点を突くことであり、
・ある時は、ルールを変えることです。
したがって、このような戦略的発想をするためには、少なくとも重要判断基準を頭の中に作り、物事を感覚的に感じ取る必要があります。例えば、あなたは他の人に比べてどの程度の記憶力の良さがあるのかということについては、感じ取るしかないでしょう。
必ず成果を叩き出すには、ハウツーに頼り過ぎないことが大切です。多分に勘所である部分や、ニュアンスでしか伝えられないこともあります。感覚的なものも含めた哲学的な判断もいくらかは必要になります。
失敗は、全てを手順化して考えて、受け身の学習になってしまうことによって起こりやすくなります。合格している人は、攻めの学習をしていることが多いのです。このような、攻めの学習については、気合、根性、努力、など人それぞれで、表現の仕方が違います。
【ポイント】
・ハウツーに頼り過ぎないことも大切。
・ハウツーは受け身の姿勢で勉強することにつながりやすい。
・考えずに、戦略もなく、受け身で勉強すると遅く、非効率的。
・攻めの学習については、気合、根性、努力、など人それぞれで、表現の仕方が違う。

おごり高ぶらずに、真摯に現実を観察することを私は大切にしています。私には圧倒的な記憶力がありません。つまり、他の人を圧倒的に凌ぐ頭の良さは無いということです。ただ、分析することや、結果につなげることは得意です。ここは、記憶力がそこまで関係しない分野です。
したがって、記憶力が良い人が作った講座にしか興味が無い人にも、本講座はオススメできません。
ディジシステムは、「ITとスキルアップの知見」を組み合わせ、従来は実現できなかった領域の価値を追求する企業です。様々なサービスがありますが、どれも共通するのは、『成長』です。ディジシステムを利用する方は短期間で先端的な技術や研究成果を利用し、大きく成長されることもあります。まだ読んでいなかった方は、以下の無料公開している本をお読みください。本のご感想はこちらです。
※どのような分野でも成果が出る1つの理由は、下記の書籍でもご紹介しているように、人の技術や学力、力、技能は神経細胞が活性化して物理的につながっていることに似た状態があるからです。記憶や技能を現実のものとする脳内の神経細胞を無視せず、どのような原理が存在しているのかを説いたのが、下記の書籍です。ディジシステムでは、成長の原理に基づいたサポートを行い、結果が出ています。記憶も技能も、神経細胞が関係していることが現代の脳科学では分かっています。