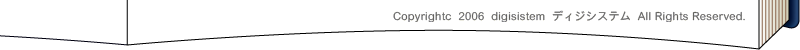�E���s��ւ̍l����
�@�����܂łňËL�Ȗڂ̕��@�ɂ��Ă��Ȃ�ڂ����������Ă����B���̂悤�ȕ��@�͈�ʓI�ł͂Ȃ���������Ȃ��B����͎��オ�ǂ����Ă��Ȃ������A�ƌ��������B�܂����Ԃ̕��@�͌��\�K���Ȃ��ƂɈ��������Ă���B�����g�A�����̍��͊��o�ŕ������Ă����B�u�Ȃ�ƂȂ�����������ǂ��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ��������́A�t���t���������o�Ɋ�Â��ĕ������Ă����B���R��������悭����Ă��܂����s�ɂ��ĕ������Ƃ���A���̂悤�Ȃ��̂����邻�����B
�E�@���̂悤�ɎQ�l�����l���Ă���A���̎Q�l�����ŋ�……�Ƃ�����ɁA�l���Ă���P�[�X
�E��w�w���ʂɍŒZ���[�g�Ƃ������̂����݂��Ă���A���̍ŒZ���[�g�������ł���u�I�X�X���Q�l���v�������Ƃ������ƂɈُ�Ɏ����S������A�S�������P�[�X
�E��������Ȃ̂ŁA�\���Z�ł���������j�̍u�`���Ȃ��ƃ_���Ɍ����Ă���ł���H�ƍl���Ă���P�[�X
�E�u�_�����A�b�v����ɂ́A���̍u�`���厖�ł�……�v�ƁA�u������w�v�Ə����ꂽ�l�[���v���[�g���炱��݂悪���ɂԂ牺���Ă��邨�Z�����ɂ������u���ɂ��Ċ��U�����P�[�X
�E�u���̗��j�̍u�`�����l���A�c��ɂR�w�����i�����I�����炱�̗��j�̍u�`����Όc��Ɏ�I�v�Ɨ\���Z�̍u���������I�X�X������Ė����Ă���Ƃ����P�[�X
�E�u�i�r�Q�[�^�[���E�j�����ǂ��Ȃ����B��������S���o�Ă��邩��B�v�Ǝw������āA���̂Ƃ���Ƀi�r�Q�[�^�[���E�j�����ʂقlj��ǂ��āA�{�Ԃ�20�_�قǂ������Ȃ������Ƃ����P�[�X
�E�o���邱�Ƃ���������A�S���܂�Ă��܂��P�[�X
�E���ڂɂ���Ă��ǂ����Y��邩��ォ���������ƍl���A�g�[�^���̋L���ʂ����Ȃ��A���c�ɍ��i�ł��郌�x���ɒB���Ȃ��P�[�X
���ꂼ��̃P�[�X�ɂ��Č��Ă������B
�E�@���̂悤�ɎQ�l�����l���Ă���A���̎Q�l�����ŋ�……�Ƃ�����ɁA�l���Ă���P�[�X
�@→�u�ŋ��v�̎Q�l���͂Ȃ��B�Q�l���̗L�p���͎g��������ŕω�����B����p�̎Q�l���𗝉���ƂŎg���Ύg���₷�����A�L����ƂŎg���Γ��R�g���Â炢�B�܂��A���̂܂܂ł͂ǂ��ƂȂ��g���Â炢���A���H������A���ǂ≹���ȂǕ��@��ς���Ǝg���₷���Ȃ�Q�l��������B�ړI�Ɗw�K�i�K�Ȃǂ܂��ĎQ�l���̎g�������H�v���Ăق����B
���������Ƃ��āA�����͂�������o������i����B���̊ϓ_�ł́A�ɕK�v�ȑS�Ă̍��ڂ������Ă���Q�l�����u�ŋ��v�ɂȂ�B���������̂悤�ȎQ�l���͔��ɍׂ������ځA�܂菬���ځi�̒��ł����Ȃ菬�������ځj�܂Ŋ܂܂�Ă��邾�낤�B�����Ȃ菬���ڂ܂Ŗԗ�����͕̂����Â炢�B
�܂����̂悤�ȎQ�l���͎����ɋ߂��{�ɂȂ��Ă���ꍇ�������B���ɂ���P�����o��������ƌ����Ă��A���Ȃ��͎����̂悤�Ȗ{����肽�����낤���H���͂܂��҂�S�������B�Ȃ��Ȃ玫���̂悤�Ȗ{�͕��{�Ƃ��Ĉ����Â炢���炾�B�ԃV�[�g�ŏ����鎚�A�|�C���g��������������ȂǁA�w�K�̂��߂̍H�v���Ȃ��A�L����Ƃ�i�߂Â炢�B���̂悤�ȎQ�l�����g���Ȃ�A��������C���Ɋw�K������̂ł͂Ȃ��A�ŏI�m�F��A�ߋ���ɏo�Ă������ǂǂ̎Q�l���ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��Ƃ��ɎQ�Ƃ���Ƃ������g����������̂��ǂ����낤�B
�@�����A���̎Q�l�������̂悤�ȎɕK�v�ȑS���ڂ������Ă��炸�A�u���̎Q�l���ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����ǁA���̎Q�l���ɂ͍ڂ��Ă���v�Ƃ������ڂ�����̂Ȃ�_�O���B��������1�̒ʂ�A��{�I�Ɏ͋L���ʂ̏������B��������o����Ώ������B����������悤�ȎQ�l�����u�ŋ��v�Ƃ͂����Ȃ��B
�@�g���₷���Q�l���A���H���₷���Q�l���A����݂₷���Q�l���͂��邪�A�P�́u�ŋ��̎Q�l���v�͂Ȃ��B�����Ă����ΎQ�l�����������Ȃ��A�L���ʂ��ő�ɂ����l���u�ŋ��̎��v�ɂȂ�B
�E��w�w���ʂɍŒZ���[�g�Ƃ������̂����݂��Ă���A���̍ŒZ���[�g�������ł���u�I�X�X���Q�l���v�������Ƃ������ƂɈُ�Ɏ����S������A�S�������P�[�X
�@→���_�I�ɂ́A�ŒZ���[�g�A���邢�͍ł������I�Ȋw�K�͑��݂��邩������Ȃ��B����������͍��i��Ɏ���I�ɕ����邱�Ƃł���A���O�A�܂�����n�߂�i�K�ɑS�Ă̖��ʂ�r�����ŒZ���[�g���\�z���邱�Ƃ͕s�\���B
�u���̎Q�l���ɂ͂��̍��ڂ��ڂ��Ă��āA�t�ɂ��̍��ڂ��ڂ��Ă��Ȃ��B�v�A�u���̎Q�l���͂��̎��_�������Ă��āA�������̎Q�l���͕ʂ̎��_�ō���Ă���B�v�Ȃǂƍl���Ă����A������d�����ŏ����ɂ����u�Q�l�����[�g�v����邱�Ƃ͂ł��邾�낤�B
�������A�m���ȃf�[�^�����ɂ������̂悤�ȃ��[�g���_�����͕��������Ƃ������B�܂����Ɋm���ȃ��[�g���_���������Ƃ��Ă��A���ꂪ���l�ɓK�p�ł���Ƃ�����Ȃ��B�l�l�u���ꂽ���قȂ邽�߁A������肻�̗��_��K�p���Ă��A�t���ʂɂȂ�A�ނ���������Q���邨���������B�ʂ̎���܂ʼn��������ŒZ���[�g�́A�w�K���I���������̎����ɂ���������Ȃ��B���̈Ӗ��ōŒZ���[�g�͎���I�ɂ���������Ȃ��B
���̂��߁A���z�̗��_���[�g���\�z��������A������x���l�����̎Q�l�����[�g��g�݁A���̌�ɒ���������������A���ʓI���B�ŒZ���[�g�ɂ�������Ď����n�߂Ȃ����Ƃ�1�Ԗ��ʂł���B�������������I�Ȍv���g��A�������Ǝ�����Ăق����B
�ŒZ���[�g�Ƃ������z�͂��������u�ŏ��̓w�͂ōő�̐��ʂ����v�Ƃ������z�ɂ��ƂÂ��Ă���B���̔��z���̂�ے�͂��Ȃ����A�Ƃ����l���̊�H�ł����ɂ������̂̓��X�N�������ƌ��킴��Ȃ��B
��w�ɐi�w���邩�A�ǂ��̑�w�ɐi�w���邩�A�Ƃ����̂͐l���łƂĂ��d�v�Ȕ��f���B�u�w���Љ�I������B�v�ƌ����邪�A4�N�Ԏ��͂̑�w�������Ă����g�A�����Ď����g�A�E���������A�w���ł���T��œ����Ă���g�Ƃ��ẮA����͌����߂����Ɗ�����B�m���ɏ]���̊w���Ƃ����قǂ̊w���Љ�͐g����߂Ă��邪�A��ʂ̏A�����̃X�N���[�j���O��i�Ƃ��Ċw���͏d��Ă���B�܂��A�E����L�����A�`����l�Ƃ̕t���������l����ƁA����(�Q�l���邱�ƂȂ�)�A�L���ȑ�w�𑲋Ƃ��邱�Ƃ��L���ɂȂ��Ă���Ɗ����Ă���B����قǂ̏d�v��������w�Ȃ�A�u�Œ�̓w�͂ōō��̌��ʁv�ł͂Ȃ��A�u������w�͂��Ă���������ō��̌��ʂ��o���v�헪���̗p���邱�Ƃ͌����Ĉ����I���ł͂Ȃ��B
�E��������Ȃ̂ŁA�\���Z�ł���������j�̍u�`���Ȃ��ƃ_���Ɍ����Ă���ł���H�ƍl���Ă���P�[�X
�@→���̃P�[�X�͗��j�����ɓ��Ă͂܂�Ȃ��B���j�ȊO�̉Ȗڂł��������Ƃ��l���Ă���l�͑����B���̍l���ɂ́A2�_��肪����B�v�l�����ƂƘ_���̔����_���B
�u��������v�Ƃ������A����ł͔��R�Ƃ��Ă���B�Ȃ���������ŁA�w�K�̂����ŕK�v�Ȃ̂��A�ǂ̒��x�K�v�Ȃ̂��l����[�߂邱�Ƃ��ł���B����ɑ��鎄�̓����́A�u�����͋L���̕⏕�̂��߂ɕK�v�ŁA���������S�ɗ�������K�v�͖����A������������x����Ώ\���B�v���B
�@����ɖ��Ȃ̂��u���������→�u�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƂȂ��Ă���_���B��������邽�߂ɂ͕K���搶�̎��Ƃ��K�v���낤���H����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�F�l�̘b�����C�Ȃ������Ă邾���ŒN�������������ƂƂ����������Ƃ�����…�Ɛl�������C���[�W�ł��邵�A�b�������ł͗ǂ�������Ȃ����Ƃ��}�ɂ����1���ŕ����邱�Ƃ�����A�{����������ǂ�ŗ������鎖��������B�v�͗����̎�i�͑��̐l����1����10�܂Ŏ��葫��苳���Ă��炤�K�v�͕K�������Ȃ��B���ɈËL�Ȗڂ̏ꍇ�́A�����n�ȖڂƔ�r�I�ɗ������ׂ��������ȒP��������A���̗ʂ����Ȃ����Ƃ������B�����̂��߂ɗ\���Z�ɒʂ��K�v�͂��܂�Ȃ��A�s�̂̎Q�l���ŗ����ł��邱�Ƃ������B�ނ���s�̂̎Q�l���̕��������I�Ȃ��Ƃ͂悭����B���̓_�ɂ��Ă̓E�F�u�u�b�N�w�\���Z�Ƃ̕t���������x���Q�l�ɂ��Ăق����B
�E�_�����A�b�v����ɂ́A���̍u�`���厖�ł�……�ƁA�u������w�v�Ə����ꂽ�l�[���v���[�g���炱��݂悪���ɂԂ牺���Ă��邨�Z�����ɂ������u���ɂ��Ċ��U�����P�[�X
�@→����ɂ��_���ɔ����B�u�w������w�x�̐l���I�X�X�����Ă���→�_�����オ��v�ƂȂ��Ă���B�u�w������w�x�̐l���I�X�X�����Ă���→�w���͐�ɐM�p�ł���→�_�����オ��v�A��1�����܂��邱�Ƃ��ł���Ζ��Ȃ��B
�@���w���Ȑl�̃A�h�o�C�X�̕����M�p�ł���B………�{���ɂ������낤���H�m���ɍ��w���Ȑl�͑����̎��������z���Ă����̂�����A�������ʂ��Ȃ��l�̃A�h�o�C�X���M�p�ł���B���ꎩ�̂͋q�ϓI�Ȏ����Ŗ��͂Ȃ��B���ہA����ɏ]���Č��ʂ��o�����l�����邾�낤�A�������A�����ɗL����w�̃u�����h�ɓ��Ă��Ă��܂�����A����ɂ����܂�Ă��܂��Ă��Ȃ����낤���B����ɂ���Ď�����P���Ȃ��Ă��܂��Ă��Ȃ����낤���B����͓��R�l�[���o�����[�ɂ���āA���̂悤�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ�������ł���B
�@���w���Ȑl�̃A�h�o�C�X�͐M�p���₷������ŁA�������Ǝ�`�ɂ����܂�Ă���\��������B�������A�w��������l�̃A�h�o�C�X���ɂ��ē˂��i�ނ̂͒�R�����邩��n��������(���͌��ʂ��o�Ă��Ȃ��̂�����A���ʂɊm�M�����ĂȂ��͎̂d���Ȃ�)�B����I�ɂ���2���Ԃ����Ă��܂��̂͂ǂ����悤���ł��Ȃ��B������ł���A�h�o�C�X�́A������������l���邱�ƁA�����Ɖ��߂���ʂ��čl���Ă��Ƃ��B���ɏ��_���҂́A���_���̗��K�ɂ��Ȃ�̂ł��Ў��H���Ă݂Ăق����B�{���ɂ��̍u�`�͗L�����A���K�I�ɗ]�T�����邩�A�����ɑg�ݍ��߂邩�A�E�\��_���̔�Ȃ����A�g�D�̘_���ɏ]���ē����Ă���̂�……�v�l��[�߂Ăق����B
�@�Ƃ���ŁA�Ɋւ�����������Ă���ƁA���܂��܂Ȍ������̐l�����M���Ă��邪�A�w���ŏ�������āA���̐M�����f����͖̂{���ɂ�߂Ăق����B�w���⌨�����ɑ��āA���m�ɏ�������邱�Ƃ�����(�c��SFC��蓌��̕����̂��āA����̒��ł����V����ŁA������n�[�o�[�h�̕����ゾ�낤���H�ǂ���y�U���Ⴂ�����Ĕ�r�ł��Ȃ��B)�����A����ɂ���ď��̖{�����l(���g)�͕ς��Ȃ����A�����s�тŌ��ꂵ���B�w���͂����܂ŎQ�l�ɗ��߂Ăق���
�@���łɋ�����l�̊w�����������������I�Ƃ����������ɂ��G��Ă��������B�u�`�͒m�������ɒm���Ă���l���m��Ȃ��l�ɋ����邱�Ƃ�����A������l�����w���ȕ����������邱�Ƃ������Ƃ����̂͊m�����낤�B�������w���ɂ���ċ�����X�L���ɏ����ƌ����Ă̓E�\�ɂȂ�B�w���͖������Ǖʂ̒i�K�Ő��܂������������l�����邩������Ȃ��B�܂����w���ȋ��t�ł��A���k�����ĂȂ��Ƃ���ʼn��`��������X�L������b�����Ă�o�C�g�u�t������B
�E���̗��j�̍u�`�����l���A�c��ɂR�w�����i�����I�����炱�̗��j�̍u�`����Όc��Ɏ�I�Ɨ\���Z�̍u���������I�X�X������Ė����Ă���Ƃ����P�[�X
→������_���ɔ����B�u���̍u�`����→�c���3�w���ɍ��i�����v�B�ԂɁA�u���̔N�ɂ��܂��ܗ\�z�����������v�A�u���̐l���u�`�ȊO�ł߂��Ⴍ��������Ă����v�Ȃ�ē����Ă����������͂Ȃ��������B���Ȃ������̐l�̍s�������S�Ƀ}�l���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����܂Ŕ|���Ă����l�ԑ��������ȂǕ��ȊO�̓_�͑S���Ⴄ���炾�B�t�ɁA�u�`1�ō��i�����܂�ƍl���Ă���Ȃ�l�����ɂ��قǂ�����B
�@�Ƃ���ŁA�c��N���X�𗘗p�����l�ɁA�c���3�w���ǂ��납4�w�����i���āA���̌�͋L���m�Ƃ����T�[�r�X�𗘗p���č����œ�֎�����1�ł�����F��v�m������1�����i�����l�����邻�����B�����炱�̃T�[�r�X�𗘗p����o�c�O���̌��ʂ��o�܂���I(�{���ɂ����Ȃ��T�[�r�X���ȁH��1�x�����~�܂邱�Ƃ��ł�����i�ł�)�B
�E�u�i�r�Q�[�^�[���E�j�����ǂ��Ȃ����B��������S���o�Ă��邩��B�v�Ǝw������āA���̂Ƃ���Ƀi�r�Q�[�^�[���E�j�����ʂقlj��ǂ��āA�{�Ԃ�20�_�قǂ������Ȃ������Ƃ����P�[�X
�@→�w�i�r�Q�[�^�[���E�j�x���悭�o���Ă���Q�l�����Ƃ����_�ɂ͎^�����B�̂ĂĂ��܂������Z�̐��E�j�̋��ȏ�����Ƃ��Ď������p�������A���J�Ȍ����œǂ݂₷�����A�p�o����������ׂ������Ƃ܂Ŗԗ��I�ɏ����Ă���B���͎g��Ȃ��������A���W���t���Ă���B�܂����ǂ�1�̕��@�Ƃ��ėD�G���B�L���ւ̒蒅�̓o�c�O���ɗǂ��B
�@�������A���̓_����������Ă��S�̍œK�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����œK�̐ςݏd��≠�S�̍œK�A�Ƃ������Ƃ͊��Ǝg�������Ȃ̂ł��łɊo���Ă������B�Ȃ��{�Ԃœ_�����Ȃ��������͐��m�ɂ͕�����Ȃ��B�����炭�́A�������Ȃ����A�p����L�[���[�h�ƍ��킹�Ċo�����Ȃ������A���ǂ̎���������������߂ɋL���ւ̒蒅�����ʓI�ɏ������Ȃ����A�A�E�g�v�b�g��ƂɊ���Ȃ������A�Ƃ����������������I�ɍ��킳�����̂��Ǝv���B
�@��������1�A2���番����悤�ɁA�͌���ꂽ���ԂŋL���ʂ��ő�ɂł���Ώ��B�܂�g�[�^���ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��֎����͈�{���ł͕K�����E������B�S�̍œK�̎��_��ێ��������悤�B
�E�o���邱�Ƃ���������A�S���܂�Ă��܂��P�[�X
�@�ËL�Ȗڂ͊o���邱�Ƃ���������B�܂��A����Ⴀ�������B�����n�Ȗڂ�藝�������₷�����A��������o�������Ȃ���ނ荇�����Ƃ�Ȃ��B�������ǂ�ǂ�Y��Ă����B
�@������������Ƃ����āA���߂�قǂł͂Ȃ��B�������ȒP�Ȃ̂�����S�̂����炤���Ƃ͖��Ȃ��B���Ƃ͊o���邱�Ƃ���肾�B��������͂����܂Ŗ��ɂȂ�Ȃ��B1�x�o���Ă��܂��A���ɂ��Ƃ��̘J�͂͂���Ȃɂ�����Ȃ��B�Y�p��ɒ���I�ɕ��K�����邪�A�Y��Ă��܂��Ă�����ȂɋC�������Ƃ͂Ȃ��B����1�x�o�������������B�������ĉ��x�����K���Ă����A�{���Ɋo�����Ȃ����ڂ͂قƂ�ǖ����Ȃ�͂����B�����A�L����Ƃ͎����I�ɒP����Ƃ̌J��Ԃ����B���Ƃ͂��C�̖�肾�B���C�̓R���g���[����������A���i�ƈႤ�����ł���Ă݂�A�C���[�W���g���A���i��̎�����z������Ȃǂ��ď����Ăق����B
�E���ڂɂ���Ă��ǂ����Y��邩��ォ���������ƍl���A�g�[�^���̋L���ʂ����Ȃ��A���c�ɍ��i�ł��郌�x���ɒB���Ȃ��P�[�X
�@→������L����Ƃ����Ă��Y���(��������4)�A���ꎩ�̂ɊԈႦ�͂Ȃ��B�������A�Y�p��Ƃ��āA�u�L����Ƃ��ŒZ�X�P�W���[���őg�݁A�Y�p������O�Ɏ�������v�Ƃ����헪���̗p����̂͊댯���ƍl����B���Ȃ��قǎ��Ԃɗ]�T���Ȃ��ꍇ�ȊO�͂��̕��j���̗p���Ȃ��B���Ԃɗ]�T������̂Ȃ�A�����ŏЉ���悤�ɁA�Y��邱�Ƃ�O��ɂ��đΏ�����B
�@�Ȃ��L����Ƃ���ɂ���Ɗ댯�Ȃ̂��낤���B���̗��R�́A���ς���\���A�L���Ώۂ̗ʁA�]�T�s���ɂ���B
�@�L����Ƃ���ɂ���Ƃ������Ƃ́A�����܂łɂ͋L�����Ԃɍ��킹�邱�ƂɂȂ邪�A���̎��Ԃ�i�s�x���ǂꂭ�炢���m�Ɍ��ς�邾�낤���H���ɂ́A���R�A���i�܂łǂꂭ�炢������Ηǂ����Ƃ������o���m�����Ȃ��B����ɁA�����ɂ͑��̉Ȗڂ��v���悤�ɐi�܂Ȃ��A�a�C�E����Ŋw�K���i�܂Ȃ��Ȃ�ȂǁA�ËL�ȖڈȊO�̗v�����e�����Ă���B���̂悤�ȏł́A�v���g�݂��Ƃ͂ł��Ă��A���̌v��ʂ�ɐi�މ\���͒Ⴍ�Ȃ�B
�@���ɁA��w�ł͋L�����ڂ̗ʂ��������āA�Y���O�ɎɗՂނ��Ƃ͎����I�ɕs�\���B���E�j���Ɏ���čl���Ă݂悤�B���E�j�̗����ƋL����Ƃ��ς܂��āA�區��→������→�����ڂ���ʂ肳�炢�A��背�x��(�Ő킦��Œ�C��)�̂�6����(�������m�F)���������B��背�x���ɂȂ�������w�K�𑱂��Ă������A���̌�2,3�����͋L���̌����ł��Ăׂ͒����J��Ԃ����Ă����B�����܂ł�8,9�������������B����͎��Ԃ��t���Ɏg����Q�l���ł̂��Ƃ�����A�����������Ƃ�������A1.5?2�{���āA12�����A�܂�1�N�ہX�����邩������Ȃ��B
�@���̒ʂ�A�L����Ƃɂ����\���Ԃ�������B��ɂł���قNjL���ʂ͏��Ȃ��Ȃ��B�����A�區��→������→�����ڂ���ʂ肳����������ŎɗՂ����Ƃ���Ȃ�A�����x�����B�����炭�A�L���̋��x���キ�A�u��������Ƃ����邯�ǎv���o���Ȃ��v��ԂɂȂ鎖�̂��������邩�����Ă݂�Ƃ����B
�@�����܂Ō�헪�̖��_��������Ă����B���̐헪�̖��́A�ËL�Ȗڂɉ��Ԃ����Ȃ����ƂɋN������B���Ԃ����Ȃ�����v��̏C�����ł����A�{�Ԃł��L���ʂ����Ȃ��Ȃ肪���ɂȂ��Ă��܂��B�ł͂��̖��̉������j�͂ǂ̂悤�ɂȂ邾�낤���B�P���ɁA�ËL�Ȗڂ։��Ԃ𑝂₹�����B�ËL�Ȗڂ͂����قNjL��������(�Y��ɂ���)�ɁA��ʂɂł���B�ł��邾���������ԁA�L����Ƃ����āA�L���𑝂₹�Ζ��͉�������B���ꂾ���ŕs���i�ɂȂ郊�X�N���w�b�W(���U)�ł���Ȃ�������̂��B�Ɍ��炸�A�ڕW�B���̂��߂ɂ͎��ԂƋ��������Ղ�p�ӂł���قǗL���ɂȂ�(�����q���Ȃ���……)�B����������Ȃ�ςȗ��R�ŏo���ɂ��݂���͔̂��������B
�@�ȏ�ŁA�ËL�^�Ȗڂ̃|�C���g�Ƃ悭���鎸�s�ɂ��Ē��X�Ɛ������Ă����B�����R�c�����闝���n�Ȗڂ₻�������͈͂��傫������p��ȂǂƔ�ׂ�ƁA�ËL�^�Ȗڂ͕��ʂɂ���Ă���A��֎����ł��A���ʂɍU���ł��Ă��܂��B���̃E�F�u�u�b�N���Q�l�ɂ��āA���ЈËL�^�Ȗڂ��˂������A���i���Ăق����B
�f�B�W�V�X�e���@�g�n�l�d