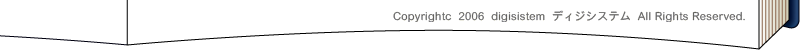Ⅴ センスを磨く7つの対策
(1)センスを磨くことはできる
センスを磨くことはできる。センスとは経験の積み重ねの結果生まれるものでもあるからだ。先天的な要因もあるが、後天的な要因もある。以下順番にセンスを磨く方法についてご紹介していく。
(2)対策1:ハウツーに頼りすぎない
私の経験では、ハウツーに頼る人ほど難関試験に合格しにくい。頭の働かせ方が、感性も含めた総合的なものではなく、ハウツーになるとどのようにまずい問題が起きるのか。何も考えなくなるということである。知識をはめ込む、構文にはめこむ、フレームワークにはめ込む、ネタを入れる、手順にはめ込む、これらの作業は大変楽だ。頭を使わない。しかし、総じてパフォーマンスは下がりやすい。当然頭を使っていないに等しいので、表面的にしか考えられていない。
(3)対策2:「見えていないもの」を見る努力をする
センスが無い場合、本人には感じ取ることができていないものがある。ファッションセンス、バッティングセンス、思考センス、文章のセンスというものは、あるか無いかと言えば、存在する。
ところがセンスが無い人からすれば、自分が何を見えていないのかが分からない。自分が分からないので、(センスなど無い)と思うこともある。そういう場合は、美容室に行ってみよう。センスがあるスタイリストが多いことにすぐに気づくだろう。このように視覚的にはっきりと分かる分野は、認知しやすい。運動神経も同様である。
一方で、文章や思考のセンスについては、見えないので、認知しにくい。みな同じに見える、あるいは、単にいかめしく書いただけの文章が素晴らしく格調高く見えるのは、単に自分のレベルが低いだけである。ところが往々にして人は自分の気持ちが大きくなりがちであり、若いときにはその傾向も強い。
自分で言うのもなんだが、自分が書いた小論文は相当よく書かれている・・・と思ってしまうのだ。これがそもそもとんでもない勘違いであることも多い。(恥ずかしい)という気持ちが薄い場合、センスが磨かれていない可能性を疑おう。私が運営する小論文の塾では、生徒が予測点数を記入する欄がある。センスがいい人は、自分自身が書いた小論文の点数について、比較的評価に近い点数を予測することができていた。この予測点数がズレている人の点数は総じて低い傾向にある。見えていないものを(分からない)と考えないことだ。(センスなど無いのだ)と考えるのも良くない。(自分はすごいのだ)と考えるのは最もよくない。自分が他の人よりも優れていると思っている人は、そうではない人に比べて総じて思考力が低いことが研究によって示唆された。
要するに、「モノが見えていない人」ほど、他人のレベルが低く見えるということだ。自分が見えていないからそう見えているに過ぎない可能性が極めて高いということである。
従って、職位や経歴、保有資格や学歴にかかわらず、他者の持つ能力の複雑性や潜在性に想いが至らないのは、大変危険であると言わざるを得ない。
(4)対策3:一流に触れる(本、音楽、映画など)
センスを磨く良い対策の一つは一流に触れることである。最初は何も分からなくてもいい。一流と言われるものを見て、一流と言われるものを聞き、一流と言われるものを読むことが大切だ。一流の人物に会えば、何が優れているのかについて、勉強になることもある。一流に触れさえすれば、すぐに物事が見えるようになるわけではない。
しかし、あなたの感性は一流の感性に刺激を受ける。新しいものの見方や感じ方を、あなたはできるようになることもある。あなたは、一流の人物が描いた絵画を見ても、その成果物しか見ることはできない可能性が大きい。その画家が描いた際の頭の中をのぞくことはできない。
一流に触れるということは、凡庸な感性を飛び越えて、その思想や哲学、ソウルに触れるということでもある。その時にあなたが感じ取る感覚が重要だ。その感じ取る感覚にあなたの感性を反映させるように、今度はあなたが何らかの感性によって増幅された成果物を出すのである。
何もインプットせず、生まれた瞬間から、ジャングルの奥地に住み、何にも触れず、何十年も生きた人が、突然人の心を打つ音楽を奏でることはできない。それは単に、音楽の記憶が無いからというだけではなく、後天的に感性が刺激を受けていないからである。まずは一流と呼ばれる音楽から聞いてみよう。
(5)対策4:美意識を持つ(方法 VS 感性)
美意識を育てよう。あなたの中にある独善的な美意識を育てることではない。あなたが他者の美意識に触れ、一流に学ぶことで、その美意識や哲学を育むことである。感性は美意識だけから成り立っているわけではない。
しかし、感性は美意識に集約される性質も持つ。「芸術は爆発だ」というセリフで有名な岡本太郎氏は、「先生、芸術はドカーンと爆発するということですね。」という質問に対して、「そんな下品なものではない。もっと静かなものだ。」と不満を述べた。静かに大きく爆発するという感覚は、恐らくは岡本氏の何らかの美意識の表れなのかもしれない。
このように、どのような感性であれ、いかようにも働く感性が何らかの思想や哲学の中で、一つの体系に集約されるということは、なんらかの評価を受けているということである。これを美意識と表現することは妥当ではないかもしれないが、ここでは分かりやすくするために、「美意識」と表現した。
あなたは、文章や思考に(美しい)という感覚を感じることができるだろうか。論文の構成として美しい、思考方法が美しい、思考の発露が美しい、表現手段が美しい、その発想の展開が美しいなど、もしもこのような何らかの美意識が全く芽生えていないのであれば、あなたの文章は、小論文試験でも高い点数を得ることが難しい可能性が大きい。美意識を育てるには、思想や哲学を学ぶことが重要になる。ネタ本を読んでいる場合ではない。
(6)対策5:論文の多読
小論文試験を受験する人は、論文を多読することが良い勉強になる。ただし、論文を読んでも内容が分からない時に、(何これ、意味わかんない)などと不満をもらさないことが大切だ。恐らくほとんどの論文について、大学受験生ならば何を書いているのかさっぱり分からないことが予想される。仮にそうであっても、論文の構成や文章の書き方について、勉強になることが多いものだ。
(7)対策6:思想と哲学を学び、指導を受ける
文章を書くことや考えることについて、ハウツーレベルにとどまらず、深く教えてもらうことが望ましい。ハウツーレベルでしか教わらなければ、あなたの書く内容は、ハウツーレベルになることが予想される。
(8)対策7:謙虚に己の力をわきまえる
謙虚に素直に学ぶことが大切だ。あなたが見えていないものは、存在しないのではない。あなたが見えていないだけである。自分の成長がストップするのは、自分はたいそうなものだと考えたときだ。従って何歳になっても、初心を大切に、謙虚に技術を磨いていくことが望ましい。