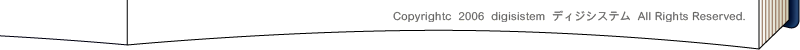ところで、
地球温暖化説については、慎重論もある。
地球温暖化否定説のわかりやすい論拠の一つは、地球温暖化で巨額の利益をあげる企業が存在することだ。そして、具体的には何が事実でどう考えるべきかについて、多くの書籍が出版もされている。
地球温暖化が嘘なのか、嘘ではないのか、興味が無い人が多いだろう。
問題の一つは、地球温暖化は、このような社会問題の氷山の一角にすぎないということである。
私達にとって、恐ろしいことの一つは、(私は常識人でありたい)という願望である。
もっと言えば、私はあまり突飛なことを言って、人におかしく見られたくないという誘惑であり、現代人はとにかくこの誘惑に弱い。
しかし、一方で、学術を中途半端にやってしまうと、あまり文献調査をすることもなく、事実を把握することもなく、論理的に考えることもなく、その前提を調べることもなく、常識を疑うこともなく、
単に多くの人がそう言っているというだけの理由で、何も考えずに、Aが正しいとか、Bが正しいと言ってしまうのが現代人の特徴である。
その背景にあるのは、冷笑主義であり、主知主義だ。
問題は・・・・
第一に、冷笑主義的であればあるほど、推論能力が上がるわけではないこと。
第二に、懐疑的であればあるほど、推論能力が高くなるわけではないこと。
第三に主知主義的であればあるだけ現実を正しく認識できるわけではないこと。
(主知主義とは知識主義的に物事を見て考える態度のこと。)
このような原理原則は、現代社会における根本的かつ基本的な誤謬であり、現代人の認識を大きく誤らせる元凶となっている。
私達は、年齢、学歴、性別にかかわらず、人を見下してしまうことが多く、それよりも、事実を把握せず、考えることもなく、何かを信じることが多い。
言い換えれば、何かについて懐疑的な人は、この心的傾向が強いので、懐疑的であれば懐疑的であるほど、常識人であれば常識人であるほど、主知主義者であれば主知主義者であるほど、騙されやすいということである。
この人は騙されているな・・・
という場合、もう一つのポイントは、この類の人は、他の人が何かを信じているのだという、妄信主義的な考え方が支配的であることだ。
このような考え方は、かつてオウムサリン事件などを発端として、何かに洗脳されるという社会通念が支配的になった時代により顕著となった。
つまり、何かを信じている人は愚かというわけであり、信じるとか信じないということが人の知的活動の根本にあるという誤解である。
一般的に人は何かを信じることがあったとしても、世の中の人すべての認識能力が同じなわけではない上に、理解力にも違いがあり、思考力にも違いがある。従って判断力に差が出てくる。
このような事情を頭から除外するきっかけとなった大きな出来事がオウム事件だ。(今の若い人は知らない人も多いかもしれないが、カルト教団が起こした無差別殺人テロである。)
しかし、たまたまオウム事件が起こったという具合に現代人はすべての出来事をたまたま偶然の産物と見なし、何がその背景にあるかを考えたりはしない。
このように、人の先入観は、多重構造的であり、現代人は見事にこの多重構造の先入観を自分の中に作り上げている。
そのため、現代人的な発想としてよくある疑問に、
『何を信じればいいのかが分からない』
というものがある。
『何が正しくそれはなぜか』とは、現代人は問わなくなってしまった。
頭の中に入る情報量が多くなることで、人は自分で判断することを放棄する。
その分立派に現代人的に、いな、常識人的に、物事を考えていると多くの人は思うが、多くのケースで『常識』に判断は丸投げされている。
そのため、物事を深く考えることはせず、常識の後追いをする人が増加してしまった。
逆に言えば当塾が非常識な成果を出し続けることができている一つの理由はここにある。
常識が正しくないためである。現代人の多くは常識は正しいという宗教の信者のようになっている。常識は誰かが作っているとは考えず、世論の形成システムは純粋に偶然であり自然であると考え、文化も考えも偶然生まれていると考える人が多い。
賢者は歴史に学ぶという言葉がある。しかし、現代人は歴史には学ばない。なぜならば、古い歴史は粗野で愚かな文明社会の今よりも一段と劣った社会であるとみなしているためだ。
歴史の中に秩序や法則性を見出す人は稀であり、その内容を解析できる人もほとんどいない。そのため、現代人の社会的な病理とは、慢心がすべての人に形作られる社会システムにある可能性を疑うことには価値がある。
ところで、ある土地の地層調査に置いて、過度に濃縮されたウランが土壌から出てきたという事例がある。この場合、多くの現代人は何を考えるのだろうか。答えは何も考えないである。つまり不合理な自分の常識に反するあらゆる事実には目をつぶり、なかったこととして扱い、ひたすら常識にトレースした思考を続けることが、現代人的な【あたまがいい】なのである。しかし、言い換えれば、考えない、事実を把握しない、判断しないということであり、この結果できることは、常識人っぽくふるまうことができるので、少なくとも平均的な常識人から見た評価を下げないという程度のことである。
多くの人が信じる常識とは、例えば東大を頂点としたヒエラルキー構造であったり、権威である。そのため、東大合格者が『英単語は鉄壁がいい』と言えば、理由もなく鉄壁が神参考書などと考えるようになる。
当塾では、一つ一つ原理や仕組みを紐解きながら、もっとも学習が効果的になるように牛山が教育プログラムを再設計している。
そのため、非常識な合格報告が続々と寄せられている。
書ききれないが、何度模試を受けても上位1%、一橋受験生の中でも上位1%、偏差値20台から約半年で慶應法学部合格(23900人中23600番台であった)、英語全国模試1位など。
小論文は慶應文系6学部全勝合格、毎年のように4学部合格者輩出、全国模試1位の報告を3年連続でもらう、短大卒から慶應大学院合格など。
普通なことをすれば普通の結果になることは自明なのに、多くの人はもっともふつうなやり方で突破しようとする。
あるいは、長文問題が出れば長文問題集、AO対策ならAO塾、FITならFIT専門塾というように、考えることをやめてしまい、何が妥当なのかを考えることなく、テーマだけで同一的な内容を選択することが利口だと考える傾向も見受けられる。
FIT入試は面接と論文試験なので、面接がダメならダメ、論文がダメならダメである。
面接で高い点数を取るにはどうすればいいか、
論文で高い点数を取るにはどうすればいいか
と考えることは、思考の最低限のレベルとなる。
一般的に、高い判断力のベースとなるのは、高い理解力である。
少し前のところで紹介した地球温暖化に関する論文についても、内容がチンプンカンプンということならば、判断につながりようがない。
この意味で、自分の理解力は高い方なのかどうなのかを考えることも、適切な判断をする上で大切になる。
塾の生徒が同時に同じことを聞いている場合に、同じ理解力で内容を把握することはない。
皆理解力は違う。
ここまでの内容を言い換えれば、このように、多くの人の勘違いを見抜くことができるかどうか、あるいは、多くの人の勘違いを論理的に指摘できる講師かどうかが、妥当な教育を提供できる一つの目安となる。
なぜ牛山の言うことを信じた方がいいのですか?というご質問に対して、私が返答するなら、間接的な理由の一つはここになる。
分析モドキが社会には氾濫しているので、分析という言葉を軽々しく使いたくはないが、問題の分析が得意なレベルと、判断力は一般的に大きく相関することが予想される。
私はこのような分析や洞察が得意だから本を35冊書いているのであり、コンサルタントを仕事としている。他の人がよくわからないことをまとめて、これだけやればよいという具合に提示するのが、生まれつき得意というわけだ。
言い換えれば私はモデルのような美しさは持っておらず、高い計算能力があるわけでもなく、頭の回転の速さ自慢ではなく、記憶力が他の人より人一倍優れているわけでもない。私が得意なのは、分析や洞察、問題発見と問題解決である。
私が推論能力と数学の成績についてデータを取得したところ、むしろ逆相関であった。つまり、計算能力が高くなくても推論能力が高い人は多いということである。
そうなってくると、いわゆる『その仕事に向いている専門家』が大事になってくるわけだが、
物事を信ずべき理由と、選ぶ理由は異なる。
つまり、例えば牛山の場合、信ずべき理由は以下のようなものである。
- 塾の実績
- 指導者の実績
- スキルアップの研究実績
- 常識が多くのケースで間違っている
- 慶應進学の専門性
- プレゼン入試の合格実績(牛山は東工大にプレゼンで合格)
- 塾業界では高い研究力
- 各種能力の高い到達性
- 高いレベルに到達しなければ合格しないという現実 牛山だけではなく大学教員もある指導をダメだと述べている。
ところが、選ぶべき理由ということになると、途端に話は難しくなる。
例えば、少なくともここまでに述べた内容を理解する必要が判断の前に必要となる。
その上で、情報に出会う必要がある。
つまり、センスと運である。
ビジネス界のベストセラー作家である本田氏は、誰を師とするかはセンスの問題ですと述べた。
つまり、なぜあなたを信じていいのですか?という問いは、私のセンスに任せて判断すると、あなたは魅力的な感じがしますが、そうでもないような気がします。
ということになる。
少なくとも本田氏によれば、
ポイントは、この感じ方は個人のセンスによって異なるということである。
つまり、魅力は客観的ではなく、主観的かつ相対的となる。
かつて船井総研の船井氏は、物事に対処する専門家は、プロと超プロに分けられると述べた。その上で、同氏は、超プロに仕事を依頼することの重要性を力説した。
なぜか。
超プロは判断をその領域で誤らないからである。
もっと言えば、判断が得意な人は判断を誤らない。
また、判断が得意な人は、この超プロの判断を幾重にも重ねて判断することが多い。
しかし、せいぜい一つの業界で、超プロは、一人、多くても二人程度である。
この日本における学習カテゴリでは、手前みそだが、牛山がその超プロだと自負している。もう一人いる。そのもう一人は、和田秀樹氏である。彼は本物だ。
東大に行きたいなら和田氏に学ぶのがいいだろう。慶應に進学したいなら私に学ぶのがお勧めである。
ところが、ここまでにお伝えしたように、和田氏の知性の高さを感じることができない人は、ついついミーハーな選択をしてしまいがちである。
その理由の一つは運にある。運は運ぶと書くが、運ばれてくると考えるのがよいだろう。
その根拠は、少なくとも数千年分の様々な人類の叡智が関連するが、根拠などはここではのべないことにしておこう。
なぜならば、認識力が人によって違うということを考えず、理解力が不足している可能性を考えず、自分の判断力は常に人より高いと考える人は、この手の最も思考が難しい領域の話はすべて、くるっているようにしか思えないからである。
従って、分からないことは、判断を保留することを私はお勧めしたい。
牛山さんはなぜ慶應受験に関して、正しいのですかという問いは、ここまでに述べたように、永遠に解決しない問題である。
物事を認識判断する能力は人によって大きな違いがあり、下から上は見えないが、上から下は見えるという原理が存在するためだ。
従って、認識力が不足する人は、常に多くの人の気がくるっていると考えるようになり、(現代社会は、その病理が加速している。)愚かだと考えるようになる。
自分が判断できないことについて、人に判断の根拠を求めても、その判断の背景には、一か月間つきっきりで教えても教えきれない知識と思考がある。そしてそれらをすべて教えても、私の経験から言えば、理解できない人もいる。そして、その理解できない根本理由の一つが、人が持つ慢心である。ここまでに述べたように、慢心が最も人の判断力を低下させ、盲目にする。
そのため、慢心から発信した疑問に対する答えを慢心が理由となって誤判断するという負のサイクルから人は抜けられない。
このような事情は、ピアノ、習字、体操、スポーツ、音楽、その他あらゆる教育分野において共通する。
生徒が先生に対して、『先生、なぜあなたは自分の指導が正しいと言えるのか』と問うとき、その生徒の心は、学ぶための十分な準備が無く、誰に学んでも何も成長しない負のマイナスに作用する因子が、見えたり隠れたりしている。
時折生徒は、この自分の慢心に気付き、闘おうとするも、先入観が強く、あまりにもこの慢心の力が強いことに屈し、自分のプライドを守り、かたくなになり、先生に挑戦してしまう。そして、あらゆる人に慢心の心から生まれるヒエラルキーで勝ちたいという気持ちが芽生え、成長が止まっていく。
非常に大切なことなので、ややあいまいな物言いを少しだけ許していただきたい。
慢心とは、本当のことを言えば、私たちが暮らすこの世界の中で最も強い力である。あまりにも強大であり、人間が人間である根本原理であり、人間が人間足り得て、もっとも下等な生き物となってしまうものである。慢心があるから、人は成長できるが、慢心が最も人を不幸にして、その人の人生の喜びを少なくさせる。慢心で人は不幸になる。そして、繰り返すが、この慢心が、この世界で最も大きな力を持っている。
従って、私は慢心を最も恐れる。慢心は知らず知らずのうちにしのびよる。背後からきづかれないようにそっとあなたに近づく、もちろん、私にも近づく、そして、知らないうちに心を支配し、判断力が低下し、精神的に愚かになり、人格が崩壊する。この慢心にこころがおかされる程度は人によって異なるが、抵抗するもっともよいやり方の一つは、一日に何度でも反省し、自分を顧みて、成長できないかを考え、謙虚であることを何度も願うことである。私は一日に少なくとも5回は謙虚にと心の中で唱えるようにしている。
従って、先生なぜあなたは正しいのですかという質問は、師を選ぶ前と、あとでずいぶんと事情が異なってくる。
少なくとも師を選ぶ前は、誰もが自分で判断できないため、センスに頼るしかない。その上で、あれが正しいのか、これが正しいのかと思いをめぐらせることは悪いことではない。
センスが働かなければ、優秀な人でも、レベルが低い指導を受けることに甘んじてしまうことがある。
その理由は、現代的に言えば、運としかいいようがないが、あとはセンスの問題である。
ここまでに述べた内容はあなたの人生を決定づけるだけでは足りない。
あなたの人生の根本にあるものに、大きくかかわっている。
しかし、その内容はこのウェブブックでは言及できない。
そこで、音声で分かりやすく今回の内容を説明した。
ぜひ参考にして、夢や目標をかなえ、根本的な部分で、人生を失敗しないように、気を付けてほしい。
あなたの命が、よりよいものとなり、幸せと喜びに人生があふれますように。
【音声】なぜあなたは正しいのですか?
再生速度: