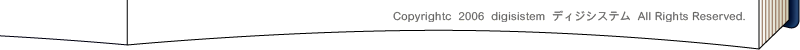小論文の本を読んだ人が出している結果
小論文指導は、わりと混乱している。
様々な主観に基づく良い、悪いという意見がある。
そこで少なくとも事実ベースで考察していくことが大切だ。
私の本や小論文の添削の方向性は、以下のような実績が出ている。
・約1万人中全国10位、総合政策学部合格。(中村君)
・模試で全国6位。(平井君)→SFCダブル合格。
・北海道大学法科大学院に第二位で合格、授業料免除で進学。
・トリプルE判定からの総合政策学部への逆転合格。(渡邊君)
・E判定からの環境情報学部へ逆転合格。 (守矢君)
・進学校ではない高校から慶應法学部に進学(星君)
・慶應大学4学部合格。(辻本君)(法・経・総・環)
・全国模試で10位。
特徴は一言でいうと、急上昇である。
もう一つはトップ層の成績になっているということ。
つまり、事実ベースで相対的に小論文の成績が急上昇している。
もし仮に、間違った方向に導いているのであれば、この実績は明らかに
不自然である。
私は神仏ではないので、絶対に正しいことしか言わないということは
ない。大上段に構えて、自分だけが世界で唯一正しいという顔をして
高みの評論を決め込むつもりもない。
私がやっているのは、世界のグルと言われた大前研一氏や
世界一のコンサルティングファームと言われる
マッキンゼーのOBの教授から教わった思考法等を
生徒に伝授し、生徒と切磋琢磨して精進することだ。
毎日が勝負だ。
小論文で学ぶべき範囲は、本当は広大
小論文試験を楽にこなして、パッパっとやればいいよ!
という指導は、確かに存在する。
この類の言説というのは、たいてい天才肌の人か
頭脳明晰な人の指導である。
長嶋茂雄がかつてバッティング指導を求めれた時
(念のために説明しておくと、長嶋茂雄は、伝説的な
バッターである。)
『うーん、バッとボールが飛んできますね?
それをね、バーーーン!!と打つ。分かった?』
と言い、質問した若手のプロ野球選手は何も分からなかった
というエピソードは有名すぎるくらいに有名である。
つまり、天才は、プロのプレーヤーとして一流だが、
コーチとしては一流とは限らないということである。
例えば、次のような話をすれば分かりやすいかもしれない。
論理思考と言えば、誰でも知っている。
論理的なものがどんなものかも、少し教えてもらえば
説明できるようになるだろう。
しかし、これと論理思考ができるということは別だ。
私はMBAのコースの大学院で、通算100回近くの論文
を書いてきた。毎週の論文の課題は、どこまでも
真剣勝負。
真に論理的に物事を考えるために、東大卒や東大院卒の
クラスメートは、議論を重ねて論文を書いた。
そうやって、2年間学び、MBAを取得して卒業してもなお、
論理思考が簡単だなどと言える人は、卒業生の中には一人も
いないだろう。
『一生勉強です。』
と、大前研一学長は言った。
物事を論理的に思考するということは、未来の予測も、
意思決定もすべてを含む。
未来がどうなるかを予言できる人などいない。
それでも、今手元にある情報から、未来を予測しなければ
ならない時もある。
自分がわかったつもりになるのはたやすい。
しかし、分かったつもりになっている人ほど、
思考力が低いことが研究によって明らかになっている。
このように、たった一つの論理思考という点を取り上げる
だけでも、物事の難しさは分かると思うが、この
広大な範囲を学習するにはどうすればいいのか。
私がお勧めするのは、手前味噌だが私の本を3冊読み、
できれば無料で提供している小論文の冊子を読むことである。
1)「小論文技術習得講義」・・・小論文の感性を強化(右脳面)
2)「慶應小論文合格バイブル」・・・慶應小論文への適応
3)「小論文の教科書」・・・論理思考・問題解決思考を強化(左脳面)
ガッツリやればほぼ受かっている
小論文の勉強と、小論文の添削をガッツリ受けた子はたいてい慶應大学に合格している。
小論文をコツコツやるのは地味な感じがして嫌に
感じる人が多いのかもしれない。
もしそうならば、だからこそチャンスである。
小論文の配点が高く、多くの人が点数を取ることが
できない小論文試験で点数を取ることができるように
なれば、あなたの慶應大学合格の可能性は高くなる。
ぜひ元気を出して小論文の勉強に取り組んでほしい。
質問や、お問い合わせは下のフォームよりお受付しております。
慶應絶対合格情報(無料メルマガ)の登録→無料メルマガ登録
※ここでしか手に入らない、慶應合格・不合格情報、英語、暗記法、思考法小論文対策を無料提供!
メールマガジンではサービス・役務のご案内もあります。その為にメールマガジンは無料提供となっています。プライバシーポリシーはこちら・メルマガ解除はこちら
合格実績 慶應クラス資料請求 慶應クラスTOP ディジシステム HOME